試聴映像
- 1. 幼い子どもの教師ほど人格者でないといけない
- 2. 先生の卵に伝えたこと 〜 教師にとって最も重要な資質
- 3. 家庭に問題を抱えた子どもが教師に見放されたときの不幸
- 4. 講演で若い先生達に訴えたこと 〜 生徒にレッテルを貼らないで
映像を観る
概要
教育に携わる方からのリクエストに応じ、優れた指導者となるためのヒントについて話す。子どもに関わる上で教師は両親の次に重要な存在であり、その影響は非常に大きい。子どもに良い影響を与えるために必要な教師の資質や視点について話す。また問題を抱える子どもの家庭環境に触れながら、教師が果たすべき役割についても述べる。
映像編集者のオススメポイント
-
私は小学校の頃、体罰が当たり前のような教室がイヤでよく学校を休んでいました。あぁ。。。学校の先生が竹下先生のような先生だったらどんなに幸せだろう。そして子どもにとって学校が安心できる平和な場所であってほしい。切に思いました。
-
映像配信開始以来、竹下氏が学校教育と教師の役割について講義1本まるまる語ったのは初めてです。多くの方に観ていただくことで、子どもたちが幸せに過ごせる時代が早く来てほしいです。親子シリーズ、子育て無料書籍、かんなままさんの連載も併せてご覧ください。
目次
1.(質問9-1)今の子どもたちや彼らへの教育に関する話を聞きたい (00:00:04)
教師が子どもに関わる上で最も大切なもの、それは教師自身の人格である。その人格が与える子どもへの影響とその重要性について話していく。また教師に求められる姿勢や態度にも触れる。今生まれてきている子どもたちの魂についても述べる。
2.(質問9-1に関連した話題)家庭に安らぎがない子どもたち (00:21:10)
勉強に集中できない子どもたちの多くは、家庭環境に何らかの問題を抱えていることが多い。家庭崩壊の実例を挙げながら、そのような不幸な環境にある子どもたちに対して教師が果たすべき役割について話す。
3.(質問9-1に関連した話題)本来の教師の役割とは (00:38:55)
教師の大切な役割は、生徒に気と心を配ること、そして学ぶ楽しさを伝えることである。生徒は教師の言動を細かく観察している。そのことを認識した上で、教師が生徒1人1人にどう接するべきか、またどんな視点を持つべきかを話していく。また教師が絶対に避けるべき、生徒に対する差別的な扱いについても触れる。
4.(質問9-1に関連した話題)いつでも生徒のありのままを受け止めることができるか (00:57:09)
教師は生徒に対し、偏見を持たず、いつでもありのままを受け止めることが重要である。かつて竹下氏は教育委員会の研修講師として呼ばれ、若い先生たちにこのことを訴えた。そのとき伝えた具体例として、登校拒否で引きこもりになった子の心を竹下氏が解放し、社会的に自立するまで回復させることができた体験について話す。
終わり(01:14:48)
※詳しい目次は、映像を購入してログインすると見ることができます。


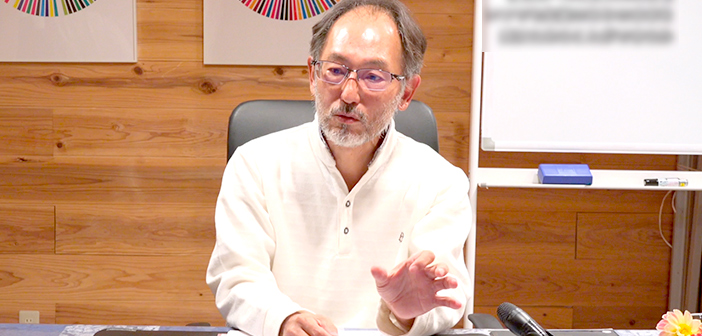




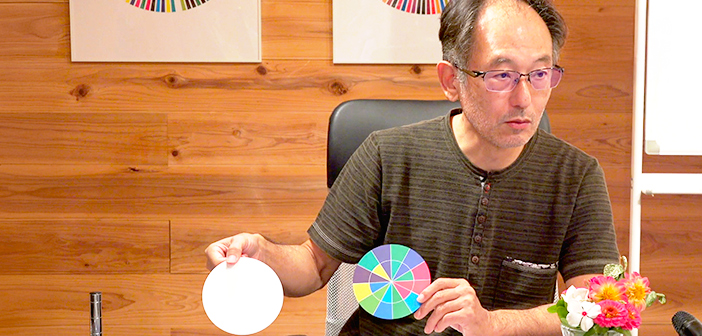
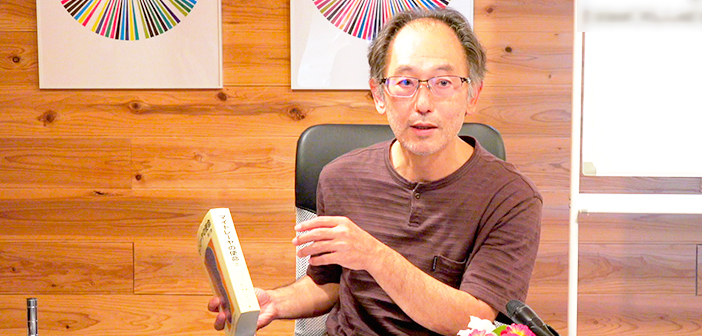

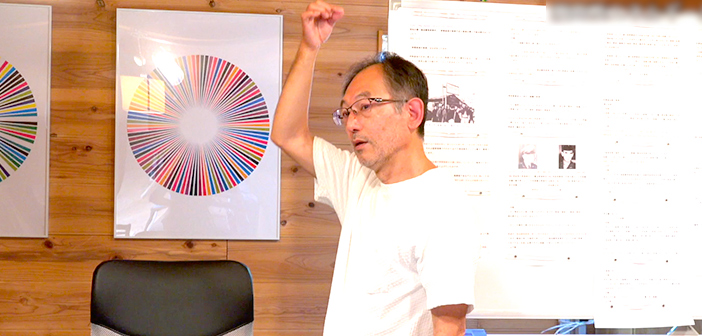
17件のコメント
今回の講義も教育者のみならず全人類必見という感じで内容が濃かったです。
自分の子ども時代の先生たちはどうだったかな…と思いながら観ました。
立場差のあるコミュニケーションは支配・抑圧・管理…となるのがひな形みたいになってますね。
親と子、教師と生徒、先輩後輩、上司部下…。
子どもは天から授かった宝という言葉にうるっときました。
その宝を光らせるのか曇らせるのかは、親や教師にかかっているということですね。
なんらかの理由で曇ることがあっても…登校拒否の女性のように…また立ち直ることができる。
それは希望に感じました。そこでも少しうるっとしました(泣き虫)。
ありのままに受け入れることが救いになるんですね。
今回の配信を通して、竹下さんが伝えたい事が、ひしひしと伝わって来ました。
ちゃんと受け取れていたらいいなと思います。
お話しの中で涙ぐまれた時は、どれ程深い愛をお持ちなのかと感動しました。
終始、深い愛を感じられるお話しで、竹下さんの愛が身体の中で広がっている感じがします。
沢山の愛を、ありがとうございます。
低学年ほど人格的に優れた人が先生であるべき、に
本当にその通りだと思います。
私はいま子育て真っ最中ですがその中で思ってきた事
行動してきたことを竹下先生がお話されていて
うんうん頷きながら拝見致しました。
勉強は楽しいものなんだというのを教えてあげたくて
学校を選びましたが中々思う通りにはいかないものですね。
先生がおっしゃる100人に1人の先生たちばかりの学校だったら
途中で魂をなくす子もぐんと減るだろうなぁと思いました。
多くの人にこの映像が届きますように。
私は高齢者の部類に入り、孫とも遠隔地に離れて生活をしているので、子供たちと接する機会は今世中には無理。今から思えばもっと抱きしめて育てれば良かったと後悔するも、息子夫婦の子育才能は遥かに私を凌駕しているので一安心。私の魂が残るように頑張って来世では正しい子育てをしたいと強く願いました。
話は変わりますが、先日レプリコン接種者の客と応対した際、強力なシェディングで仕事続行が不可能になる事態に…教えて頂いている対処法はすべて実行しているので、数時間後には復帰でき、今のところまだ私の身体の中でレプは増殖していない模様。何の防御もしていない幼い子供達をこの先どうやって守ったらよいのか?頭の痛い問題です。
–
Stupid old man local civil servant様
コメントの一部を削除して公開させていただきました。
今後ともよろしくお願いいたします。(シャンティ・フーラ)
レッテルを貼って対応するのが当たり前の世の中なので、レッテルを貼らずに
ありのままを受け入れることは、普段から意識しないとできないですね。
簡単なようで簡単でないと思うのは、簡単なことを勝手に難しくしてしまっているだけなのかも。
ありのままを受け入れる・・これを頭の中で思い浮かべると、キリギリスのパパが出てくるのは
私だけなのかな?
いつも貴重なお話有難うございます。社会の基本は教育ですが、現在の成績偏重な教育では社会が歪むのも当然だと思います。
先生になるのも、試験の成績。先生になってからも、クラスの生徒のテストの成績で評価されている。
多少は人格での評価もあるとは、思いますが…評価基準が全然駄目だと思います。
竹下先生のおっしゃる通り、教育にお金を掛けて先生を2倍以上に増やして、先生一人あたりの負担を減らさないと、より良い人格形成の為の教育は望めないし、現状では社会がより良い方向に向かはないと、改めて感じました。
私も、支配的な親に育てられ、学校に入りいじめもあり先生に相談しても、拒否されて案の定心の病になりました。
あの時に良い先生に出会えていたら少しは良い思い出や、前向きな心になれたのではと思います。
先生になる方々も、教育虐待や、ありのままの心を認めるなど経験がないのだと思います。
私はそんな自分だった
と気づいて今、心の勉強をしています。
自分をみつめて、ありのままを受け入れていくことをしています。
今では心を通わせられるパートナーとも出会い、楽しくなって来てます。
人間は、学校の勉強だけではなく、心、愛、など目には見えない本当の教育が必要だと教えて頂いたお話でした。
ありがとうごさいます。
講話が、素晴らしすぎて、胸がいっぱいになりました。
子どもが、小学生の時に、竹下先生を知りました。私は、やや機能不全家庭で育ちましたので、自分の子育てに不安がいつもありました。子どもの心があぶない。私の心もあぶないという時がありました。その時に、夫に相談し、大きく生活をかえました。世間からの、厳しい視線 雰囲気も感じました。いろんなことがありましたが、大学生になりました。娘は、大学の本屋さんで、野口晴哉の体癖文庫本があって、購入したことを報告してくれました。よく、体癖の話をしていたから、覚えていたようです。息子は、家の本棚から、体癖上下巻を抜き、下宿生活に入りました。 教育についての、一問一答。私が、もし、YouTuberなら、サムネイルに、教師みろ!と、書きそうです。子どもたちの心に、よりそってくれるように社会が成熟しますように。
幼い頃から、教育に対してなんとなく感じていたモノクロの違和感に、竹下先生が色をつけてお話ししてくださった感覚で、スッと心に入った講話でした。
子供ながらに、私のように勉強ができない子や、親との関係がうまくいかずに学校で鬱憤を晴らす子、授業に集中出来ない子など、どこか心に翳りを抱えた子たちがありのままに受け入れて貰える場所はないのか?
こんな場所通うなんてしんどいな、と頭の中でストレスを感じていました。
精神が成熟し、子供に敬意を持って暖かい気持ちで接してくださる先生がいたならば、何人の子供達が救われるんだろう、と教育に新たな希望を持つことができました。
世間的な間違った「当たり前」と、自分の心のそれに対する違和感に、
いつも真っ直ぐに向き合ってくださる講話ばかりで、心があたたかくなります。
ありがとうございます。
感謝でいっぱいです。
これが人に対する愛なのだと実感して、見終わった時に涙があふれてきました。
毎朝ガヤトリーマントラの「除霊と浄化の祈り」を行って、仕事が休みの時に「愛のマントラ」を行っていますが、正直「愛」とは如何なるものかが分かりかねていました。
妻に対する「愛」は分かるとしても、人に対する「愛」と言うのはこの映像配信で分かりました。
見て良かった!
今までの自分の考え方や、子供たちに対しての考え方を改めて修正出来る内容でした。
本当に感謝いたします。
まったく同感です。
僕は、はるか昔、中学校の子の家庭教師をしていた時、学年最低から学年10番以内にしたこともありました。
でも、テクニックを教えてはいません。
あるとき、土方のバイトで疲れていて、難しい問題を出して、できたら起こせと言ってバイト時間寝てました。もちろん解けないから2時間ぐっすり眠れました。
でも何故か親が別の部屋で仮眠してたみたいで、首になりました。でも、ずっと兄ちゃん兄ちゃんとその後も懐いてくれてました。
僕も劣等生だった(今も)ので、彼らがどこでつまずいてるか分かったつもりだったからうまくいったと思っていたけど、後で思うと、彼らと一切隔てのない付き合いだったからだと思ってました。今回の講義は、懐かしい思い出で、終始涙があふれて止まりません。
竹下さんは、学校が必要と今回はおっしゃってますが、いま僕はこれからは、寺子屋方式で教育は進めることが必要と思ってます。以前から竹下さんも子育てで学校に疑問を持っていたみたいだから、どこかで寺子屋方式の考えを伝えていただきたい。できればでいいです。
人間社会は優劣をつくる社会。「これも悪い人達が創った社会の仕組み」と、別の映像配信で学ばせて頂いてるので、この世界は更に悪くなっているんだと、分かる様になりました。
「競争社会」の考えを信じていたので、有利な方(例:勉強が出来る、世の中上手く渡る)に入ろうとする生き方をしてきました。昭和の時代は失敗から学ぶ、弱い子を守る、その子から学ぶなど、融和する考えがまだ有りましたが、今は効率人間化が加速して失敗を許さない社会になっていると思います。
AIに置き換えられる社会が加速していくなか、心からこんな社会は間違っていると思わないと変わらない、つまり子供達に良い社会は生まれない、、と思いました。
今の子供達には「学校が嫌なら行かなくていい」と逃げ道を作ってあげる事は大切に感じました。
最後に(学校に行けなかった)学生さんのお話から、意識が変わる事で導かれる未来が変わるのかな・・と思いました。
子育てと教育、結婚もしておらず、子供もいない私には無縁の講義かな・・・と思いつつも拝見いたしました。
お話中に竹下さんが涙ぐまれた時、ものすごくショックを受けました。
子供が愛されないことに、こんなに傷ついておられる・・・母なる神々さまもどんなに苦しまれていることだろうか。
私は実際に我が子を愛することは出来ませんが、愛されてこなかった『子供の自分』を愛してあげることは出来ます。
今まで、自分を許して愛することが大切だと頭では分かっていましたが、そうしようと思うと必ず、自分を否定する気持ちが出てきてしまい、なかなか出来ませんでした。
この講義を聞いて、そんなことを言っている場合ではない、これ以上神々さまを悲しませてはいけないと強く思いました。
やっと、否定せずに、自分に愛してるよと声をかけてあげられるようになってきています。
神さまに愛されていることを忘れずに、続けていこうと思っています。
悟りって、『やっぱりそうだよな』ってことかなと解釈しました。
現代社会のように、人間の相互利害や利便性のため益々複雑化していく中で、
生命が生存のために上手に周囲の環境に順応しなければならない宿命の中で、
単にそれらに巻き込まれ過剰に生存適応するのではなく、魂の本心に気付くこと、
また気付きながらなお愚直に生きる事、それが悟りのように思いました。
その意味では、悟りには魂が必要なのかも知れないと思いました。
私などは、日々過酷な快適生存競争の中、巻き込まれっぱなしで周囲を悪く捉え
たりと恥ずかしながらさんざんですが、でも全く愛がない訳でもないと感じています。
ただ、ほぼ生存と一体化してしまうと、人生に光も艶も感動もなくなってしまい、
そういう人は、はるかに深い愛を持った方々から見ると、相対的に魂(光・愛)が
無いように感じるのかも知れないと勝手に解釈しています。
今回のようなお話を、以前より一貫して確信をもって発信し続けておられる方は、
やはりそのようなお方なのでしょうと思う今日この頃でした。
そのようなお方でないと、そのようにできない、と私も思いました。
以上は私の拡大解釈です。
元教員、紆余曲折あり今は0歳から高校生までの子どもとその親に関わる教育(学習塾)の仕事をしています。
講義丸ごと一本教育のお話、ありがとうございます!!
子どもが小さいほど、低学年ほど、教育者は人格者でなければならないとのこと。自分が人格者かどうか、生真面目に考えこんでしまうとお仕事出来なくなりますね…。でも天職と思っているからには、少しでも人格者に近づく努力をし続けないとですね。とにかくはヤマ・ニヤマを守り、ガヤトリーマントラを欠かさないようにしようと思います。
ところで、気を欲する子、たくさんいます。家庭に恵まれた子が多くみんな可愛いです。でも東京都内の受験塾も乱立する地域で、両親たちはますます共働きが当たり前、幼少期から子どもたちは沢山の習い事。疲れている子どもも多いです。お母さんに言いにくいけど、早く帰って家でゆっくりしたいってこぼす子もいたり。心が痛みます。
子どもたちの心が少しでも安らぐよう、全ての子どもたちに気を配っていきたいと思います。満足した子は自立が進みます。
竹下先生の話を聞いて、確信しました。将来は、優しい眼差しのおばあちゃん先生になりたいかなあって。
私は教員ではありませんが、大学生と過ごす日々を送っています。
1人1人にちゃんと気を配るということがいかに大事か先生の講義を聞きながら噛み締めていました。
実際にやっていくと本当に難しいです。
今回の講義はよりハッ!とすることも多くありました。
教育や部活動を通していかに生徒をコントロールしていくということに重きを置いているように思われる今の学校での現状で教育機関と教員の価値観とこの講義を通して竹下先生から学ぶ価値観がいかにかけ離れていることか、、、。
子供が将来教員になろうかと思っているようです。
今は中学生でもう少し先になると思いますが、いつかこの講義を一緒に見たいと思っています。
大切なことを先生の講義を通してですが伝えていきたいです。
こころに誰もが太陽を抱いて生まれてくるのに、子供も大人も関係ないのに、間違った価値観を植え付けられて、ぽかぽかのこころを感じられずに病んでいってしまう。
「ありのままでいいよ、そのままでいいよ」って言葉は、暗く冷たい世界を、あたたかくて煌めく世界に導いてくれる魔法のような言葉ですね。
いろいろ共感しながら拝聴しました。ありがとうございました。