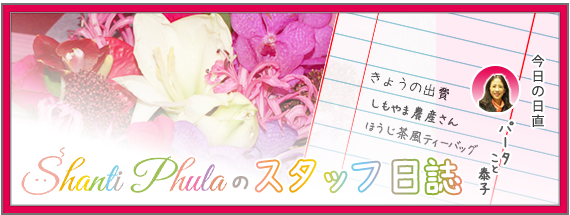皆様、上映会が立て続く、良い日和の9月であります。
あさって21日には、広島市東区できらめきの花さんの上映会があります。皆様、是非ご参加くださいますよう、お願いいたします!
さて、一つ前のひな豆の会さんの上映会の紹介記事にコスモスの花の中に、アゲハ蝶が写っているのに、気づかれましたか!?
◆ 9月21日 きらめきの花さん 上映会のご紹介◆

日時:9月21日(日)13:30~16:50(13:15~受付開始)
上映会テーマ:家族の絆 ~親子(16)
背く子背かれる親(未熟な親) ~81分
13:30~ DVD上映
休憩
15:00~ 交流会(1時間50分)…自由参加です。
場所:広島市東区民文化センター3F 小会議室
(無料Pあり)~広島駅から徒歩9分 地図はこちら
参加費:500円
みなさま こんにちは~
野原や山の裾野のあちこちに、すすき、彼岸花、
紅紫色の花をつけた山萩が姿を現し秋の到来を告げています。
久しぶりの上映会です。
親世代の私たちへのメッセージ~必見です!
~講演のなかから一部抜粋~
いつも博打をやっているような成果主義はやめなければいけない。
こういう社会を作ると、ものすごく不安定で
それが崩壊したときに悲惨な社会が待っている。
社会の仕組みを変えないといけない。
社会全体をどういう仕組みにしたら人々がもっと豊かに
本当に自分がしたいと思うこと、
好きなことをして生きていける社会をつくりたい訳ですね。
1.親の本心と不安定な社会
2.未熟な親
・なぜ嫁姑の問題が起こるのか?
・息子・娘夫婦を別れさせようとする親のエゴ
・食べる物が同じだと考え方も似ている
・(余談)もしも息子と音楽の趣味が違ったら・・・
・(余談)世界最高レベルの歌と最低レベルの歌
・自覚すべき子供に対する親の立場
・孤立する男、孤立しない女
3.人間としての自立
4.ものの考え方と態度
5.教育の誤り
今回は、干し椎茸2種類(波動が良いものと波動が悪いもの)を
提供 していただきました。
干し椎茸の波動を感じ取ってくださいね。
皆さまのお越しを心より楽しみにお待ちしています~
初めての方もお気軽にご参加くださいね~
きらめきシスタ~ズ
◆ 7月20日 上映会のご報告◆

日時 :7月 20日(日)13:30~16:50
上映内容:家族の絆 ~親子(15):背く子背かれる親(思春期の要求)
場所 :広島市東区民文化センター 3F
暑い中、ご参加頂きました皆さま、本当にありがとうございました。
前回から三回に亘り野口晴哉氏の本『背く子背かれる親』から
文章を取り出して、一生の流れという形で説明をしています。
また、一般的な育てられ方の標準的なモデルを紹介して、
そこに潜むいろいろな問題点を話しています。
今回は、いかに自発の行動・自由が大事であるかということで、
思春期から結婚するあたりまでのことを話されました。
『野口晴哉氏の時代は介護のシステムなどなく、
子供が親に孝行するのが当たり前で、
嫁姑の問題が起こると「それは嫁が悪い」になります。
それは年寄りから見た視点であって、
冷静に見たら本当のところはどうなのか分かりません。
「背く子 背かれる親」は舅、姑が勉強するために書かれている、
そういう本だと思っていただければいいと思います。』
各2種類の「きな粉とスパゲティ」のサンプルが話題を盛り上げました。
皆さんがそれぞれ何度も手にとってみたり、
じっと波動を感じてみたりととても有意義な時間でした。
学び合える場として、
(感動を)共感できる場・共有できる場
があってよかったとの意見もありました。
年齢を超えて人の様々な経験や生き方を知り、
知恵を学び気づきを得ることを幸せに思います。
皆さまの温かいご支援のもと上映会を開催できますことを感謝いたします。
きらめきシスタ~ズ
☆交流会でのご意見、上映の感想等☆
★人生を生き切る。自発的な仕事のできる社会、将来不安のない社会を作りたい。自分の才能をいかして喜びを持って生きること、このことは周りの人も喜ぶ。才能を使い切って生き切る。これらの言葉が胸に響きました。
★具体的に竹下先生がお話ししてくださるのでとても共感できるし、わかりやすい。
★竹下先生が奥様のご両親と結婚の話をしに行かれた時に、その場をつくろうことはせず正直に嘘をつかずに話しされこれまでも生きてこられたことに改めて感動した。
★まだ子供を育てたことがないが、竹下先生の話を聞くたびに、自分を大人にしてくれている、成長できていると思えます。
★上映会で竹下先生の話を聞くたびに、自分の中のネガティブに気付けるようになった。自分にネガティブがあったからこそ気付けたのだし、自分に必要だったのだ。気付いていくたびにポジティブになっているのがわかる。
(参加者の皆さんが思わず拍手する場面でした)。
★ベクれたきなこと波動の違うスパゲティをくらべました。大変盛り上がり、正解を読み上げてからも、それぞれ食べ物に対する意識や普段どうしているかなど意見交換できました。今後もこの企画を参考にしてみたいと思います。日輪の写真や千人力ぴよちゃんも皆さん愛用されています。
★この企画から、いろいろ身近な話もできました。放射能の話しは仕事場や身近ではあまりできないようです。
★放射能のことは自分の言葉でできるだけ話をするようにしている。理解されたかどうかはわからないが押し付けたりまではしていない。
★なんでも話せるようになるには信頼関係が大切だと思う。
★自分が体験したことが自分のものになっていると思う。そのことは伝えやすい。
★高齢者、福祉の話しにもなり、「人間力を感じるときやエネルギーのやり取りをしていると感じるときがある。」など仕事から学んだことも話題になった。
» 続きはこちらから