注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

(中略)「(政府予算案には)新型コロナ対策が1円も入っていない。予防的緊急経済対策を講じるべきだ」
(中略)
また、新型コロナウイルスの合同対策本部も開き、クルーズ船から下船した人に対する健康観察の徹底▽PCR検査(遺伝子検査)を受けられる体制の早期構築――などを政府に求める提言案をまとめた。
「(政府予算案には)新型コロナ対策が1円も入っていない。」って驚愕!
— 渡邉麻里子 タルマーリー (@talmary_mari) February 21, 2020
麻生財務相、
「現時点で直ちに不足するとは見込んでいない。修正する必要があるようには思っていない」
ひえ~。
これで野党を批判している人って、どういう論理なの?https://t.co/S4V7rRkPXj
危機管理って、メディア対策だと思ってたんじゃないかな。
— ねずみ王様 (@yeuxqui) February 21, 2020
え、まじで…。さすがにまずくない?
— つしまようへい (@yohei_tsushima) February 19, 2020
〈検査で陰性とされたのは、十日以上前…「私たちも再検査したら陽性になるかもしれない。下船が始まってからでも再検査をして、結果が出るまでは隔離してほしい」と訴え続けたが、認められなかった〉https://t.co/p0hKHf5qn4
» 続きはこちらから


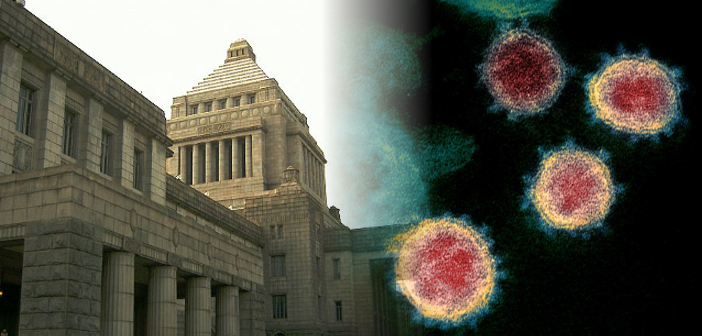


![[Twitter]キッズ目線](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2020/02/u221.jpg)







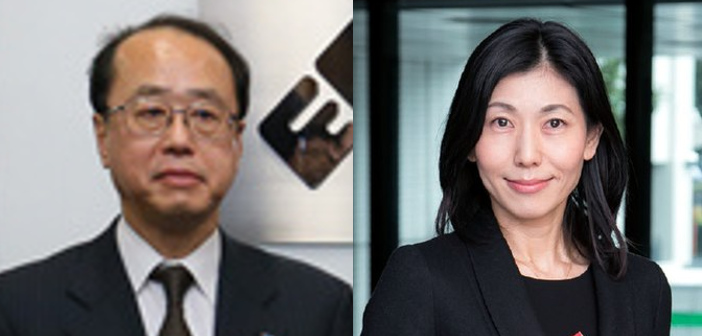

20日の衆院予算委員会で岡本充功議員は、感染研が開発したというPCR検査について、その「偽陰性になる確率」を何度も食い下がるように質問しました。しかし感染研の脇田所長はそれ以上に強情に答弁をはぐらかしていました。本気でコロナウイルスを追い詰める気などないことを露呈しています。1日に検査できる数は3000件程度で、しかも実際にそれほどの検査能力があるのか現場は不安を訴えています。ベッド数は未だに1800床程度が検討され、陰性から陽性に転じた人数も確認できず、何から何まで不明で、しかも感染症対策の予算が組まれていなかったとは、底抜けに驚愕です。諸外国は何千億円レベルの予算を組んでいるのに!
野党は、統一会派で予算の組み替え動議を提出する方針。原口一博議員は、かなり以前から「新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)」を適用すべきと訴えていましたが、安倍政権は無視し続けてきました。無能で後手後手に回っているというよりも、政府が積極的に予防の邪魔ばかりしているようです。水際作戦失敗、クルーズ船対応失敗、国内感染防止失敗、率先して感染を防止するはずの感染研は厚労相の天下り先で、つまりは安倍政権に頭が上がらないのだそうです。