生活の中の木
よく燃えるのは松、クロモジなど油分の多い木です。火を燃やしたいときに、松葉などが着火剤になります。昔から老松の根元や芯部分の油が多い肥松(コエマツ)を細かく切って着火剤として使っています。この肥松は木工材としても珍重され、光沢があり赤みがかった美しい木目の高級銘木です。
ただし、松を燃やすと高温になるので一度にたくさん燃やすと釡やストーブを痛めます。地元の鍛冶屋さんでは松の炭を使って鉄を熱し鍛えておられます。その松の炭も地元の炭窯で作られます。

松
クロモジは燃やすといい香りがします。精油が多く雨で濡れていても燃えます。クロモジはご存知楊枝の高級材ですが、平安時代は生の枝の端を叩いて歯ブラシにしていたとか。精油が虫歯予防、口臭予防になっていたのですね。

クロモジ
どこの家も薪風呂だった一昔前は、落ちた杉枝を拾うのが子供の仕事で、学校から帰って遊びながらも、杉枝を毎日拾ったそうです。
杉枝があるとお風呂を沸かすのにも、薪ストーブで火を焚くにも助かります。

杉
笹や竹なども油分が多くよく燃えますが、節と節の間の空気が膨張して弾けますので、気をつけます。 竹は色々な用途に使いますが、身近なところでは、菜箸を竹で手作りしています。他にも南天の木や桜など剪定ででた木を箸にしています。桜の木の箸置きなどもかわいいですね。色々な木の輪切りは素敵なコースターになります。ちょっと削ればお皿もできそうです。竹のお皿やコップなども夏には合いそうです。
竹を長持ちさせたい時は火であぶって油を滲み出させ、拭きとって使います。この時も弾けると危ないので、ドリルなどで穴を開けて空気抜きを作って火であぶります(穴から出る熱い蒸気にも注意)。

竹林
建材にする時など、竹を伐る時期があるそうで、10月~11月頃が虫が入っていなくていいのだとか。
木は冬場に伐った方が水分が少なく、春は勢い良く水を吸い上げていて、伐るとまるで血を流すようだったと聞いたことがあります。
木も生きていて命があり、「すべてのものに心も知性もある」と竹下先生のお話にもあるのですが・・・・。
5~6年前チェンソーの使い方実習に参加して、間伐用の直径20㎝くらいの杉を伐ったことがあります。教えられた通りに伐ったのですが、木のてっぺん辺りが曲がっていて、自分の方に倒れそうになりました。その時、命のやり取りを感じました。
木を伐ることに一生懸命で、自分が木の命を絶とうとしていることに気が付かなかったのです。杉は一度伐られると広葉樹のように再生できません。自分が危険になってやっと、その木の命を奪おうとしていることに気がつきました。
ロープをかけて反対側に引いてもらい、木は倒れたのですが、その倒れた杉を見た時、杉の木がまだ幼かったのを・・・感じてしまいました。
日本の斧には、木こりが木を切る時にお祈りするための、3本の筋が刻まれているのを、教えていただいたことがあります。お神酒を意味していて、木を伐る前に斧を立てかけて祈るための3本筋なのだとか。
また、インターネットで調べると4本筋もあり、こちらは太陽、土、水、空気を表すそうです。

4本筋をヨキ(木を育てる4つの気)、3本筋をミキ(神酒)と呼び、山の神様へ感謝と木を伐る許可と安全を祈るとか。
以前住んでいたところに砂防ダムが作られる時、突然、木が伐られる日の朝、あたり一面なんとも言えない悲しい空気が漂っていて、私の頭の中では『悲しくて悲しくてとてもやりきれない~』の歌が繰り返し浮かんできて、今日は一体どうしたんだろうと思っていたのです。山の木々の悲しみが辺りに充満していたのでしょうね。



![[第26回] 地球の鼓動・野草便り 生活の中の木](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2017/09/26.jpg)











![[第25回] 地球の鼓動・野草便り 生でいただく食事](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2017/08/a98b1120712ae2558c294773114e59b3-1.jpg)





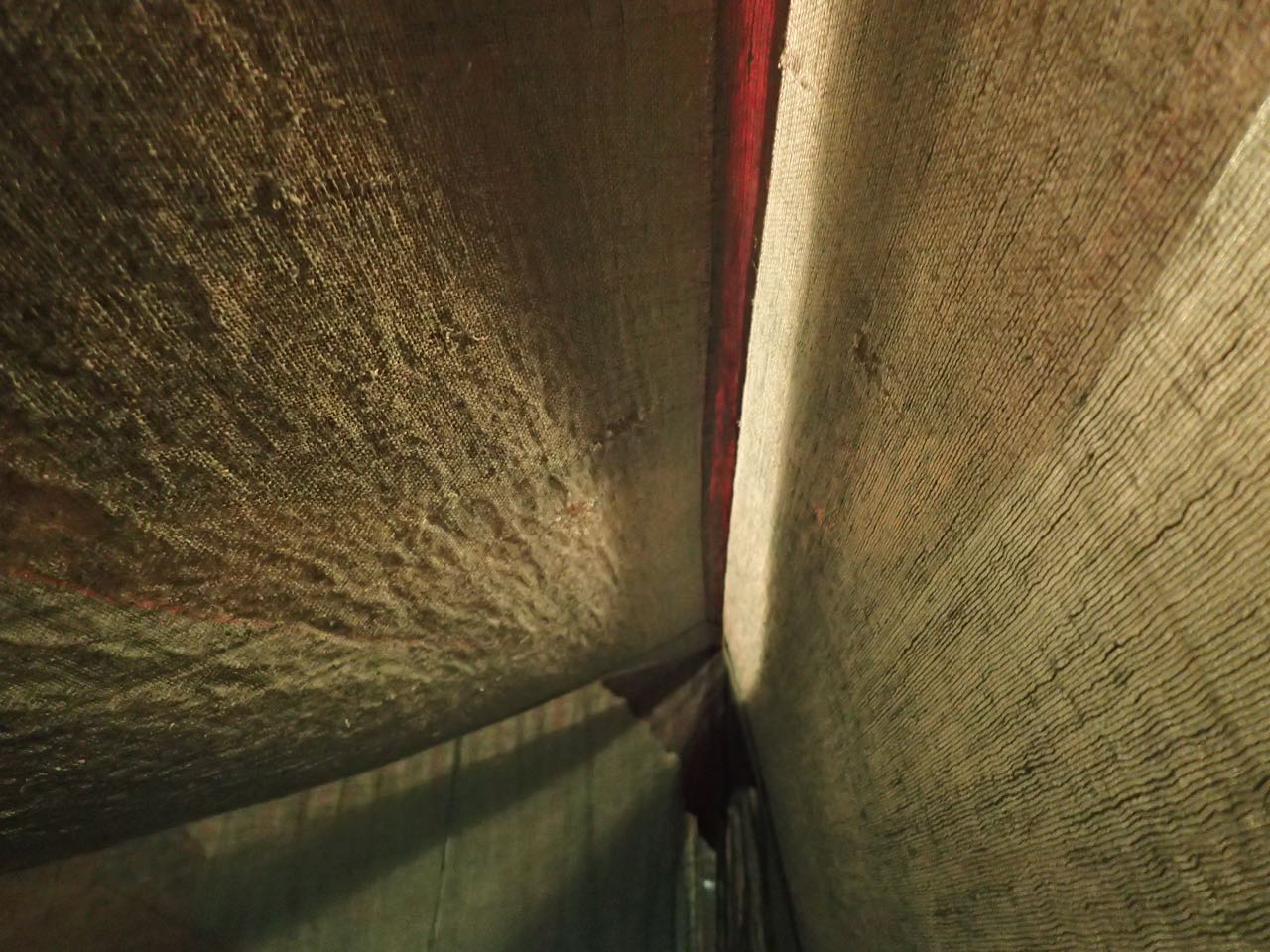











![[第24回] 地球の鼓動・野草便り 秋の七草](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2017/08/24.jpg)


















![[第23回] 地球の鼓動・野草便り 昔からの生活の中の植物と薬効の高い植物](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2017/08/23.jpg)

















![[第22回] 地球の鼓動・野草便り 野生のハーブ](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2017/08/a98b1120712ae2558c294773114e59b3.jpg)















