湯川秀樹も影響を受けた三浦梅園の思想

今日は、
知る人ぞ知る、三浦梅園の話をしよう。

だれそれ?

三浦梅園(1723〜1789)は、江戸中期の思想家で医者、天文学者、自然哲学者、私塾の講師、詩人、画家、書家で、思想家だった。家は庄屋の分家で、士農工商では「農民」だった。彼の代表的な著作は、「梅園三語」と呼ばれる「玄語(げんご)」「贅語(ぜいご)」「敢語(かんご)」で、中でも中心となる「玄語」は存在の研究、宇宙の研究とも言われる。

理科系も文化系もこなせる、マルチな才能の持ち主だね。
 あの湯川秀樹も「玄語」に影響を受けたとか。
あの湯川秀樹も「玄語」に影響を受けたとか。湯川が書に残した「気物相い食(は)み、混成す」は、「玄語」からの引用だそうだ。(
YouTube)

へえ、中間子理論となにか関係があるのかな?

ひええ、どこまで行ったの?

うちから車で30分。

はあ?! そんな近い所にあるの?

ああ。山一つ越えたら、梅園さんちだったのよ。


うわあ、りっぱな茅葺きだあ。

この家に隣接している梅園資料館には、国の重要文化財に指定されている梅園の著書や、直筆の書、愛用品、肖像画などが展示されている。それらの展示やパンフレット、そこでゲットした子ども向けの「三浦梅園伝」「三浦梅園先生の哲学」を参考に、
梅園の生涯を紐解いてみよう。

よろしくで〜す。
天地万物の謎について知りたかった梅園
 子ども時代の梅園は、「なんで、物は下に落ちるのか?」「なんで、目は見えて、耳は聞こえるのか?」「なんでお日さまは上って沈むのか?」などと聞く子
子ども時代の梅園は、「なんで、物は下に落ちるのか?」「なんで、目は見えて、耳は聞こえるのか?」「なんでお日さまは上って沈むのか?」などと聞く子で、大人は「そういうもんじゃ」と答えるしかなかったそうだ。

親は大変だ。

小さい頃は、家にある漢文の書物をかたっぱしから読んだ。
16歳、ようやく二人の師についたと思ったら、1年くらいで止めてしまった。というのは、梅園は天地万物の謎について知りたかったのに、二人の師は教えられなかったからだ。「青年梅園にとっては、今や天地こそがたよるべき師であり、自然こそが交わるべき友であった。」(梅園伝14p)

先生もタジタジだね。
 以来、ずっと独学で、大好きな生まれ故郷から離れなかった。
以来、ずっと独学で、大好きな生まれ故郷から離れなかった。生涯で、長期の旅行をしたのは3回だけ。梅園は言う。「毎朝、両子川(ふたごがわ)の水で顔を洗い、夜は両子山(ふたごやま)に抱かれて眠る。私はこの生活に満足している。」

本当の自分の人生を生きている人のセリフだ〜。

これが、梅園が見ていたであろう眺めだ。


やっぱ、自然がインスピレーションの源だからね。

そう、
梅園は「自分の師は自然だ」と知っていた。梅園「疑いをはさむ余地のない真理は、人間が頭の中で作り上げたものではなく、自然の中にある。だから、人は素直に自然の中にある真理を見て知るべきである。」(哲学9p)そして梅園
23歳の時、当時の新しい学問の中心地、長崎に旅行した。そこで彼は、西洋の天文学に驚かされた。

西洋の天文学って英語、オランダ語だよね。読めたの?

いや、中国語に翻訳された本があった。漢文は読めたからな。
そして、村に帰るや、さっそく自分で「天球儀」を作り始めた。

地球儀じゃなくて天球儀?

「
天球儀というのは、地球を取りまく天空を一つの球に見たて、その表面に多くの星を書き入れたものである。だから実際には、人がその球の中心にいて、表面に書かれた星を裏側から見るはずのものである
(後略)」。(梅園伝23〜24p)毎晩、夜空を観測しながら、完成までに数年かかったと言う。

へえ、どんなのか見てみたい。資料館にあった?

残念ながら、実物は展示されていない。ただ、本の表紙に写真がある。


うわあ、こんなのを自分で作ったの?太い金色の線はなんだろう?

天の川だ。資料館入口のホールには、こいつのでっかいレプリカがある。


ほお!
 だが、梅園は不満だった。
だが、梅園は不満だった。「23歳のとき初めて長崎に旅行して西洋天文学に触れ、地球球体説や緻密な観測結果から大きな影響を受けますが、
『それ切り』の学問であって、天地のしくみを『うら返し』てみせたものではなく、梅園の探求はなお、続きました。」(資料館パンフレット)また、「西洋天文学者の技術は正確だが、
なぜそうなっているかということは研究されていない」とも。(哲学37p)

もっと深い、宇宙のからくりが知りたかったんだ。
突然、真理を悟る

だが、どんなに自然を観察しても、自然の原理までは手が届かない。考えて、悩んで、苦しんで、頭が狂いそうになりながら探求を続ける梅園は、
29〜30歳の時、人生2度めの長期旅行、お伊勢参りに行った。そして、伊勢から帰った梅園は、なんと!突然、真理を悟ってしまった。

えっ?!お伊勢参りのご利益?

因果関係はわからんが、梅園は
その瞬間、「気に観るあり、天地に条理あるを知る」と気づいたそうだ。そしてこれが、梅園の学問の中でもっとも重要な「天地の条理」と呼ばれるものとなった。

なんかよくわかんないけど、必死で求めたから、天が答えてくれたんだね。

そうよ、真理はヒラメキが肝心なのよ。だが、ヒラメいたはいいが、
こっからが大変だった。梅園の中ではクッキリわかっているのに、言葉でするのが難しい。

たしか、言葉は言いたいことの4分の1しか表せないって、
東洋医学セミナーで言ってたよ。

それだよ、
だから梅園は、独自の言語を編み出すしかなかった。

言語まで作ったの?

梅園オリジナル言語、これが後々の研究者を苦しめることになる。しかも、書いてあることはこんな感じ。「すべての物は、一つの気からできており、すべては一気(一:いち)の現象(一一:いちいち)として理解できる」という。

ムリ!

「一一(いちいち)が一(いち)である」つまり「一一即一(いちいちそくいち」。これが「条理」の認識で、「異」が「同」、「同=異」の認識だと。

ムリ!

だな。
こうゆう真理は直感じゃねえとわからんと思う。あえて噛み砕いて説明すると、「二つのものは反対の性質のものが一組になってできているから、一つは昜(よう)、一つは侌(いん)というように順々にどこまでも分けていくことができる。このようにしてすべてのものができている。逆に反対のものを合わせていくと、最後は一つの根本のものになる」。(哲学35p)

「昜(よう)」「侌(いん)」みたいな漢字、初めて見た。

それには、こういう理由がある。「梅園先生の頃は、人びとは普通、性質の反対のものを陰と陽と言っていました。しかし、そう言うと
陽が表で陰が裏ということですから、そこに上下の差別が生まれます。」(哲学38p)

たしかに、山陰山陽と言うだけで、山陰には暗いイメージがついて回る。
 そこで、梅園は「陰陽」を使わず、「一と一」とした。
そこで、梅園は「陰陽」を使わず、「一と一」とした。一と一なら対等だからな。

なるほど! だからわざと、「こざとへん」を取って「侌」「昜」にしたんだね。

そうだ。梅園は、自分の言う「侌」「昜」は、普通に言う「陰」「陽」とは違うと言いたかった。
「男女」「殿さまと人民」は陰陽ではなく「一と一」、つまり対等だと言いたかったんだ。「一と一とは一組の対立するものが陰陽という区別をされる以前の物である。」(哲学39p)

そういうことか。

さらに、「
自然の真理は性質が反対のものが一組になっている。一つのものには二つのものがふくまれ、二つのものは一つのものが分かれたものである。これが条理である。
だから、反対のものをよく見て、合わせて見ることによって、本当のことが分かる。これが反観合一である。」(哲学35p)

「反観合一」? また、わからない言葉が出てきたよ。

相反するように見えるものが、元は一つだと言いたいのよ。「
梅園先生の条理は、このように二つのものは性質は反対であるが、そのために、相手を負かしてしまって、一方が勝ち残るというものではなくて、互いに助け合って共に生きるという考え方です。もし男性だけが残り、女性がいなくなったとしたらどうなるか、殿様だけ残り、人民がいなくなったとしたらどうなるか考えて見ればすぐ分かることです。」(哲学39p)

わかったような気がする。
 文章だけだと難しくなるので、こんな図を使って説明しようと試みたが。
文章だけだと難しくなるので、こんな図を使って説明しようと試みたが。

また、こんなんとか。

一がいっぱいあって、つながり合ってる?

もっと見たけりゃ、
ここにあるから。

すごい! けど、何を描いてるのかさっぱりわかんない。

やっぱ、
「条理」を説明した「玄語」は、あまりにも次元が違いすぎて、どんなに工夫して伝えようとしても、理解できるヤツがおらんかった。
大好きな故郷を離れたくなかっただけ

でも、こんなお利口な人、世間は放っておかなかったじゃない?

ああ、
梅園にはいろんな藩からスカウトが来た。24歳のときは玖珠(くす)藩主、58歳のときは久留米(くるめ)藩、小倉(こくら)藩。全部、断ってるがな。

藩にスカウトされると、どうなるの?

家臣になる、つまり農民の地位から武士になるんだ。それは名誉なことだが、
梅園が断った理由は、「分を知れ。人には分というものがある。分に過ぎたことを望むな」という教えを大事にしたからと言われる。だが、本音は大好きな故郷を離れたくなかっただけ。「私ののぞみは富貴や栄達からのがれ、富永(梅園の住んでいた土地)の山中で読書や、春の野歩きや、魚つりなどをすることで、人に苦労かけて自分が楽をする地位につくことではありません」という内容の詩を送って、断ったと言う。(梅園伝51p)

すんごくわかる。でも、凡人は名誉やお金を選んじゃうよね。

召し抱えられることはなかったが、自分のいた杵築(きつき)藩の相談には乗っていた。
杵築藩の七代目藩主、松平親賢(ちかかた)からの招きで、殿様にいろいろアドバイスしたこともある。「領内を治める道は、親が子を育てる方法と同じであるべきだ。決して、商売人のように、富を民から吸い上げる方法をとってはならない」というように。

梅園のアドバイスに耳を傾ける殿さまもエラい。
「梅園塾」での教え

また、藩の武士から物価問題について質問を受けた梅園は、「条理」に照らして経済の根本を探る、「価原(かげん)」という本を書いている。

経済も「条理」に当てはめたんだ。でも、江戸時代と言えば、日本はまだユダヤ銀行家の手に落ちていないのに、お金の問題なんてあったのかな。

ほれ、時代劇によくあるだろ? 「お主も悪よのお」の越前屋みたいなヤツが、藩を賄賂で腐敗させる話。
商人の奴隷になった社会から脱却する道を、梅園は説いたのよ。「富はお金ではなく、穀物などの財にあり。
民の手元に財があることが、国富であること。国を治める者は、商人の術を用いてはならぬ」。

はあ、商人の術にどっぷりはまっている、今の日本の政治家もそうやって叱って欲しいよ。そう言えば梅園さんは、私塾の先生もしてたよね。

ああ、「梅園塾」だ。が、最初は、教えてくれと頼まれても、人に教える学問をやっていないし、「教授の徳」もないからと断ったそうだ。それでも、「
梅園の学徳を慕うおよそ200人もの生徒たちが、豊後一円はもちろん伊予、阿波など17カ国もの国々から集まり学んでいました」と、パンフに書いてある。

どんな教え方をしたんだろう?
 梅園は学派を否定した。「師は、あくまで天地であって、人ではない」「魚のことを知りたければ、魚の本を読むより魚屋になれ。花のことを知りたければ、花の図鑑を見るより、花畑に走れ。」
梅園は学派を否定した。「師は、あくまで天地であって、人ではない」「魚のことを知りたければ、魚の本を読むより魚屋になれ。花のことを知りたければ、花の図鑑を見るより、花畑に走れ。」

今だったら、「魚の本を読むより水族館に行け」だね。

さらに梅園は、学問の弊害についても述べている。「ふつうの偏見は、学問が正すことができるが、
学問によってできた偏見は直しようがない。医者もさじを投げる」「学問は臭い菜っぱのようなものだ。しっかりと臭みをとらなければ、食べられない。少し書を読めば、少し学者臭い。余計に書を読めば、余計に学者臭くなる。困りもんだ」と。

わかるわあ、知識をひけらかして臭くなっている人、いっぱいいる。
 また、ボヤいてもいる。「浄土宗と日蓮宗のもとで、それぞれ10年勉強してくると、二人の青年は当初の『天然の真』を失って、決して自説を変えようとしない。」
また、ボヤいてもいる。「浄土宗と日蓮宗のもとで、それぞれ10年勉強してくると、二人の青年は当初の『天然の真』を失って、決して自説を変えようとしない。」

わかる。洗脳された人って、頑固になるよね。

こうして梅園は、医者のかたわら、「梅園塾」をやり、村人の相談にのったり、もめ事の仲立ちをしたり、先頭に立って村の事業に取り組んだりして一生を終えた。

「玄語」は完成したの?

彼は
死ぬ間際まで、「玄語」の改訂を続けたが、とうとう完成はしなかった。しかも、「玄語」は難しすぎて、師弟にすら理解してもらえない。そんな梅園は、こう言い遺している。「私ののぞみは、のちの世に賢者が現れて、この本に心を止めてくれることである。そうすれば、私は死んでも永遠に生きることになる。」

人類が「玄語」を理解するのは、いつの日か?
Writer
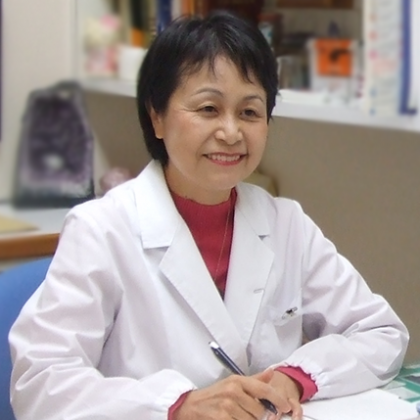
ぴょんぴょん
1955年、大阪生まれ。うお座。
幼少期から学生時代を東京で過ごす。1979年東京女子医大卒業。
1985年、大分県別府市に移住。
1988年、別府市で、はくちょう会クリニックを開業。
以後26年半、主に漢方診療に携わった。
(クリニックは2014年11月末に閉院)
体癖7-3。エニアグラム4番(芸術家)












大分の学校ではきっと、郷土の偉人として教わるのでしょうが、よそ者の私は、いつかドライブ中に目にした「三浦梅園旧宅」という道路標示の記憶しかなく、昔の学者さんかな?くらいの知識しかありませんでした。
ところが、調べるほどにりっぱな人物で、こんな人物が日本に、大分にいたことが誇らしいと思いました。
参考:三浦梅園資料館パンフレット、「少年少女のための三浦梅園伝(文中では『梅園伝』)」「少年少女のための三浦梅園先生の哲学(文中では『哲学』)」