読者の方からの情報です。
渋谷区立美竹公園は、商業化されていない、のどかな普通の公園だそうです。様々な事情から福祉にたどり着けない人々が24時間使える公共の場です。ボランティア組織「のじれん」は、毎週100人以上の野宿者、支援者で共同炊事のボランティアを長年継続されてきました。ところが2021年、東京都と渋谷区が美竹公園一帯を再開発すると発表し、完成予想図では美竹公園は「単なるビル前広場」にすぎない空間にされると判明しました。「公共の土地をみんなのために使うことを考えるのでなく、企業の利益を第一に考えるやり方は、おかしいです。」と「のじれん」は抗議の声を上げていました。10/25、朝早く美竹公園が強制封鎖されたという情報がネットに上がり、渋谷区職員や警備員、警察までが威圧的に公園を取り囲む騒然とした映像が流れました。山本太郎議員が渋谷区に説明を求める強い声も聞こえました。多くの抗議でその時の強制封鎖はなんとか阻止されました。しかし渋谷区はその後も対話を求める野宿者たちを無視して「行政代執行」による追い出しの手続きを進めていました。渋谷区議会は野宿者排除に7893万円もの予算をとりました。そして12/14、美竹公園は再封鎖され、野宿者たちが神宮通公園に避難したところを渋谷区職員・警備員が大挙して訪れ、何の法的手続きもとらずに「今晩の寒さを凌ぐための毛布、それから現金、携帯、仕事に必要なものなど貴重品も根こそぎ奪われました。」美竹公園で遊んでいた子ども達も排除されたそうです。
寒空の下、ギリギリで生きている人々を救おうとせず苦しめる渋谷区は、一体誰のために働いているのでしょうか。
寒空の下、ギリギリで生きている人々を救おうとせず苦しめる渋谷区は、一体誰のために働いているのでしょうか。
注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
————————————————————————

配信元)
#美竹公園再開発 #神宮通公園強制封鎖
— ねる会議 (@nerukaigi) December 14, 2022
渋谷区職員や警備員が人垣を作って私たちをテントから引き離し、その隙に行政代執行の手続きもとらずテントや荷物をトラックで持ち去って行きました。今晩の寒さを凌ぐための毛布、それから現金、携帯、仕事に必要なものなど貴重品も根こそぎ奪われました。 pic.twitter.com/VeOIMQ4wIb
————————————————————————
「ここで生きつないできたのに…」長年炊き出ししてきた渋谷・美竹公園、再開発のため突如封鎖、これからどこで…
引用元)
東京新聞 22/10/31
(前略)
四半世紀にわたり続いていた炊き出しの現場が失われようとしている。東京・渋谷駅近くの美竹公園。再開発を理由に、公園を管理する渋谷区が突然、周囲に囲いを立てて出入りの制限に乗り出した。「ここで生きつないできたのに…」。
(中略)
公園が高層施設の整備予定地に含まれたことで、野宿者らは今春から区に何度も話し合いを求めてきたが囲いは突然、設置された。区側は「工事の着手に先立ち、準備が必要」と説明している。
のじれんによると、コロナ禍で炊き出しの利用者は激増していた。以前は渋谷の路上生活者が多かったが、最近は生活費を抑えるために離れた街から通う人が現れてきた。地方から上京した若者もいる。
(中略)
支援者は「公助で、こぼれた部分を民間の支援や自助努力でかろうじて受け止めているのが現状だ。炊き出しを必要としている人は多い。何とか続けられる方法を模索したい」と話した。
(以下略)
四半世紀にわたり続いていた炊き出しの現場が失われようとしている。東京・渋谷駅近くの美竹公園。再開発を理由に、公園を管理する渋谷区が突然、周囲に囲いを立てて出入りの制限に乗り出した。「ここで生きつないできたのに…」。
(中略)
公園が高層施設の整備予定地に含まれたことで、野宿者らは今春から区に何度も話し合いを求めてきたが囲いは突然、設置された。区側は「工事の着手に先立ち、準備が必要」と説明している。
のじれんによると、コロナ禍で炊き出しの利用者は激増していた。以前は渋谷の路上生活者が多かったが、最近は生活費を抑えるために離れた街から通う人が現れてきた。地方から上京した若者もいる。
(中略)
支援者は「公助で、こぼれた部分を民間の支援や自助努力でかろうじて受け止めているのが現状だ。炊き出しを必要としている人は多い。何とか続けられる方法を模索したい」と話した。
(以下略)
» 続きはこちらから







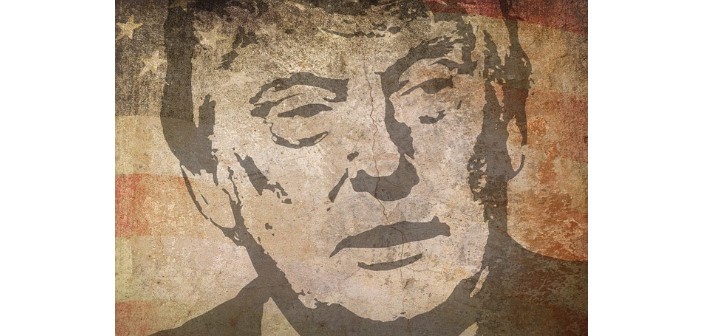

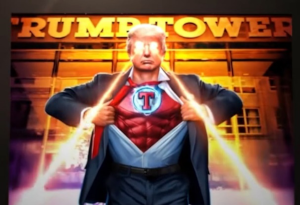









12/15の夕方にようやく取り戻せたのですが、まだ大事な荷物の一部しか取り戻せていないとのこと。
渋谷区の無慈悲な暴挙を許してはなりませんね。他人事ではありません。
この数年、年末の美竹公園気付で友人たちにも協力してもらい、寝袋や毛布を送っていたのですが、少し前に美竹公園から追い出されたということでしたので、今年はどこへ?と「のじれん」さんのツィートを開くと、「ねる会議」さんのツィートをUPされてました。
「このような暴挙は許さない!」という想いを天高く持ち上げました。
誰もが屋根の下で暮らせる日が、1日も早く訪れることを祈ります。
私も今から抗議の電話を。