竹下雅敏氏からの情報です。
————————————————————————
【現代の悟り修行】〝第六感、第七感〟を開いて魂と繋がる方法
配信元)
YouTube 25/7/2
————————————————————————
配信元)
X(旧Twitter) 25/6/25
僕が体感した、“悟り”というやさしさの話。|こぉちゃん-love trigger コーチ- https://t.co/xYDfW4mNuy
— こーちゃん@未来創造コーチ❤️🔥 (@LGBT8787) June 25, 2025





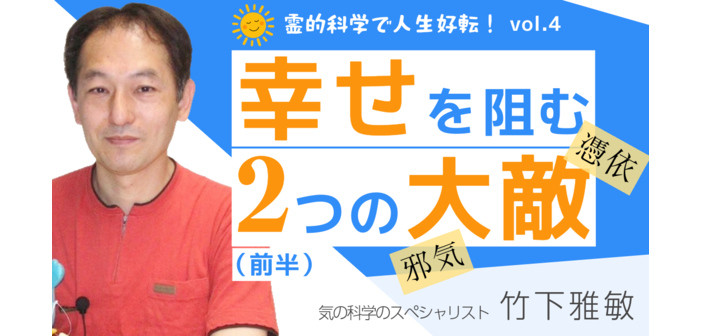










“これは私の発信している全ての情報に言えますが、迷ったら信頼すべきは私の情報より皆さんの「感覚」です。それが「真実」なのです。私たちはどうしても何が「真実」なのか、本当のことを知りたいと思うじゃないですか。でも、それは次元によっても違いますし、魂というのは「真実」を探したいのではなくて、「自分を思い出したい」だけなんですね。中心にあるのは常に「自分を知ること」です。(8分4秒)”と言っています。
これは全くこの通りです。「自分を知ること」については「内面の浄化」が不可欠なのですが、動画の21分45秒以降でその方法が語られています。“この『ありがとう』という言霊を、何度も何度も言うことでエネルギーに「感謝の癖をつける」ということと、『ありがとう』という言霊自体が「調和」とか「統合する」ための言葉ですので、そういう方向に導いてくれます。”と言っています。
2022年3月14日の『中西征子さんの天界通信76』で、スベテヲスベルヒメミコ(色上姫浅子)から「感謝のマントラ」が伝えられました。
「ありがとう! ありがとう! ありがとう!…」というように、「ありがとう!」という言葉を17×17=289回唱えます。
また、「悟り」というのは、簡単に誰でも得られるものだということは、「“悟り”って、特別じゃなかったんや。」という記事をご覧になるとよく分かります。
『悟りについて(’19/5〜)』の一連の記事も参考にしてください。