竹下雅敏氏からの情報です。
注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
――――――――――――――――――――――――

「托卵女子」という恐怖の悪女〜DNA鑑定で暴かれる「ホトトギスの罪」
引用元)
biglobe 16/7/13
DNA鑑定の結果、2割が夫の子どもじゃない?
(中略)
昔はいくら父子関係に疑念を抱いても、正確に調べる術がなかった。しかし、科学の進歩により、パンドラの箱を開けられるようになってしまった現在。「知らぬが仏」で済んだ時代は終わり、現代的な「悪女」として、「托卵女子」が男を悩ます種となってきている。
(中略)
いったい、「托卵女子」とは、どのような女たちなのだろうか。
(中略)
「ロケットニュース」の記事「【男子は注意】別の男の子供を夫に育てさせる『托卵女子』が急増か」(2014年2月6日)では、婚活中だという30代女性の「結婚するなら金持ちのキモメンで、産むならイケメンの子がいい」という衝撃的な声が掲載されている。
ようは、「金持ちのキモメン」なら浮気の心配がなく、経済的にも不自由ない結婚生活が送れる。しかし、子どもが不細工だったら苦労するため、托卵でイケメンの子どもを産むことは、自分にも、子どもにも、ひいては夫にもメリットがあるはずだ、ということらしい。
(中略)
つまり、彼女たちは「婚姻関係の選択」とは別に、「精子の選択」を行っているということになる。「DNAの選択」とも言い換えることができるだろう。
(中略)
地位や階級の問題が絡んでくれば、より深刻なものになる。血縁によって相続されるはずだったものが、他人の子に渡ってしまうからだ。(中略)男にとっては血縁に対するテロリズムにほかならないが、女にとっては、愛する男のDNAを階級上昇させるレジスタンスとして托卵が機能していたのではないか。
(中略)
さらに、「DNAのつながりだけが父子関係なのか」という意見もある。血縁も大事だが、子どもを育てた精神的なつながりも重視されるべきだ、と。托卵が判明した後でも、自分の子どもとして育てることを望む夫もおり、父子関係は理屈で割り切るほど単純ではない。
(中略)
しかし、忘れてはならないのが、傷つくのは夫だけではなくて、子ども同じだということ。そういう意味では、DNAのつながりだけが父子関係ではなく、また、どういった経緯にしろ我が子を産みたいと思う女性の気持ちは尊重されるべきだとしても、やはり周囲を欺いて托卵することは、罪深い行為だと言えそうだ。
(以下略)
(中略)
昔はいくら父子関係に疑念を抱いても、正確に調べる術がなかった。しかし、科学の進歩により、パンドラの箱を開けられるようになってしまった現在。「知らぬが仏」で済んだ時代は終わり、現代的な「悪女」として、「托卵女子」が男を悩ます種となってきている。
(中略)
いったい、「托卵女子」とは、どのような女たちなのだろうか。
(中略)
「ロケットニュース」の記事「【男子は注意】別の男の子供を夫に育てさせる『托卵女子』が急増か」(2014年2月6日)では、婚活中だという30代女性の「結婚するなら金持ちのキモメンで、産むならイケメンの子がいい」という衝撃的な声が掲載されている。
ようは、「金持ちのキモメン」なら浮気の心配がなく、経済的にも不自由ない結婚生活が送れる。しかし、子どもが不細工だったら苦労するため、托卵でイケメンの子どもを産むことは、自分にも、子どもにも、ひいては夫にもメリットがあるはずだ、ということらしい。
(中略)
つまり、彼女たちは「婚姻関係の選択」とは別に、「精子の選択」を行っているということになる。「DNAの選択」とも言い換えることができるだろう。
(中略)
地位や階級の問題が絡んでくれば、より深刻なものになる。血縁によって相続されるはずだったものが、他人の子に渡ってしまうからだ。(中略)男にとっては血縁に対するテロリズムにほかならないが、女にとっては、愛する男のDNAを階級上昇させるレジスタンスとして托卵が機能していたのではないか。
(中略)
さらに、「DNAのつながりだけが父子関係なのか」という意見もある。血縁も大事だが、子どもを育てた精神的なつながりも重視されるべきだ、と。托卵が判明した後でも、自分の子どもとして育てることを望む夫もおり、父子関係は理屈で割り切るほど単純ではない。
(中略)
しかし、忘れてはならないのが、傷つくのは夫だけではなくて、子ども同じだということ。そういう意味では、DNAのつながりだけが父子関係ではなく、また、どういった経緯にしろ我が子を産みたいと思う女性の気持ちは尊重されるべきだとしても、やはり周囲を欺いて托卵することは、罪深い行為だと言えそうだ。
(以下略)




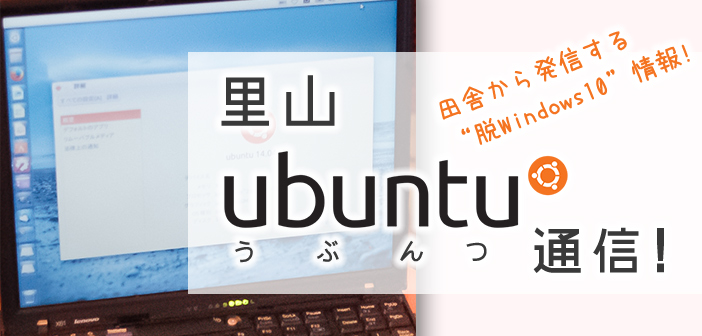


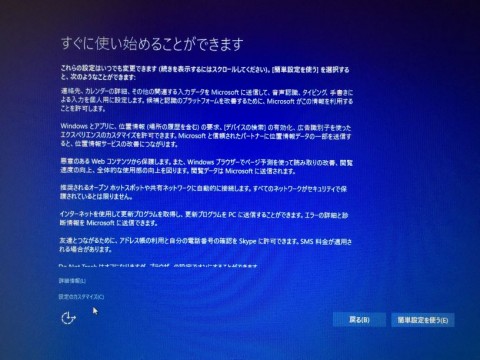
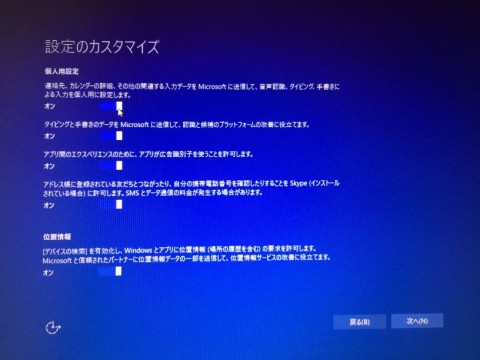
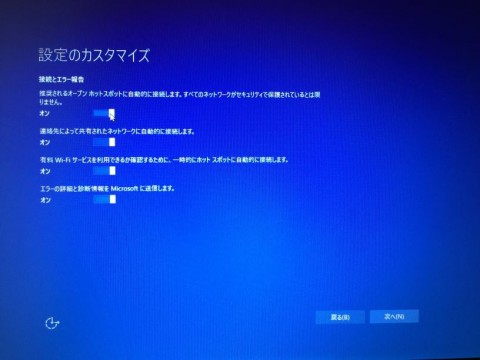
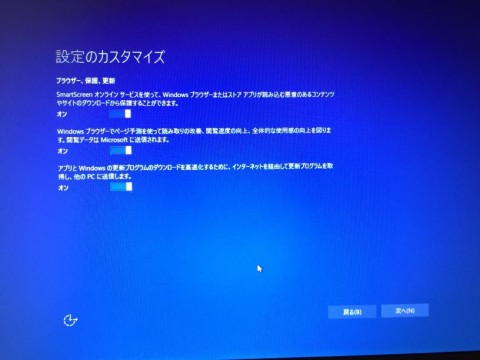
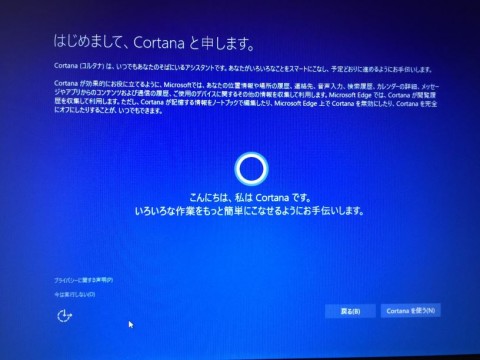



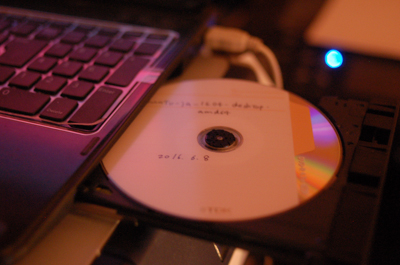
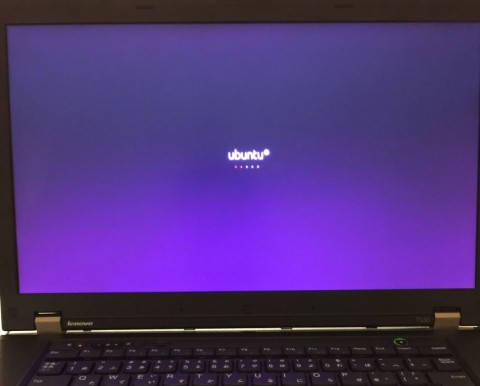


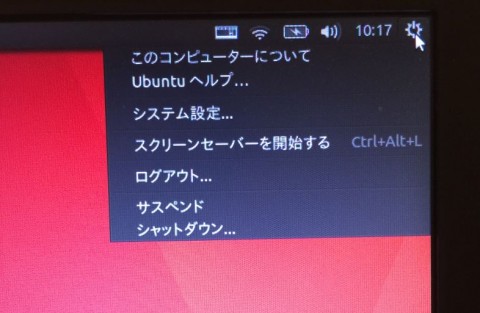
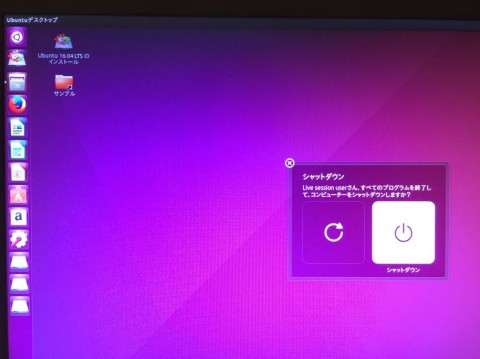
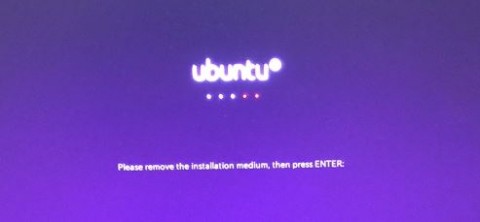








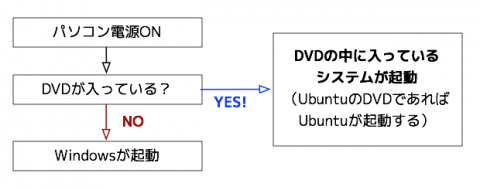
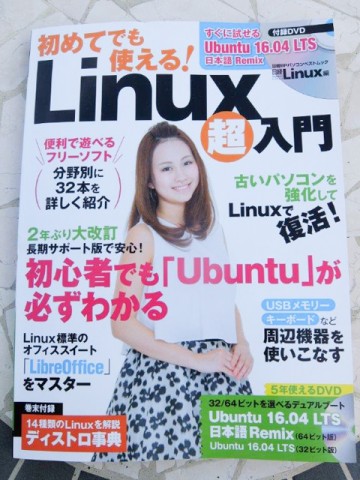
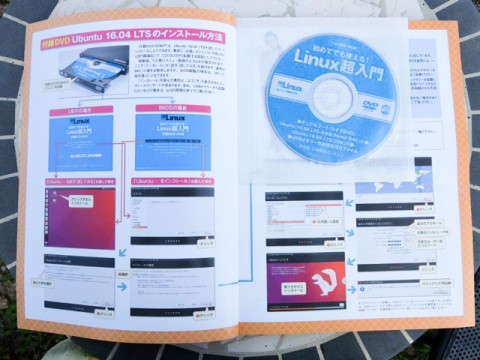

記事を読んで、そう思うしかないものです。科学技術の発展で“パンドラの箱”が開けられるようになって、誰の子かはっきりとわかるようになった今、“托卵女子”が少なくとも2割居るのではないかという衝撃的な記事です。彼女たちを一言で言うと、“結婚するなら金持ちのキモメン、産むならイケメン”ということで、経済的に不自由の無い、もっと言うと、セレブならキモメンで十分、ただし、イケメンの子供を産んで、夫と我が子を騙し続ける選択をするということのようです。
この記事で衝撃的だったのは、このような托卵女子の行動は、“男にとっては血縁に対するテロリズム”でしかないが、“女にとっては、愛する男のDNAを階級上昇させるレジスタンス”との一文。あまりにも見事な表現だけに、この記事は紹介せねばなるまいという気になりました。
記事では、DNA鑑定で父子関係が調べやすくなった現在、彼女たちのような悪女をどうすれば良いのかと語られています。しかし、よく考えてください。代々続く名家と言われる血筋の家長は、地位や階級の安定のために愛情を伴わない政略結婚をし、公然と何人もの女性を妾にして子供をたくさん儲けています。残念ながら現代の社会は、地位と名声、そして財産を獲得した男性が何人もの女を囲うのは半ば当然であり、男の甲斐性ぐらいにしかこのような問題を捉えていません。
ところが、容姿で評価される女子が同様のことをすると、悪女と非難されるのです。違いは、一方は公然と行っているのに対し、一方は隠し続けるということでしょうか。
彼女たちを“悪女”と言うなら、何人もの女性を囲う男性は、“悪”ですよね。そういう観点で世の中の王族・貴族を眺めて見ると、確かに悪そのものです。ということは、やっぱり彼女たちは、悪女ですね。
男性にせよ、女性にせよ、こうした問題の根底にあるのは、男女の結びつきが愛情ではなく、お金だということです。何人も女性を囲っている男性が居たとして、その男性が破産した時に何人の妾が残っているでしょう。おそらく金の切れ目が縁の切れ目で、全ての女性が破産した男性から去って行くのではないでしょうか。要するに、問題の要点は、婚姻関係がお金で結びついていることだと思います。
記事の中で、托卵女子の言い訳は、“子供が不細工だったら苦労するため、托卵でイケメンの子供を産むことは、自分にも子供にも、ひいては夫にもメリットがある”というものです。よくまあ、こんな欺瞞に満ちた言葉を吐けるものだと思いますが、要はそれでなくても嫌いな夫の不細工な子供は、とても愛せないということではないかと思います。
そもそもこういう間違った倫理観に基づいた結婚をしないことが大切です。人間が地上に転生する目的は、愛を育むことであって、安楽な生活をするためではありません。ここを勘違いすると、自分だけではなく、自分に関わる周りの人たち全てを不幸にしてしまいます。