注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

 ネット上でも「まるで絵画のようだ」などと形容された、なんとも不思議で”秀逸すぎる”構図の「例の写真」についても興味が及んでしまうんだけど、↓こちらはどうなのだろう?
ネット上でも「まるで絵画のようだ」などと形容された、なんとも不思議で”秀逸すぎる”構図の「例の写真」についても興味が及んでしまうんだけど、↓こちらはどうなのだろう? 
出典:産経新聞
 やはり、こちらも当初から、(構図が絵画のようにあまりに出来過ぎている、安倍総理の目線などが不自然などの点から)「合成ではないか?」との疑惑が上がっている状況なのですが、こちらの写真はドイツ政府が公開したという情報が出ており、この写真の真偽は現時点では分からない状況です。
やはり、こちらも当初から、(構図が絵画のようにあまりに出来過ぎている、安倍総理の目線などが不自然などの点から)「合成ではないか?」との疑惑が上がっている状況なのですが、こちらの写真はドイツ政府が公開したという情報が出ており、この写真の真偽は現時点では分からない状況です。(以下略)
今日の写真:G7の立ち位置。詰め寄るメルケル。横にマクロン。応じるトランプ。で。わが首相は。どこかの新聞橋渡しに苦心と書いていた。 https://t.co/77XwlMFyLT
— 孫崎 享 (@magosaki_ukeru) June 10, 2018
G7で対峙するメルケルとトランプ。? 何かが違う!https://t.co/kQ0G6kgZY4
— mko (@trappedsoldier) June 19, 2018
I have a great relationship with Angela Merkel of Germany, but the Fake News Media only shows the bad photos (implying anger) of negotiating an agreement - where I am asking for things that no other American President would ask for! pic.twitter.com/Ib97nN5HZt
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2018
トランプ、アベの動きを明かす:
— 宋 文洲 (@sohbunshu) June 18, 2018
アベ、ずっとその場に居なかった
最後に写真を撮りに来た
だからアベはこの時の動画を出さない
静止写真をアップして動画を作った pic.twitter.com/5hUjNJrnG3
そうか。写真だけ撮りに来たから、こんな議論が白熱しているような場面でも通訳が脇にいないわけか、、
— ライナ (@mneaiortioot) June 18, 2018
後ろに居たみたいですよトルドーさんの写真に 頭だけ写ってました 各国の首脳の方々はG7の時の写真を出してます 合成すると世界の笑い者に なりますよ 何故 後ろに居たのか 何を話してるのか 分からないからだそうです
— ニンニン君 (@hantahanta) June 18, 2018










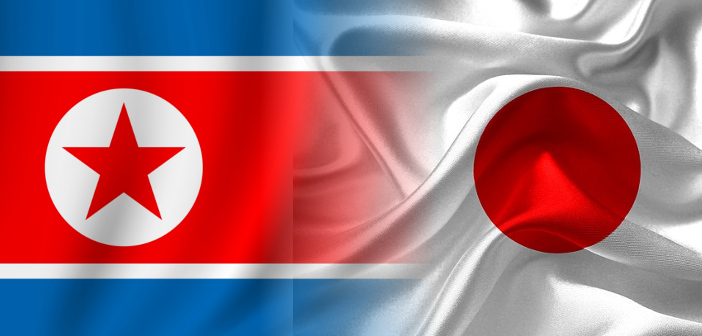





孫崎享氏のツイートには、どこかの新聞が、G7であべぴょんが“橋渡しに苦心”と書いたとのこと。まさに、これがあべぴょんの目的です。
あたかも自分が会議の中心にいて、トランプ大統領と他の国の代表との橋渡しに苦心しているかに見せかける印象操作です。あべぴょんお得意の、カメラ目線を意識したポーズに過ぎません。
私がそう考えていたのは、トランプ大統領や他の首脳が掲載していた写真の中には、あべぴょんがほとんど写っていないからです。だいたい英語がわからないあべぴょんが、こうした場面で仲裁役を買って出れるはずがありません。
このように考えていたのですが、宋文洲氏のツイートによれば、なんと、トランプ大統領が真相を明らかにしたらしい。あべぴょんはその場にいなかったのに、“最後に写真を撮りに来た”とのこと。
やっぱり!
この恥ずかしい奴はなんとかなりませんか…。日本人は騙せても、世界の笑い者です。