————————————————————————
まみむのメモ(62)〈食べられる野草図鑑・春(6)〉
セリ(芹)

| 時期 | 春の七草の一つ。常緑で秋に節から新芽をだしてふえる。 |
| 場所・環境 | 日本全土の水田や溝、小川、湿地などに生える。およびサハリン,中国,朝鮮,台湾,ウスリー,マレーシア,インド,オーストラリアに分布し,低湿地,水田などに普通に見られる。 |
| 花 | 花期は8月ごろ。越冬株から直立した高さ10〜30cmの花茎を伸ばし、その先が枝分かれして直径5cmほどの傘状花序を複数つけて、白い花を咲かせる。花柄の長さは揃っているので、花序はまとまっている。個々の花は小さく、花弁は5個で、たくさんつく。
|
| 葉 | 葉は根際に集まってつく根生葉と、茎に互生してつく葉に分けられ、ともに1〜2回3出羽状複葉で、全長は30cm以上になる。小葉(裂片)は長さ1〜3cmの菱状卵形を基本に、丸みを帯びた心臓形から長卵形まで変化に富み、葉縁に明確な鋸歯がある。根生葉は、葉身に長い葉柄がつき、茎につく互生葉の柄は上部になるほど短い。葉柄はいずれもさや状になる。全体的に柔らかく緑色であるが、寒くなる冬にはアントシアニンを帯びて、赤っぽく色づくこともある。
|
| 実 | 種子は秋に熟し、果実が2つに分かれて落下する。種子の発芽期は晩秋(10〜11月)または春(4〜5月上旬)で、夏場に芽が生長する。
|
| 根 | 春から夏場までの日が長い時期(3〜9月)は、泥の中や表面を横に這うように根元から白く長い匍匐枝(ほふくし)を多数伸ばして、秋から冬にかけて日が短い低温期は、多数の根生葉を叢生する。秋(9〜10月)にその匍匐枝の節から盛んに白いひげ根を出して、新しい苗ができて盛んに成長する。晩秋(10〜11月)に長い柄のある根出葉を盛んに出して、冬場(12〜3月)は根出葉の伸長は停止して、枯れることなく冬を越す。
|
| 見分けるポイント | セリと似た環境で育ち、見た目も似ている草にクレソンやタネツケバナがあるがこちらはアブラナ科で、葉先が丸く香りもやや違い、辛味がある。またシャクは葉先が尖り、香りも似ているが、生え方が根生で茂り、草丈も50cm〜1m前後と大きくなる。 |
| 間違えやすい毒草 |
ドクゼリはセリと同じような場所に生えるため、特に春先の若芽はセリと間違いやすい。 5月のセリは、食べるなという言葉があるのは、猛毒のドクゼリがこの時期に伸び始めるから。 ドクゼリの特徴として、(1)地下茎が緑色で太いタケノコ状の節があり、横に這わず「これが最大の特徴」、セリは白いひげ根があるで区別できる。(2)セリ独特の芳香がない。(3)大型で、草丈が60~100センチになる(ただしセリも葦が茂るなどの環境によっては2mくらいになることもある)。(4)茎が丸く、中が空いている。(5)ドクゼリはセリより鮮やかな緑色で、葉が全体的に大きい。 キツネノボタンもセリと同じような場所に生育する毒草である。根生葉のときにセリと間違いやすい。 ドクニンジンは、ニンジンにも似たヨーロッパ原産のセリ科有毒植物で、日本には関東地方から中国地方の範囲に帰化しており、草原に生えている。個々の小葉だけを取ると似ているので間違えるおそれがある。 |
| 生え方 | 多年草 |
| 学名 | javanica(ジャヴァニカ) |
| 科名・属名 | セリ科セリ属 |
| 採取方法 | 花が咲き十分生育しているセリの地上部を、茎の柔らかいうちに採集して乾燥させる。 はじめ日干しにして、少し乾燥してから日陰で風通しのよい所につるして、十分乾燥させる。 水分を多く含んでいるので、速やかに乾燥させ、カビを生じないようにする。 食用には一年中、全草いただける。 |
| あく抜き | 一般に流通している栽培品は灰汁(アク)が少ないが、野生のセリ(山ぜり)は風味が強く、アクも強いので塩を入れてさっとゆでて水にさらす。(鍋物にはあく抜きせずにそのままで、鍋物の主役はセリにかなうものなしといわれる。) |
| 調理法 | 春の七草の一つとして七草粥、巻き寿司やちらし寿司、吸い物、鍋物などによく食される。セリが持つ香りや、ビタミンCやカリウムなどの水溶性栄養成分の損失を防ぐため、加熱しすぎないようにする。香り成分は肉類の臭みを消す効果があり、肉を使った鍋物や炒め物に適している。 春先の若い茎や根をさっと茹でて水にさらし、おひたしや酢味噌和え、酢の物、卵とじ、煮びたし、油炒めにする。天ぷら、すき焼き、即席漬けにも。また、刻んで塩味をつけて、炊き上がったご飯に混ぜたせり飯にしたりもする。根はきんぴらに、花は天ぷらにできる。宮城県仙台市周辺では、セリを主役とした鍋料理「せり鍋」があり、葉から根まで使われる。また、秋田県では根をきりたんぽ鍋の材料として好まれる。 江戸川柳に「なべ焼きの鴨(かも)と芹(せり)とは二世の縁」というのがあり、このことからも、カモとセリの鍋物が古くから親しまれていたことがわかる。 クレソンと同じように生で食することもできるが、その場合は肝蛭(かんてつ)の感染に注意が必要で、良く洗う。 |
| 他の利用方法 | 薬用、浴湯料 |
| 効能 | ビタミンB1、B2、CやビタミンK、βカロテンなどのビタミン類。カリウム、カルシウム、マグネシウム、リン、鉄、銅などのミネラル類や食物繊維が豊富でバランス良く含まれている。 ビタミンCは免疫力を高めるとともに、活性酸素の働きを抑え老化防止や肌にうるおいを保つ効果がある。 ビタミンKは血液中の老廃物やコレステロールを排出する効果が高く、生活習慣病の予防効果に役立つ食材だといわれている。 βカロテンは体内でビタミンAに変換され、活性酸素を抑え動脈硬化や心筋梗塞などの生活習慣病から守るとともに、皮膚や粘膜の細胞を正常に保つ働きや免疫力を高める働きもある。 ミネラルは血液や骨の生成に欠かせない成分。 食物繊維には腸の働きを整え、便通を良くする働きや、コレステロールの排出や急激な血糖値の上昇を防ぐ働きもある。 セリの茎や葉を乾燥させたものを、生薬で水芹(すいきん)という。水芹を煎じて服用する事で、食欲増進の他、解熱や神経痛、リューマチ、黄疸(おうだん)去痰、緩下,利尿作用などに効果があるとされている。,鎮痛作用もあり,神経痛,リウマチには陰干しした茎葉を布袋に入れ浴湯料とする。小児の解熱には生のしぼり汁を1回2~4 ml飲ませる.肝硬変には青汁を飲む。 セリ特有の芳香にはオイゲノ―ルなどの精油成分が含まれ、鎮静効果があるとされている。また、ピラジンと呼ばれる成分が血液凝固を防ぎ血栓を予防したり、肝機能を強化するのに役立つとされている。 |
| その他 | セリの種子は好光性で、発芽率は40 - 50%との調査例があり、25度前後でよく発芽するが、変温を与えた方が発芽率が高まる傾向にあるといわれる。 野生種から選抜したものが栽培されていて、栽培時期は春に苗の植え付けを行って秋に収穫し、栽培適温は10〜25度とされている。水田栽培の「田ぜり」と畑栽培の「畑ぜり」の二つの栽培方法で行われていて、水田栽培は清水があるところに早春に親株の植え付けが行われ、畑栽培では秋に匍匐枝(ランナー)を取って植え付け、たびたび灌水して育成する。一般には秋早くに種田から親株(種ゼリ)を採取して水田(本田)に植え付けられて、冬の収穫期に緑の若葉が茂る。田ぜり栽培では、秋どり栽培の早生系(10〜11月収穫)、冬どり栽培の中生種(12〜2月収穫)、早どり栽培の晩生系(2〜4月上旬収穫)があり、収穫期間の異なる3つの作型がある。 |
| 参照サイト・文献 |
松江の花図鑑 熊本大学薬草園 薬草データベース 旬の食材百科 ウィキペディア イー薬草・ドット・コム |
| 関連記事 | なし |
ノビル(野蒜)

| 時期 | 春から初夏にかけて、地中の鱗茎(りんけい)につく小鱗茎と花後や花の代わりにつく球芽(むかご)が地面に散って秋に発芽する。
|
| 場所・環境 | 東アジアに広く分布する。日本では北海道から沖縄までの山野、土手、道端、畦道や堤防上など、丈の低い草が生えているところによく自生する。日当たりの良い草地や、道ばたなど、人間の生活圏に群生していることが多い。人間の手の加わっている場所に繁殖する傾向にあり、その土地に人間の手が加わらなくなると自然に消滅してしまう。 |
| 花 | 花期は初夏から夏(5〜6月)ころで、まっすぐ立ち上がって40〜60 cmに達する花茎を1本だけ伸ばし、先端に花序(散形花序)をつけ、白色または淡紅紫色を帯びる。ネギ坊主を小さくしたような小花が多数球状に集まった花で、花径は4〜5 ミリメートル(mm)、長さ数ミリメートルの楕円形の花被片が6枚、実際にはユリと同様に花弁は3枚、残り3枚は額が変化したものである。花被片の中央には、濃紫色の筋が1本ある。花柄はやや長く、ニラやラッキョウとよく似た花形をしている。花が咲かずムカゴになることもある。 |
| 葉 | 葉は、数枚が下方にあって、互生(ごせい)して、狭線形で先は尖り中空で、下部で茎を包む。ネギを小さくしたような形で、晩秋から伸びだし、生長すると20〜30cmのものを数本出す。葉は柔らかく、表面に白い粉をふいているような白みを帯び、中部以上は内側が凹んだ浅い溝状となって、中空で断面が三日月形をしている。ネギやワケギよりも細く、ラッキョウと似ている。成熟すると1本の花茎になり、途中から数本の葉をつける。 |
| 実 | 6月ころになると花茎頂に、花になるはずの細胞が変化して、小さな球根のような珠芽(むかご)ができ、散布体としてポロポロ落ちて新しい個体になって繁殖する。しばしば、開花前から花を咲かせずにむかごだけが着生するものや、花を咲かせている個体でも、一部がむかごに変化して、むかごと花が混じったりするものがある。むかごは白色から紫褐色になり、固く密生し、たくさん集まると表面に突起の出たボールのようになる。田んぼや畑の周囲に、花を咲かせずむかごだけの個体が多く見られる理由は、人の手によって頻繁に雑草の草刈りが行われるために、花を咲かせて種子をつけるよりも、効率良く子孫を残すことができるためだと考えられている。 むかごの散布以外にも、球根が盛んに分球して繁殖する。 
|
| 根 | ラッキョウに似た白くて小さな球根(鱗茎)があり、直径1〜2cmの球形で、白い膜質の外皮に包まれている。下部にひげ根がついている。
|
| 見分けるポイント | 近縁種 Allium vineale(英名: Wild Garlic(野生のニンニク)または Field Garlic(野原のニンニク))がヨーロッパ、北アフリカ、中近東に分布するが、ノビルにはニンニク臭はない。ラッキョウよりも球形で球根は一つで小さな種になる球根が付く。ラッキョウの花は秋に咲き、紫色。 |
| 間違えやすい毒草 | 有毒植物のタマスダレ、ヒガンバナ、スイセン(すべてヒガンバナ科)の葉に似ており、葉が茂っているときに花がないため、ノビルと間違えないように注意を要する。ノビルの鱗茎は白い色をしているが、タマスダレの鱗茎は茶褐色をしているので見分けることができる。また、タマスダレやヒガンバナ、スイセンにはネギ臭がないことでも見分けられる。 |
| 生え方 | 多年草 |
| 学名 | Allium macrostemon |
| 科名・属名 | ユリ科(APG分類・・・DNA解析による分類:ヒガンバナ科)・ネギ属 |
| 採取方法 | 3月〜6月にかけて、葉やむかご、地中の鱗茎(りんけい)を採取する。 10月〜12月に若葉を摘む。簡単に抜き取れることもあるが、鱗茎が地中5〜10cmに残る場合があるので、軽くスコップを差し込んでおいて(掘り起こさないで)、抜き取る。大きい鱗茎だけ収穫して小鱗茎は埋め戻し、地面をもとどおりに押さえておく。)鱗茎は年中採取できるが、春が大きい。 |
| あく抜き | なし |
| 調理法 | 柔らかい葉や鱗茎を細かく刻み、味噌汁、納豆に混ぜる。さっと茹でて水に取り、酢味噌、芥子酢味噌、味噌マヨネーズ和えに。鱗茎を生で生味噌をつけて。天ぷら、炒め物に。約5cmに切り、人参、塩昆布と混ぜて重石をして(約1週間)漬物に。 一文字(ノビル)のぐるぐる巻き(茹でたノビル1本そのままぐるぐる巻きにして酢味噌でヌタに) |
| 他の利用方法 | ノビル栽培・・・野菜としてブランド化(佐賀大学研究)料 |
| 効能 | アリシン・・・ニンニク、ネギなど強いにおい成分のイオウ化合物の1種で、生の状態ではアリインという物質が、切る、潰す、加熱によってアリシンに変化する。 βカロテン、ビタミンK、C、B2などのビタミン類が豊富。 カリウム、カルシウム、マグネシウム、リン、鉄分などのミネラル分が豊富。 ・アリシンは疲労回復効果があるビタミンB1と結合して体内に長く止まらせ持続させる。またコレステロール値上昇を押さえ、活性酸素を抑えるなどの抗酸化作用により、生活習慣病予防に役立つ。 またアリシンを含むイオウ化合物には、血液が固まりやすくなるのを防ぎ、心筋梗塞や脳梗塞などの血栓予防と血流促進効果がある。 アリシンには強い殺菌力があり、サルモネラ菌、チフス菌、コレラ菌などの病原菌から体を守り、風邪予防にも効果がある。 また、独特の香りが唾液や胃液といった消化液の分泌を促し、食欲増進、消化吸収を高める効果がある。 ・ビタミンB2は過酸化脂質の分解を促し、動脈硬化、心筋梗塞の予防に効果的。 ・鉄分は貧血予防に。 ・ビタミンKはたんぱく質の働きを活発にして丈夫な骨作りに効果があり、骨粗鬆予防になる。 ・ビタミンCは、コラーゲンの生成やメラニンの抑制による美肌効果や抗酸化作用による老化防止作用が期待できる。 また、副腎皮質ホルモンの分泌を促し、ストレス解消に役立つ。 ・カリウムがナトリウム(塩分)排泄をして高血圧予防、筋肉痙攣防止などに効果がある。 ・カルシウム、マグネシウム、リン、鉄分などのミネラルは、骨の生成に欠かせない成分。 全草を生で、または金網の上で黒く焼いて粉末にして、そのままあるいは砂糖湯で服用すれば健胃、整腸、鎮咳、去痰剤、食欲不振、胃がん、百日咳、気管支炎、肺壊疽(えそ)、肺膿瘍、子宮出血、月経不順、血栓予防に効果がある。 また、ごま油やひまし油で練りあわせて貼れば、腫物、毒虫刺され、切り傷、火傷。癰疔(ようちょう)、肩こり、五十肩、扁桃腺炎に効果がある。 生の鱗茎をつぶすかすりおろして小麦粉で練って貼れば、打ち身、毒虫の刺し傷に効果がある。 生の汁を塗れば、毒虫刺されのかゆみ、ぜにたむし、はたけなどに効果がある。 民間薬として、全草を天日干し、または陰干ししてよく乾燥させたものを煎じて服用すれば、血を補い、良く眠れるといわれる。 民間療法として、強壮、鎮咳、扁桃炎、咽頭炎にも効果があるともいわれている。 古書には「腎を温め、脾を補う」と記されている。 焼酎などに漬けて半月したものを1日1〜2個づつ食べるのも、滋養強壮などにおすすめ。 鱗茎を夏に掘りとって天日乾燥したものが生薬となり、薤白(がいはく)とよんでいて、狭心症の痛みの予防や、食べ過ぎによる食欲不振など、ラッキョウ同様に効果があるといわれ、薬草名もラッキョウと同じ薤白である。 薤白1日量3〜5グラムを、約600ccの水で半量になるまでとろ火で煮詰めて煎じた汁を、3回に分けて服用する利用法が知られている。 ノビルには胃腸を丈夫にし、身体を温める効果が期待される。 |
| その他 | 全国に70以上の方言をもつほどに山菜として親しまれ、万葉の昔から春の幸として伝えられてきた。 『古事記』(712年)に応神天皇の歌として、 「いざ子ども 野蒜摘みに 蒜摘みに」 また、『万葉集』の長忌寸意吉麻呂(ながのいみきおきまろ)の歌に、 「醤酢に 蒜搗き合てて 鯛願ふ 我にな見えそ 水葱の羹」 がある。「酢味噌和えのノビルと、鯛を食べたいと思っている私に、ナギ(ミズアオイ)の汁など見せないでほしい」と謳っている和歌である。 記紀の東征神話においては、白鹿に化けた地の神をヤマトタケルが蒜で打ち殺すエピソードがあるが、これもノビルである可能性が高い。 |
| 参照サイト・文献 |
食べる薬草事典/村上光太郎・著/農文協 ウィキペディア イー薬草・ドット・コム 日本薬草効能図鑑 松江の花図鑑 旬の食材百科 WITH HERBS わかさの秘密 |
| 関連記事 | [第53回] 地球の鼓動・野草便り 野草の保存食 |







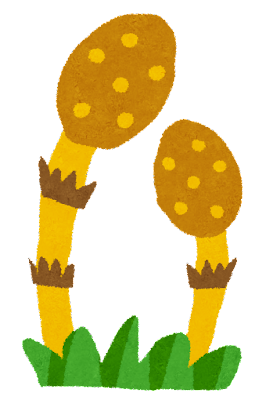

ところで前々回ヨモギに漂白効果や美白効果があると早とちりしたと思いました。それで東洋医学セミナー、映像配信で教えてもらった真実の見分け方で確認しないといけないと気がつきました。私自身はまだ完璧に見分けることはできていませんが、やはり漂白効果も美白効果もありませんでした。訂正してお詫び致します。漂白には重曹と酢を使っています。ついでにいうと汚れてすぐに唾液で汚れを落とすのが一番と着物関係の人から聞いたことがあります。何はともあれ、波動や真実を正しく調べられるようになり、間違わないようにしたいと思います。申し訳ございませんでした。
今年も早6月、野草があっという間に大きくなりました。今年は重曹と酢を使った米粉パンケーキに色々な野草を刻んで混ぜこんで、たくさんいただいています。春先まだ野草が少ない頃にミントが良く育ち、これが意外とパンケーキに混ぜ込むと歯ごたえが良くて匂いも軽減され食べやすく、ありがたかったです。モクレンの花びらを生でサラダにして食べてみたら、苦味もなくほんのり香りがしておいしかったです。クコの新芽もくせがなく美味しいのですが、虫が活動し始めるとほとんど虫食いになってしまうので、今の内にと少しいただきました。今年も自然の恵みにありがとう!!と言いつつ毎日元気をいただいています。