注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

🪧デモ活動は霞が関の官庁街でも行われている。
— Sputnik 日本 (@sputnik_jp) April 29, 2025
🔔 @sputnik_jp でもう一つの見方を https://t.co/1entZQLiDV pic.twitter.com/fVmAE9mKJt
昨日(4/29)の国民大集会
— 藤江成光@4月22日発売「おかしくないですか!?日本人・謎の大量死」 (@JINKOUZOUKA_jp) April 30, 2025
これが全く報道されないって、おかしくないですか!? https://t.co/OGQKzelQzS pic.twitter.com/kp3JgAkyMq
【財務省解体デモ】我那覇真子さん、素敵な言葉を紹介「だけど私に何ができるの?私はたった一人だもん、と世界中の70億人が言った」「グローバリストは本当に一握りで我々は数が圧倒的なんですよ」 https://t.co/CN1a4Crdrk pic.twitter.com/tHO3cRYgoT
— JMAX (@JmaxTopics) April 29, 2025
(中略)
集会とデモ行進を主催したのは、「いまのままなら財務省解体、厚労省解体等を求める国民の連合」(共同代表:柴田泰孝・小嶋有紀子)。2024年4月の池袋、同年5月の日比谷、同年9月の有明に続く、第4次国民運動と位置付ける。
(中略)
沿道には、デモに参加できなかった多くの市民がコールを唱和したり、声援を送った。
(以下略)




![[Bappa Shota] 超格差社会になった香港に中国人が大量移住し、中国人優遇の社会に / 日本政府が中国人へのビザを緩和したことに懸念「日本が香港のようにならないように祈る」](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2025/04/m429.jpg)


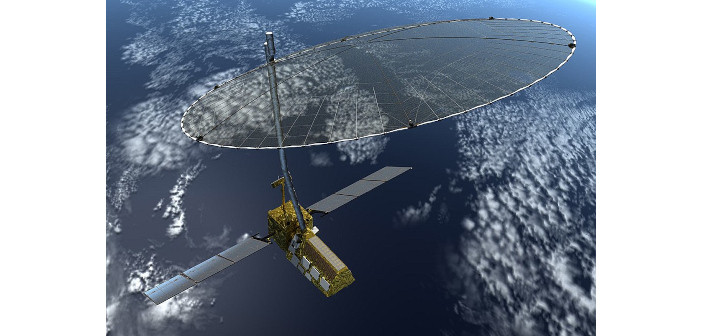





![[ゆるねとにゅーす] 兵庫県の百条委員会メンバーへの凄まじい誹謗中傷メールや嫌がらせ、「みんなでつくる党」ボランティアへのプライバシー侵害、人命が失われているのに動かない警察](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2025/04/m422.jpg)

 どんなにゅーす?
どんなにゅーす? 
これまで継続的に行われていた財務省解体デモは、珍しく大手メディアが報じていました。しかし29日の大集会は案の定、日本のマスコミは報じていません。目立った記事ではスプートニク日本と大紀元がありました。反ジャーナリストの高橋清隆氏の記事によると、国会前には数千人の人々が集まり、「パンデミック条約絶対阻止」「財務省解体」「積極財政推進 消費税廃止」「グローバリストの支配する財務省・厚労省を解体せよ」などを訴えました。林千勝氏は「暮らしと命と日本を奪おうとしているウォール街の代理人の国会議員700人は何やってんだ!」「今、日本は、ウォール街が長年かけたシナリオの下に侵されつつある」「有害な遺伝子製剤の投与や25%を目標にした消費税引き上げ、39%までの移民拡大政策、これらを防ぐのは、国民しかいない。われわれで阻止しよう!」と呼びかけました。
我那覇真子氏の言葉は印象的でした。「"だけど私に何ができるの?私はたった一人だもん、と世界中の70億人が言った"、グローバリストは本当に一握りで我々は数が圧倒的なんですよ。」自分一人の力は小さいように感じるけれども、実は圧倒的な力がある、と伝えています。