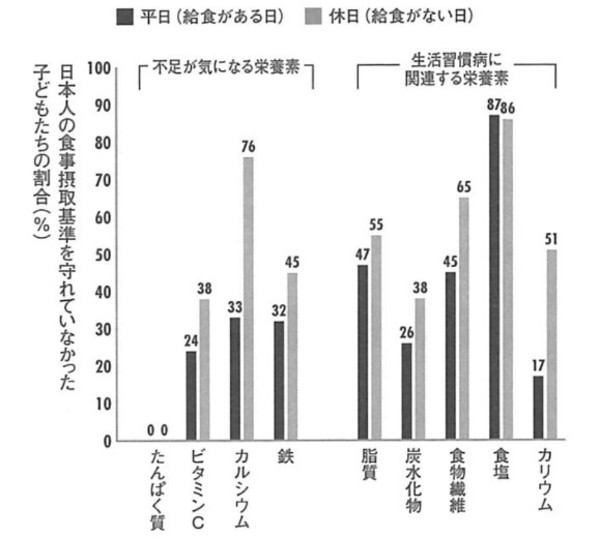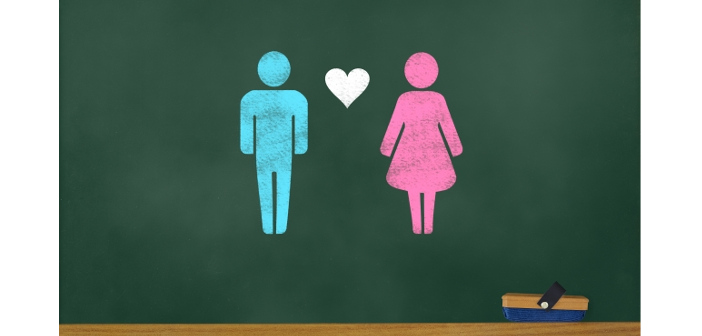読者の方からの情報です。
ニュースを見ていると、教室での授業より運動部の部活での感染拡大が多いような気がします。子供にも部活にはいかないようにさせました。退部届を受け取ってもらえなかったので。親としてどうするのが良いのか悩むところです。また海外での状況なども知りたいところです。部活に熱心な顧問ほどコロナを無視してそうで子供が変人扱いされそうで怖いです…。
先ほど公開された「ままぴよ日記55」では、海外の教育現場でのコロナ対応を紹介されていました。行政と学校、保護者との話し合いが活発で、メリット・デメリットを含め子ども達の登校や授業の方法を共に探っていました。
一方「日本ではこのような学校側の決定の過程で保護者に説明をしたり意見を聞くことはありません。その発想自体がないのです。保護者はいつも決定を丸投げされて戸惑うばかりです。」との現状が語られました。
それに呼応するような読者の方からの投稿がありました。学生の部活が原因と推測される感染が全国的に確認されています。しかし行政は検証も説明も対処も果たさず、学校も保護者や子ども達の不安に応える独自の判断をするのは難しいようです。濃厚接触に怯えつつの部活をしなくて済むよう、落ち着いて夏休みを過ごせるよう正しい知見に基づいた安全策を示してほしいと願わずにはいられません。しかし政府を挙げてGoToとなると、正行様の言われるように個々人が「変人」になる覚悟が必要なのでしょうか。
一方「日本ではこのような学校側の決定の過程で保護者に説明をしたり意見を聞くことはありません。その発想自体がないのです。保護者はいつも決定を丸投げされて戸惑うばかりです。」との現状が語られました。
それに呼応するような読者の方からの投稿がありました。学生の部活が原因と推測される感染が全国的に確認されています。しかし行政は検証も説明も対処も果たさず、学校も保護者や子ども達の不安に応える独自の判断をするのは難しいようです。濃厚接触に怯えつつの部活をしなくて済むよう、落ち着いて夏休みを過ごせるよう正しい知見に基づいた安全策を示してほしいと願わずにはいられません。しかし政府を挙げてGoToとなると、正行様の言われるように個々人が「変人」になる覚悟が必要なのでしょうか。
注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
————————————————————————

中学校の部活で集団感染 練習試合相手にも感染者 京都
引用元)
朝日新聞DIGITAL 20/8/1
京都市は、市立中学校の同じ部活動に所属する生徒らの間で、新型コロナウイルスの集団感染が発生したと7月31日に発表した。この中学校と練習試合をした2校でも感染者が出たため、市教委は3校の校内を消毒し、8月18日まで、部活動を含む全ての教育活動を中止することにした。
市教委によると、感染が確認されたのは計8人。うち7人は7月23~25日に計4校が参加した練習試合に出ていた。残り1人は感染した部員のクラスメートだった。
(以下略)
市教委によると、感染が確認されたのは計8人。うち7人は7月23~25日に計4校が参加した練習試合に出ていた。残り1人は感染した部員のクラスメートだった。
(以下略)
————————————————————————
感染した高校生の濃厚接触者は51人 大半が部活動の練習試合で 【新潟】
引用元)
3日に感染が確認された新潟県柏崎市の家族3人のうち、県立柏崎工業高校に通う男子生徒の濃厚接触者が51人に上ること分かりました。
男子生徒は7月27日から31日までの間は登校し、部活動にも参加していました。
県によりますと部活動では1日に練習試合を行っていて、対戦相手の高校の体育館で開かれたということです。濃厚接触者51人のうち大半は、この練習試合を通して接触していました。
(以下略)
男子生徒は7月27日から31日までの間は登校し、部活動にも参加していました。
県によりますと部活動では1日に練習試合を行っていて、対戦相手の高校の体育館で開かれたということです。濃厚接触者51人のうち大半は、この練習試合を通して接触していました。
(以下略)
————————————————————————
<新型コロナ>49人感染…岩槻高など 2人死亡 感染者トラブルで駆け付けた警官感染 3クラスターで増
引用元)
(前略)
県教育局によると、県立岩槻高校でこれまでに感染していた生徒2人と同じ部活動の生徒3人が新たに感染確認された。3日に判明した2人目の生徒の濃厚接触者は、体育の授業や食事で一緒だった生徒7人とされ、新たな感染者3人の濃厚接触者は調査中。県立学校ではこれまでに7校で学校関係者の感染が確認され、うち4校では2人以上が感染し校名を公表している。
(以下略)
県教育局によると、県立岩槻高校でこれまでに感染していた生徒2人と同じ部活動の生徒3人が新たに感染確認された。3日に判明した2人目の生徒の濃厚接触者は、体育の授業や食事で一緒だった生徒7人とされ、新たな感染者3人の濃厚接触者は調査中。県立学校ではこれまでに7校で学校関係者の感染が確認され、うち4校では2人以上が感染し校名を公表している。
(以下略)