————————————————————————

何もないノンプログラムの子育て広場
中学校で子育て広場を始めたのはいいのですが、一番の心配はママ達が来てくれるか?そして生徒が来てくれるか?でした。
この広場は自由参加です。楽しかったらまた来てくれるという流れを作らなければ義務感だけでは続きません。このことはいつも私の中の心配事でもあります。行って楽しいとは何か?居心地がいいとは何か?絶えず気を配りながら広場を運営してきましたが、回を重ねる度に子どもや中学生の「関係を作り上げる力」を信じられるようになってきました。というより、感動を覚えるようになりました。
ほとんどの子育て広場は、参加者確保のためにイベントばかり企画して呼び込んでいます。離乳食を出しますよ、工作しますよ、体操、ヨガ・・・。利用者の数が次年度の予算に影響しますから必死です。でも、そんなことばかりしていたら支援者は疲れて参加者も飽きます。参加者をお客様にしてしまっているのです。
私達は何もないノンプログラムの広場を目指しています。そこにどんなドラマが展開するか?全てお任せです。だからこそ居心地の良さが問われます。
スタッフは事務室に籠って次のイベントの準備や報告書づくりなどしません。いつもママ達に寄り添って孤立していないか?ストレスを抱えていないか?に配慮します。ママ達は相談したいときにいつでも相談でき、友達と出会ったり、助け合ったりできます。これが当事者支援の自然な子育て風景です。
» 続きはこちらから


















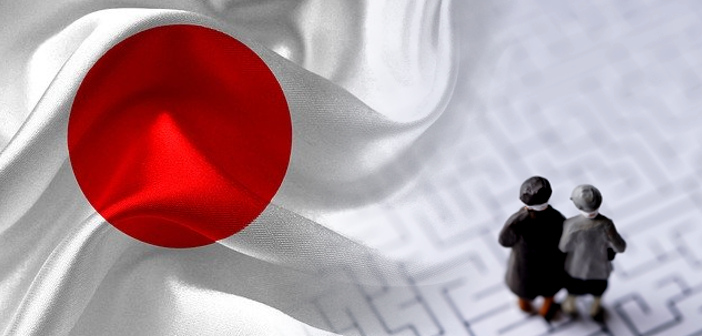








私はこの中学校で一度も問題行動を見たことがありません。