かんなままさんの執筆記事第23弾です。
————————————————————————

愛情という栄養
子どもが愛情を要求するのは、食べ物を要求するのと同じくらい当たり前です。皆さんは子どもが「おなかすいた」と言ったら、必ず食べ物を食べさせるでしょう。おなかがすいたらかわいそうだからと思って。
ところが愛情の要求をしている時にはあげないのです。私は愛情の要求の方が食べ物を与えることより大事だと言っています。
親は、たくさん愛情を与えないといけません。いい子に育つ、いい人格に育つには、たくさんの愛情が必要です
ところが愛情の要求をしている時にはあげないのです。私は愛情の要求の方が食べ物を与えることより大事だと言っています。
親は、たくさん愛情を与えないといけません。いい子に育つ、いい人格に育つには、たくさんの愛情が必要です
出典:「ぴ・よ・こ・と」竹下雅敏(著)
子供の”食事"に多大な関心を寄せるママたち
母親セミナーで、いつもテーマになるのが子どもの食事の事。子どもが食べてくれない、子どもが好き嫌いをする、料理を手際よく作るにはどうしたらいいのか?などで真剣に話し合っています。どうしてそのことが気になるの?と聞くと、「食事は子どもの健康と成長にとって大切なものだから」と言うのです。
そして、作る時間の確保が大変で、朝から作れる時に作っていますとか、夕方、テレビを見せたり、泣いていても構わず作りますと、健気です。毎日の事ですし、みんなよく頑張っていると思います。でも、もっと突っ込んで「泣かせてまで作るのはなぜ?」と聞いてみました。
「だって、決まった時間に食べないと、お風呂に入って、歯を磨いて、8時には寝かせつけられない。生活リズムをつけて、保育園や小学校に行く時に困らないようにしたい。自分を保つために私の時間も欲しい・・・だから絶対、食事の時間を守りたいのです」と、目標を決めて努力しているのです。
ママの悩み、子供の悩み
確かに保健師さんも保育園の先生も、生活リズムの大切さを指導されます。まじめなママほど、計画通りに行くことを目標にしてしまいます。そのために泣かせてまでも食事の支度をして、食べないことを叱り、どうしたら素直にお風呂に入るのか、歯を磨かせてくれるのかを悩み、結果的に追い立てて、怒って泣き寝入り・・・。寝顔を見ながらこれでよかったのか?と悩みが増えていくのです。
子どもの立場で考えてみたら・・・黄昏時は疲れて眠たくなったり、エネルギーが上手く発散できなくて鬱滞しがちです。これは体の事情です。でも、ママは構ってくれないどころか怖い顔して怒ります。そして、早くご飯を食べなさい!お風呂、寝なさい!・・・。どうしてママは受け止めてくれないのだろう。こっちを向いてほしいだけなのに。朝も「早く早く」と急かされて、怒られて保育園。ママは本当に私の事好きなの?
» 続きはこちらから


















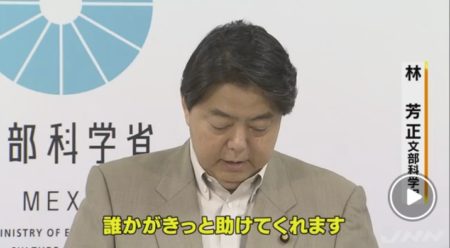






記事の中の上野動物園[公式]のツイートは、とってもいいですね。この前、パンダの赤ちゃんが生まれた時のニュースで、園長は、“母親が子育てに専念できる環境をまずはしっかり作り、しばらくは不安定な時期も続くので、観察をしっかりしていきたい”と話していました。
このニュースを夫婦で聞いていて、“パンダだったら、本当に大切な事は何かがわかってるね”と話しました。“子育てに専念できる環境”は、パンダのためには最も大切なことなのです。
ですが、人間の子の場合は、そうではないようです。母親は子どもを保育園に預けて、出来るだけ早く社会復帰することが望ましいようです。このパンダと人間の扱いの違いは何なのか? ここを少し考察すると、物事の本質が見えてくるのではないでしょうか。
記事の最後のあたりで、“しばしば自殺へと未成年の背中を押すのは…無関心であること…ほぼ全ての子どもは自殺前に注意を引こうと試みる”とあります。ほとんどの親は、子どもの成績には関心が高いものの、子どもの幸せのこと、あるいは子どもそのものには全く無関心なのではないでしょうか。
うちの家では、子どもが幸福であることを最優先にしていましたので、“学校に行きたくなかったら、行かなくてもいい”という専門家の助言を実践していました。“息子は週2回なら学校に行っても良い”ということで、小学校低学年では週休5日でした。そのせいか、実にのびのびと良い子に育ちました。つくづく、学校に行かなくて良かったと今でも思っています。
在学当時は、我が家の“積極的不登校”を批判的に見ていた担任の先生も、その後、ご自分の息子が不登校になるや考えを改めたようで、うちの息子が立派に成長したのを見て、羨ましがっていました。
この意味で、大人も子どもも、社会の枠から外れることを恐れたりすべきではありません。最も大切な事は、一人ひとりが輝くことで、成績や学歴等ではありません。その意味で、“積極的不登校”、あるいは“ポジティブな引きこもり”という概念は、推奨すべきものだと思われます。