————————————————————————

北半球全体が酷暑 ~猛暑の過ごし方~
第15楽章の記事を書いた後から、ドイツのベルリンも猛暑が連日続いています。
欧州全体で猛暑が続き、北半球全体が酷暑になっています。
まずは、popoちゃんの記事の重要な動画をもう一度
見て、目覚めて、頭を冷やして・・。
ぺりどっと通信、足もとの記事も実用的で、
毎日参考にしております。
ドイツでは、普通、エアコンが家にありませんので、
私も毎日、まず、手のひらを冷やしたり、足もとを冷やしています。
そして、猛暑のときは、午後2時から午後4時まで、お昼寝を
した方がいいのではと思っています。
(日本の働き方では、そんなこともできませんが・・)
昔、インドネシアで暮らしている時がありましたが、東南アジアの方は、
午後2時ごろになると、お店も閉まり、お昼寝をしていたような記憶もあります。
宗教講座 中級コース25回 特殊相対性理論(タキオンと斥力物質、後半) の講義の中でも、竹下先生は、寝ることでエネルギーを充電していると解説されています。
寝ることの良さについては、こんな記事も発見。
「デキる人は「寝る・風呂・歩く」を怠っていない」
創造性を生み出す習慣を研究するペンシルベニア大学の心理学者スコット・リー・カウフマンの記事で、ポール・マッカートニーが「イエスタデイ」を書いた時や、サルヴァドール・ダリの創造の源が夢であったこと、また発明家のニコラ・テスラや、哲学者のイマヌエル・カントが散歩中にひらめきを得たことなどが紹介されています。
創造性を生み出す習慣を研究するペンシルベニア大学の心理学者スコット・リー・カウフマンの記事で、ポール・マッカートニーが「イエスタデイ」を書いた時や、サルヴァドール・ダリの創造の源が夢であったこと、また発明家のニコラ・テスラや、哲学者のイマヌエル・カントが散歩中にひらめきを得たことなどが紹介されています。
(編集部)
世界を見まわすと、暑いときは、やってられない・・
グダグダしているのがあたりまえなのに・・という雰囲気も
多いです。
(自分の身を守るために、30度以上では、動かない方が
自然な姿、人間の本能だと感じます。)
熱中症は貧血なんかとは違う。
— cmk2wl (@cmk2wl) 2018年7月26日
一度でも倒れたらそのダメージは重大で、その後の人生に影響を与える。
強制感の強すぎる日本の学校
それなのに、小学校で水筒をもっていってはいけないとか、
暑い中でクラブ活動を強制されたりなど、
日本は、少し頑張りすぎ、強制感が強すぎるのでは
ないでしょうか・・。
こちらのクラブ活動の件も、驚愕しております。
ヤマ・ニヤマの霊律にも反しています。
部活で死亡。「演技じゃろう!」と蹴りをいれ「熱中症じゃないことぐらいわかっている!」と馬乗りになり平手打ちを何度も。生徒は嘔吐して死亡。殺人的行為なのに不起訴(無罪放免)、加害者の損害賠償100万円。法治主義による正義はまだ遠い。 pic.twitter.com/JIOMOh4oq4
— 竹内幹 (@takekan) 2018年7月23日
小刻みに体を痙攣(けいれん)させ、視線も定まっていませんでした。淡々と処置を行う医師と看護師、「剣太はどうなってしまうのか…」....その数時間後、目は乾ききって閉じることもできず、大きな前歯は1本折られ、変わり果てた姿で剣太は息をひきとりました。https://t.co/Un6i3hpXnC
— 竹内幹 (@takekan) 2018年7月25日
「大分県剣道部員死亡事件」
2009年8月、剣道部の練習中に、主将だった生徒が重い熱中症と顧問による暴行で死亡した事件。
指導者らが熱中症を軽く考え、倒れて異常な状態の生徒に暴行を加え続けた。指導した顧問、副顧問及び学校の責任が問われ裁判になった。
2009年8月、剣道部の練習中に、主将だった生徒が重い熱中症と顧問による暴行で死亡した事件。
指導者らが熱中症を軽く考え、倒れて異常な状態の生徒に暴行を加え続けた。指導した顧問、副顧問及び学校の責任が問われ裁判になった。
こちらの事件で、部活動の顧問の先生が、演技をするんじゃない・・・
と生徒に強制的、軍隊的、生徒を奴隷扱いしている点に異常さを感じます。
生徒の顔、様子などを見て、具合が悪いことを察知できないようであれば、
教育者、大人として問題である点です。
これは、子供にしつけ・・・と称して、親が強制していることともつながり、
竹下先生の講義でも、しつけは、人間にすることではないとおっしゃられていました。
つまり、学校教育や部活動が軍隊的になっていること・・・
そんな点は、小さなことから、大きなことまで見られますし、
そんなことが、最悪の事態になったことが、この事件だと感じています。
高校野球などの考え方も時代遅れだという記事です。
「夏の甲子園「選手の未来を考えない」指導者もファンも時代遅れだ」
〜 酷暑の中、連投させるのは危険と分かっていてなお、勝利のために投手をマウンドに送り続ける高校野球はおかしい。「連投させない指導者」と「そんな指導者を雇う学校」が求められる。
〜 酷暑の中、連投させるのは危険と分かっていてなお、勝利のために投手をマウンドに送り続ける高校野球はおかしい。「連投させない指導者」と「そんな指導者を雇う学校」が求められる。
甲子園に出場する高校球児、特にピッチャーなどは、
連投で肩や肘を痛めて、将来の道を閉ざされるという例があると
以前、元巨人の桑田投手が話されていたことも思い出します。
頑張るのがいいことではない、まず、身体を大切にすることが重要だという
価値観をすべての人が持ってほしいものです。
みんながなぜか無謀にも頑張っている社会全体を変えたいものです。
私自身、小学校時代から、学校というものは、
あれをしてはいけない、これをもってきてはいけないなど
うるさいものだなと感じておりました。
そして、子供心にいつも、どうでもいいことなのに・・と、
本当にあきれて過ごしておりました。
私の経験でも、今でもよく覚えているのが、書道の時間に
習字道具をもってくるのですが、
先生が言っていないものは、持ってきてはいけないということで、
半紙は持ってこなくてもいいということなのですが、
しかし、半紙を準備万端に持ってきた生徒がいて、
それはそれで、別にいいわけで、使用しないなら、
持ち帰ればいいだけなのに、
指示していないものを持ってきたとかで、
問題になったりして、本当にばからしい騒ぎっぷりでした。
また、中高時代には、お菓子を学校に持ってきてはいけない
ということで、生徒全員のカバンをチェックするという、
またまた、意味のない検査があり、
飴を持ってきている生徒がいて、注意されたりなど、
(喉が痛い時など、必要なのに・・と思いながら、)
これまた、あきれるだけで、時間だけがただただ、無駄でした。
(例えば、バッチ社のレスキューレメディーの
キャンディーなどは、自分の体調を守るために持ち歩く人も
いるのに、こういうのはどうなるのでしょう・・・)
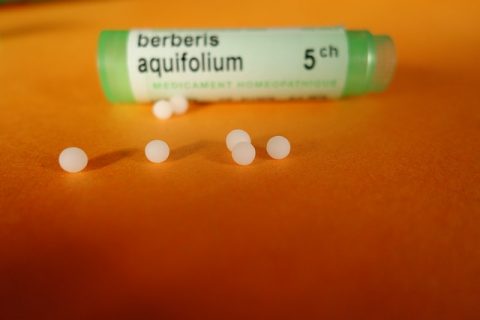
pixabay[CC0]
生徒のことを本当に考えてしていることなのか、
ただ、先生の威厳なのか、権威なのかを見せつけて、生徒を強制的に従わせることを
意図しているのか・・わからなくなります。
現在、我が家の息子は、17歳で、ドイツの学校に通学していますが、
もちろん、ドイツでは、クラブ活動の強制はなく、
学校では、卓球とバスケットボールのクラブがあるだけで、
ほんの少数の生徒が参加しているだけです。
例えば、日本のようにスポーツで活躍している生徒がヒーローだったり、
もてはやされるような雰囲気はまるでありません。
また、何かに優勝したりした生徒を持ち上げる雰囲気も感じられません。
というより、みんながバラバラな感じなので、
全体が見えない感じもあるのかもしれません。
日本のように、クラスなどがまとまりとして見えてこないのです。
みんなで協力する、クラスでまとまるなどの雰囲気がありません。
息子によると、学校にクラブ活動は必要なく、外で個別の活動の方がいい、
学校と好きな活動などが同じ場所にない方がいいと言っています。
日本では、いじめ問題なども、強制的なクラブ活動から
発生している場合も多く、
友達といる時間も学校では長くなりますので、そんなところも
原因ではないでしょうか・・。
学校とは、勉強する場であり、それだけでよいわけで、
文化祭や体育祭などもおまけのイベントなのですから、
強制される必要もないと思うのです。

Author:Seaclub[CC BY-SA]
私の経験からも、文化祭とか体育祭とか、クラブ活動なども
ただ、面倒なイベントという思い出です。
好きならば、参加すればよいし、必要のない生徒に強制するのは
おかしいと感じます。
中学生、高校生など、部活で活躍したことが、
内申書や成績に関係してくるのも、どうなのか・・と思います。
活躍したことが、プラスになるのはいいのですが、
活躍しないからといって、マイナスにしてはいけないと思うのです。
日本の学校の文化祭、体育祭、部活動なども
先生たちがいかに活動しているかなど、校長先生からの評価にもつながり、
出世に関係してくるという意味合いも多いのではないでしょうか・・。
実際に息子のドイツの学校では、体育祭はなく、
スポーツフェスティバルで自分の体力測定会のようなものになります。
文化祭は、音楽やダンスが好きな方が参加しているだけになります。
また、日本の学校の先生は、報告書を書かなければいけないと
また、それが時間がかかり大変であると聞いたことがあります。
日本の学校では、修学旅行なども学年全体の行事で、全員同じところに
集団で行くことが多いですね。
1学年だと、3クラスとして、100人以上になっているかと思います。
(これだけでも、動きがとれないことがわかります)

Author:松岡明芳[CC BY-SA]
ドイツの学校を見ていると、修学旅行もクラス30人単位で、
クラスの先生が主導で、隣のクラスの修学旅行はまた、別で、
先生が好きなところを選んで自由に行っているようです。
修学旅行も日本のように、意義をもたせるのではなく、
ただの遊び、お楽しみだけです。ただのクラス旅行です。
例えば、息子のクラスは、夏にデンマーク方面の海に行きましたが、
隣のクラスは、冬にオーストリア方面のスキーに行ったりなど、
担任の先生の好みによって、それぞれになります。
また、先生が行きたくない場合は、行かないのです。
そして、行きたくない先生は、他の先生にクラス旅行に
代わりに行ってもらうことを依頼することもできるのです。
(なんと自由で、臨機応変で、良いことだと思います。
これが、日本だと、ずるいとか勝手だとかで、問題になりそうですね。)
(ドイツの学校制度は、ドイツの州によって違いますので、
ここでお話ししているのは、ベルリンの息子の学校から見たことからに
よるものになります。ドイツの他の州や学校により違うかもしれません。)
小鳥のように思うままに唄え
夫婦33 天界(ギタンジャリ) の中で、竹下先生は、
教育の理想とは、小鳥のように思うままに唄え Byタゴールの教え
と解説されています。
外側にあるものを詰め込むのではなく、内にあるものすべてを表面に出すこと、
自分を自然に表現することが教育であると講義されています。
ドイツ語で、教育とは、Erziehung 引き出すもの・・になります。
日本語でも、強制的なイメージの教・・という漢字をやめて、
「引育」にすれはいいのかも・・と思ってしまいました。
自分を自然に表現しているピアニストといえば、
ショパンコンクールの審査員を断り、
間違えたっていいじゃない、機械じゃないんだから・・などの
名言でも有名な、フジコ・ヘミングさんを思い浮かべます。


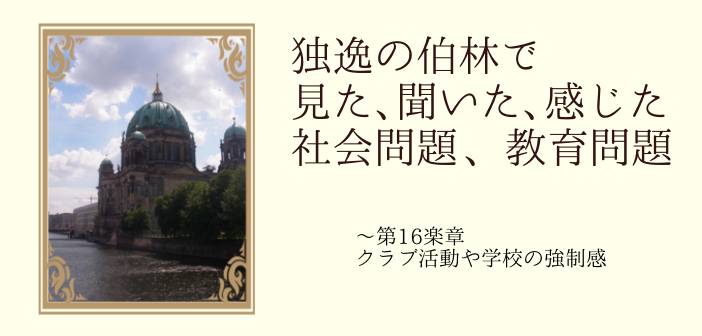

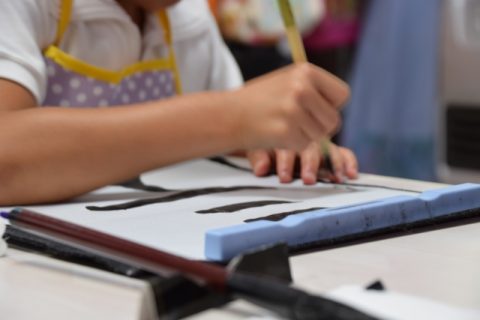

第16楽章では、ドイツと日本の学校 第2弾、
クラブ活動や学校の強制感について見ていきたいと思います。