竹下雅敏氏からの情報です。
注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
————————————————————————

子どもに対しての虐待は、その子どもに「DNAレベルの変化」を引き起こすことが国際的研究で示される。…それがもし「人類全体の遺伝子」として受け継がれていくのなら…人類は結局滅亡するかも…
転載元)
In Deep 18/10/3
(前略)
(中略)
この後者の記事は、昨年 12月のものですが、この研究では、単に赤ちゃんの時だけの健康の状態ではなく、「それがその人の一生の肉体的条件を左右する」という可能性を示したもので、記事では以下のように書いています。
さきほどの「ストレスは DNA で変化する」ことを取りあげた記事でご紹介した医薬系メディアの内容には、以下のような記述があります。
(中略)
「現在の日本の児童虐待の現状」をあらわした下のグラフです。
「子どもへの虐待がものすごく増えている」ことは事実だと思われます。(中略)… その子どもたちは、全員ではないだろうにしても、「それぞれ DNA に傷を受けて、それは基本的に一生修復されない」のです。
(中略)
「人間は遺伝子を持ち、その遺伝子は受け継がれる」という基本的な輪廻から考えても、今の時代は、過去にないほどの「破壊の時代」だと私が考える根幹はこのあたりにもあります。
(以下略)
児童虐待、被害者に残る「分子の傷跡」 研究
AFP 2018/10/03
虐待を受けた子どもは、そのトラウマ(心の傷)を示す物質的特徴が細胞の中に刻み込まれている可能性があるとする研究論文が2日、発表された。
研究は、トラウマが世代間で受け継がれるのか否かをめぐる長年の疑問解明への一歩ともなり得る。
カナダ・ブリティッシュコロンビア大学などの研究チームは今回の研究で、児童虐待の被害者を含む成人男性34人の精子細胞を詳しく調べた。
その結果、精神的、身体的、性的な虐待を受けたことのある男性のDNAの12の領域に、トラウマによる影響の痕跡がしっかりと残されていることが分かった。
(中略)
遺伝子をめぐってはかつて、受精時において既にプログラムが完了しているものと考えられていたが、現在では、環境要因や個人の人生経験によって活性化・非活性化される遺伝子も一部に存在することが知られている。
(以下略)
(中略)
AFP 2018/10/03
虐待を受けた子どもは、そのトラウマ(心の傷)を示す物質的特徴が細胞の中に刻み込まれている可能性があるとする研究論文が2日、発表された。
研究は、トラウマが世代間で受け継がれるのか否かをめぐる長年の疑問解明への一歩ともなり得る。
カナダ・ブリティッシュコロンビア大学などの研究チームは今回の研究で、児童虐待の被害者を含む成人男性34人の精子細胞を詳しく調べた。
その結果、精神的、身体的、性的な虐待を受けたことのある男性のDNAの12の領域に、トラウマによる影響の痕跡がしっかりと残されていることが分かった。
(中略)
遺伝子をめぐってはかつて、受精時において既にプログラムが完了しているものと考えられていたが、現在では、環境要因や個人の人生経験によって活性化・非活性化される遺伝子も一部に存在することが知られている。
(以下略)
(中略)
この後者の記事は、昨年 12月のものですが、この研究では、単に赤ちゃんの時だけの健康の状態ではなく、「それがその人の一生の肉体的条件を左右する」という可能性を示したもので、記事では以下のように書いています。
他の実験などと照らし合わせた時に、「子どもの時に生じる DNA の差異は、その人の健康に一生影響するかもしれない」というところにまで可能性が及んでいます。
つまりは、
「自分の子どもをできるだけ健康にしたいのなら、生まれてすぐの頃に、できるだけ肉体的接触をたくさんもってあげること」
ということになりそうなのです。この「健康」には、肉体的なものだけではなく、精神的、心理的な健康も含められます。
(中略) つまりは、
「自分の子どもをできるだけ健康にしたいのなら、生まれてすぐの頃に、できるだけ肉体的接触をたくさんもってあげること」
ということになりそうなのです。この「健康」には、肉体的なものだけではなく、精神的、心理的な健康も含められます。
さきほどの「ストレスは DNA で変化する」ことを取りあげた記事でご紹介した医薬系メディアの内容には、以下のような記述があります。
ストレスに応答する異常な DNA の変化は、DNA 結合タンパク質を異所的に生成されること(本来発現する場所以外で遺伝子が発現しタンパク質が生成されること)によって精神神経的疾患の発症に寄与すると推測されている。
(中略)
「現在の日本の児童虐待の現状」をあらわした下のグラフです。
日本の児童虐待の相談対応件数の推移(1990 年-2014 年)
(中略) 「子どもへの虐待がものすごく増えている」ことは事実だと思われます。(中略)… その子どもたちは、全員ではないだろうにしても、「それぞれ DNA に傷を受けて、それは基本的に一生修復されない」のです。
(中略)
「人間は遺伝子を持ち、その遺伝子は受け継がれる」という基本的な輪廻から考えても、今の時代は、過去にないほどの「破壊の時代」だと私が考える根幹はこのあたりにもあります。
(以下略)




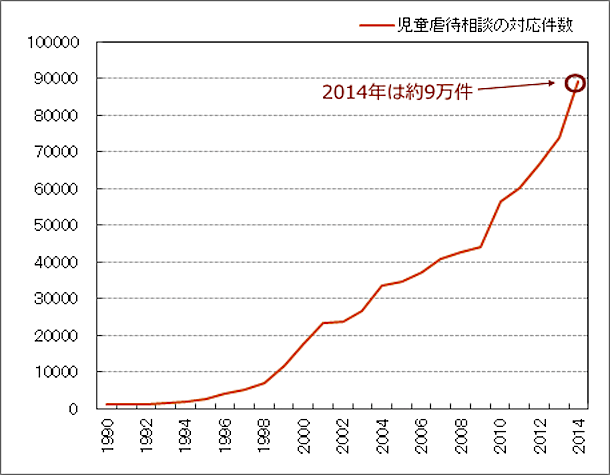




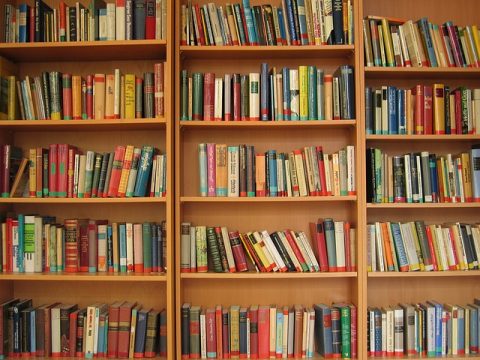
















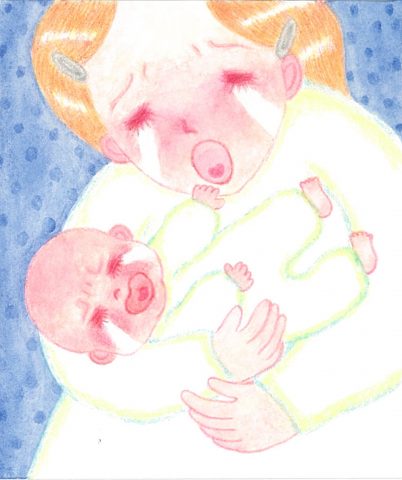

In Deepさんが以前取り上げた記事で、“赤ちゃんは「抱っこ」など肉体的接触を数多くされるほど「DNAが良い方向に変貌する」”ことがわかっています。これらのことから、赤ちゃんが生まれたら、出来るだけたくさん、両親が赤ちゃんを抱っこしてあげることが重要だとわかります。
ところが、現状では非正規雇用の増加に伴って、女性も仕事を持たなければ、普通の暮らしすら難しくなっています。このため、幼い子供を保育園に預けて働きに出ようとする女性が多くなっています。
私は、幼い子供を保育園に預けることは、非常にリスクを伴う危険な行為だと考えています。実証されたデータがないので、はっきりしたことは言えないのですが、幼い子供にとって、母親が傍に居ないことは、虐待に近いストレスを与える可能性があります。
実際に、私たち夫婦は、子供が生まれて歩けるようになるまで、抱き癖がつくと言われるほど子供を抱っこして育てました。その結果は予想した通りで、大変落ち着きのある心根の優しい子に育ちました。
息子は、保育園、幼稚園には行かず、小学校に入ったのですが、そのあまりの落ち着きぶりから、同級生に“竹下じいさん”と言うあだ名がつけられたほどです。
私の見解では、生後3カ月たったら、“赤ちゃんは泣かない”のです。赤ちゃんが泣くようでは、私の基準からは、子育ての失敗の範疇に入ります。
その意味で、この地球上でまともに子供を育てている両親はほとんど居ないと考えています。子供をきちんと育てれば、世界の平和はすぐにやってくるでしょう。
そのような子育てができる社会に変えていくとことが、最も大切だと考えています。