戦争ごっこ
やっと春めいて来ました。野草たちも待ちわびていたかのように、日ましに顔をのぞかせています。
先日、広島の廿日市市の上空を艦載ヘリが低空飛行した記事が掲載されていましたが、北広島町芸北地域では、戦闘機が低空飛行の上、火炎弾「フレア」が射出されたというのです。

以下、広報誌より引用します。
『在日米軍機の低空飛行による火炎弾「フレア」射出訓練を日本の地上部で行わないよう求める意見書』
10月11日午後、芸北地域の雄鹿原地区上空で米海兵隊岩国基地の米軍機が、低空で飛来し、火炎弾「フレア」の射出を行いその後、急上昇して旋回するという訓練が、数分間隔で十数回にわたって行われた。これが何の通告もなく、突然行われたため、住民にとっては、ただでさえ爆音と共に急降下してきて目の前に迫ってくる戦闘機に驚き、恐怖を感じさせられた上に、さらに実弾射撃を思わせるような一瞬眩しく光る正体不明の火の玉が射出されたことに、さらに大きな不安をおぼえるものであった。
当地域は、国道186号線が通り診療所や郵便局、民家が点在し近くにはこども園や中学校、高等学校もあり、普段は人々が穏やかに生活している。こういう場所で、上述のような実践訓練が行われることは、地元住民に与える影響が大きく、容認することができない。(中略)
よって本町議会は、町民の平穏な暮らしと安全を守るため、左記のことを米国および米軍に強く求めるよう日本政府に要請する。(中略)
平成29年11月8日 広島県北広島町議会
【提出先】 内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、総務大臣

私も大好きな八幡湿原がある芸北の植物観察に行っていて、何度もジェット戦闘機の爆音に驚かされたことがあります。 静かな森に轟音が響き渡ります。動物たちもさぞ驚いていることでしょう。

以前地元の人に聞いた話では、ベトナム戦争の頃にはもっと頻繁に飛んでいたようです。ベトナム戦争が終わって元米兵たちが家族連れで訪ねてきたそうです。地元にある鎧滝が飛行機からよく見えて、故郷の山を思い出していた。一度訪ねてみたかったと。
この話を当時は何気なく聞いていたのですが、地元では何十年も前から戦闘機の爆音があったということです。それには半ば慣れていた住民も今回の低空飛行と火炎弾射出に、まるで攻撃されるような恐怖を覚えられたにちがいありません。
シリアなど紛争が続いている地域では実際に爆弾が使われ爆発しているのが、いかに恐ろしいことかよくわかります。沖縄では墜落や落下事故などもあり、頻繁に低空飛行が行われているのでしょう。他人事だと思っていたら大きな間違いだということだろうと思います。また、日本がアメリカの植民地である現実でもあります。こんな攻撃まがいの訓練をアメリカの住宅地や家族がいる場所では決して行わないでしょう。
以前オスプレイが日本各地の上空を飛ぶという時にも、反対署名をした覚えがありますが、まったく聞き入れられていません。今回町議会が提出した意見書に、はたして今の国政が対処するのか疑問です。今の政権に根本的な対処など・・・。まず国民の正しい認識と自覚が必要で、そのためにも真実の情報が重要です。報道機関で働いている人たちも、決して他人事ではないということが、実際に起きてからでは遅いのですが!!
» 続きはこちらから


![[第52回] 地球の鼓動・野草便り 戦争ごっこ](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2018/03/52.jpg)

![[第51回] 地球の鼓動・野草便り 植物ホルモン](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2018/03/51.jpg)















![[第50回] 地球の鼓動・野草便り カブ・ダイコンと大豆・小豆](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2018/02/50.jpg)














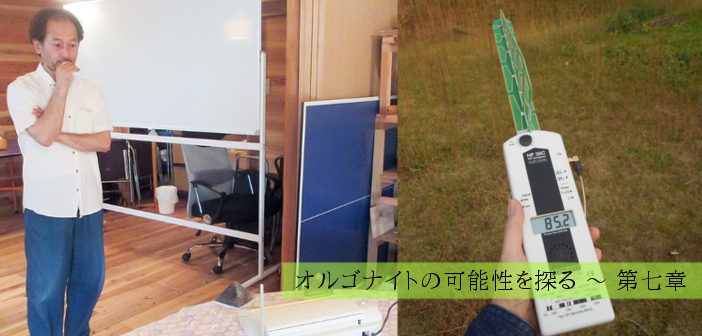







![[第49回] 地球の鼓動・野草便り 帯が電磁波防止に?](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2018/02/49.jpg)













