注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

ロシアのプーチン大統領が、アメリカのトランプ大統領との電話会談の中で、「ベネズエラの主権を決定する権利は同国民のみにある」と発言しました。
イルナー通信によりますと、プーチン大統領はこの電話会談で、「ベネズエラに対する外国の内政干渉や、武力行使による政権交代工作は、危機の政治的解決のプロセスに打撃を与えることになる」と釘を刺しました。
アメリカはここ数週間、ベネズエラの反体制派指導者フアン・グアイド氏を支持し、同国でのクーデター実施を狙っています。
トランプ大統領とプーチン大統領はさらに、ロシア、中国、アメリカによる新たな核合意締結に関して意見交換を行いました。
トランプ大統領はこの電話会談後、ツイッターで、プーチン大統領との会談は長かったが非常に良好なものだったとし、「ロシアや中国と妥協することはよい事だ」としました。
(以下略)
ベネズエラのパドリノ国防大臣が、「我が国の首都カラカスで暴動を起こそうとした兵士らの80%は、反体制派指導者グアイド氏に欺かれた人々だ」と語りました。
(中略)
ベネズエラのアレアサ外相は同日、クーデターを試みたのはグアイド氏に挑発されたわずか30名ほどの兵士のみだったことを明らかにしました。
また、「今回の少人数のクーデターは、ボルトン米大統領補佐官の教唆によるものだった」としました。
「全ての軍は我々の戦いに合流せよ」とホワン・グァイドのクーデター宣言 https://t.co/oABW0hCsSX
— mko (@trappedsoldier) April 30, 2019
首謀者レオポルド・ロペス! https://t.co/FaiZS626Gf
— mko (@trappedsoldier) April 30, 2019
クーデターに参加した下級兵士25名はブラジル大使館に亡命
— アジア記者クラブ(APC) (@2018_apc) May 1, 2019
ラ・カルロタ空軍基地の奪取をめざして発砲した下級兵士のブラジル大使館への亡命が認められた。将校は含まれていない。基地には撃退され侵入できなかった。野党支持者も武装していた。https://t.co/HrmmRBGqA0
「レオポルド・ロペスがチリ大使館に政治亡命を要求した。この連中は敗北した。しかしこのフィクションの政府には責任を取ってもらう」―ベネズエラ国連大使サミュエル・モンカダ https://t.co/Cmz95MhKsZ
— mko (@trappedsoldier) May 1, 2019
「ボルトンは現地からニュースが伝わる前に、クーデターが失敗したと語った。すなわち彼が背後にいたということだ」―ベネズエラ国連大使サミュエル・モンカダ https://t.co/wbtk8UXZW3
— mko (@trappedsoldier) May 1, 2019
» 続きはこちらから








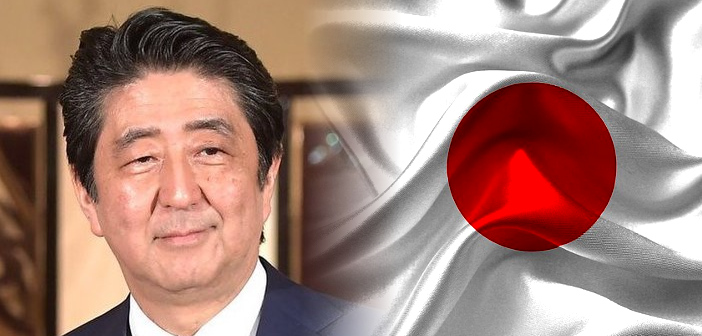







一連のツイートをご覧になると、フアン・グアイド氏のクーデター宣言からクーデター失敗の理由に至るまで、時系列で示されており、表面的には「米国の没落を象徴」する出来事になっています。
イランのロウハニ大統領には、「アメリカは大口を叩くが、力はない」と言われる始末です。こうした事態を受けて、櫻井ジャーナルでは、急速に弱体化するアメリカに無条件で従う日本は近い将来に破滅してしまう状況になっているとして、 「追いつめられた安倍政権」と題する記事を書いています。
櫻井ジャーナルがトランプ政権をどのように見ているのかは、はっきりとしません。トランプ大統領とQグループは、ディープ・ステートを追い詰めているのですが、ひょっとしたら、櫻井ジャーナルはトランプ大統領が、ジョン・ボルトン補佐官やポンペオ国務長官に騙され、支配層の言いなりになっていると考えているのかも知れません。
しかし実際には、やのっちさんのツイートにあるように、ジョン・ボルトン補佐官は、“トランプのために働いている”のです。このツイートの内容がQグループに繋がっているJoe M氏のものだということに注意してください。なので、これは正確な情報なのです。波動を見れば直ちにわかるのですが、ジョン・ボルトン補佐官やポンペオ国務長官は、意図的に道化役を演じています。それどころか、悪魔的人相のエイブラムズ氏もまたそうです。
彼らは、ディープ・ステートが仕掛けたベネズエラ介入に形の上で乗って、結局はわざと失敗しています。こうすることで、世間の注目はベネズエラに集まり、トランプ政権が着々と進めている内戦に対する準備には注目が向かわないというわけです。
トランプ大統領が彼らに騙され、ベネズエラ介入が大失敗に終わったのだとすれば、トランプ大統領は頭にきて責任者を処分するはずですが、トランプ大統領の彼らに対する好意は、依然高いままです。こうしたことはすぐに調べられるので、ぜひ確認してみてください。