注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
————————————————————————
フルフォード情報英語版:西側内戦がクライマックスに近づき、巨大ブラックスワン*が予想される
両者の激化する戦い
Mega Black Swan Expected As Western Civil War Nears Climax
By
Benjamin Fulford
March 11, 2024
2 Comments
The undeclared civil war raging in the West is headed for some sort of mega black swan event climax. The white hats are trying to bankrupt the Satanists and their entire fake US government show. The Satanists are planning some sort of mass murder event to try to stay in power. Both sides might use earthquake weapons and other electromagnetic forms of warfare. The only thing for sure is major fireworks.
西側で激化している未宣言の内戦は、何らかの巨大なブラックスワンイベントのクライマックスに向かっている。ホワイトハットは、悪魔崇拝者たちと彼らの偽の米国政府のショー全体を破産させようとしている。悪魔崇拝者たちは権力を維持するために、ある種の大量殺人を計画している。両者とも地震兵器やその他の電磁波を使った戦争をしかける可能性がある。確実なことは、大規模な花火があるということだ。
The previous attempts to bankrupt the US Corporation were delayed by events like 911 and the March 11, 2011 Fukushima nuclear and tsunami mass murder event. This time signs are either a massive earthquake or some kind of electro-magnetic attack to be blamed on a solar flare are being planned. That is why decisive action against the Khazarian Mafia leadership must be taken before they can stage another mass murder sacrifice to Satan.
米国株式会社を破産させようとする以前の試みは、9.11や2011年3月11日の福島原発事故と津波による大量殺人のような出来事によって遅延した。今回は、巨大地震または太陽フレアによるとされる何らかの電磁波攻撃が計画されているようである。だからこそ、ハザール・マフィアの指導者たちが再びサタンへの生贄として大量殺人を行う前に、断固とした行動を起こさなければならないのだ。
Speaking about which today is the 13th anniversary of the Fukushima attack. Most of the perpetrators like top Jesuit Hanz Kolvenbach were hunted down and killed shortly afterwards. However, two of the masterminds, self-described top Satanist Leo Zagami and Israeli Crime Minister Benyamin Satanyahu are still at large. They are being hunted down and will be brought to justice.
そういえば、今日は福島原発事故から13年目である。イエズス会のトップであるハンツ・コルヴェンバッハなどのほとんどの犯人は、その後すぐに追いつめられ殺害された。しかし、首謀者の2人、自称悪魔崇拝者のレオ・ザガミとイスラエルのベニヤミン・サタニヤフ【ネタニヤフ】犯罪首相はいまだに逃れている。彼らは追い詰められ、裁判にかけられるだろう。
» 続きはこちらから








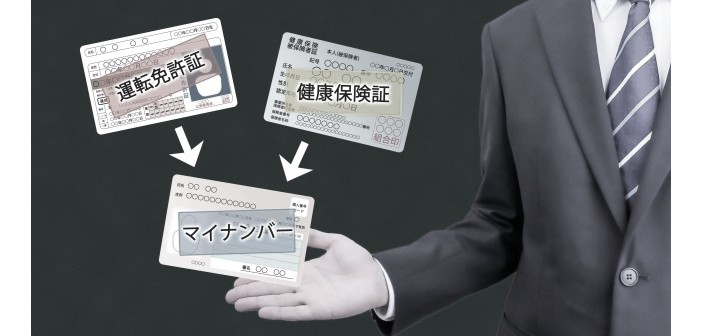









なぜ、高齢者バッシングの動きが目立つのか、それは政府、財務省の狙いがありました。
現役世代の社会保険料を減額する方法がいくつかある中で、政府が絶対にやらないのは「国がお金を出す」ことです。プライマリーバランス黒字化目標のためには公費負担を増やすことは検討されません。政府が最も望むのは「国民の負担率を上げること」で、安藤氏の説明によれば、維新の改革案を待つまでもなく政府はすでに、高齢者の資産や所得に応じた自己負担増を検討しているようです。それがうまく行ったら、次は現役世代を含めた国民の負担増の段階です。保険料率や消費税率アップを行います。
これらを行うための工作として、まずは高齢者と現役世代の世代間格差と分断をあおります。次に、財務省が政治家にレクチャーをして高齢者の負担増の必要性を発信させます。維新や国民民主など野党にも言わせます。さらに影響力のある人物に、現役世代が高齢者のせいで被害を被っていることや高齢者の存在が負担であることを公言させます。まさに成田悠輔氏の発言のように、国民を分断させ政府方針の自己負担増に賛成させるように仕向けます。
そして最も重要なことは「公費負担ができることを考えさせない」つまり「国債発行を考えさせてはいけない、最初から排除する」ことで、この工作はとてもうまく行っていると述べています。「国債発行?ないない」「MMTなんてありえないわ」「インフレになってるのにまだ国債出すの?ありえへん」こうしたコメントはネット上にも溢れています。
政府のウソ、財務省のウソにだまされないで、私たちは高齢者に怒りを向けるのではなく、政府に対して怒りの矛先を向けるべきだと訴えておられました。