我が町の子育て支援事業が全てストップ
未知のコロナウイルスが世界中で蔓延し、各地でロックダウンが起こり社会の機能がストップしてしまいました。その大きな潮の流れに引き込まれて私もコロナ情報から目が離せなくなり、家業の感染予防対策に追われ、子ども達から寄せられる世界の情報に驚き、我が町の子育て支援事業が全てストップする事を受け入れてきました。
でも気が付けばウイルスを封じ込めるはずもなく、世界中の経済まで大打撃を受け、
一番被害を被っているのは大企業を下支えしてきた
中小企業やサービス業、フリーランス、学生、子ども、子育てしている家族、医療従事者と、まるでドミノ倒しのように負の連鎖が始まり、それに乗じて不満が募った人のエネルギーが怒りと化しています。
コロナ後の世界はいったいどこに行こうとしているのでしょうか?弱い立場の者は流れに巻き込まれてもっと声をあげられなくなってしまうのでしょうか?
それは私自身の中でも起こりました。自分ではどうすることもできないドミノ倒しが始まったのです。
コロナ騒ぎに夢中になって
気が付いてみると、子育て支援事業や新しい計画が全てキャンセルになっていました。でも赤ちゃんは生まれます。この時期にお産した人は面会謝絶で家族とも会えません。お母さんが手伝いに来てくれたり、里帰りお産もできなくなったと聞きました。そして退院後の母子訪問支援事業もキャンセル。乳児健診事業も延期。子育て広場も閉鎖。つまり
母体の回復や赤ちゃんの健康、発達指導がすべてなくなってしまったのです。
私はとても心配でした。
ママ達が家でどんな暮らしをしているか見えなくなりました。
これまで私達は仲間と共に母親目線で数々の子育て支援を実践してきました。そのたびに必要性を実感して行政に伝え、信用を得て、市の子育て支援事業にまで持って行きました。今年度からはさらに飛躍して、子育て世代包括支援センターとして産前産後からの支援を市と協働で始めるところまで来ました。やっとです。20年かかりました。
その支援事業は「ままぴよ日記
42と
43」に書いたように市内の開業医と助産師と子育て支援者、先輩ママが一堂に会して、産後すぐのママ達に寄り添って個別の相談に乗るというものです。そのために私達も協力団体として正式に会則を作り、近隣の産婦人科に協力要請をして準備してきました。それが一気にストップです。
でも、子育ては待ったなしです。
せめて何かできる事はないかと考えてオンライン相談に切り替える事を提案しました。市のオンライン状況は学校と同じでセキュリティが強すぎて全く使えません。それで個人のパソコンを使って対処することにしました。でも宣伝ができません。行政は市の広報やHPでお知らせをする方法しか知らないので2か月前には原稿にしておかなければいけません。
HPに載せてくださいとお願いしたら小さく載りました。あ~絶対に産後すぐのママは見ないなあ~と思いつつ、個人情報を貰えないので待つしかありません。
スタンバイしていましたが誰からも相談がありませんでした。結局2ヶ月相談なし。
» 続きはこちらから











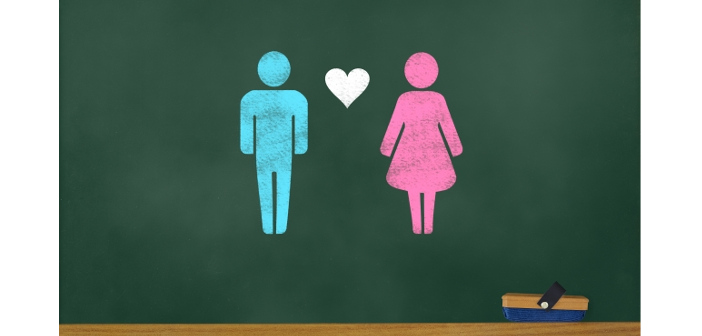










コロナの緊張の中、今度は一夜にして地形が変わるほどの豪雨です。我が町もレベル5にあたる大雨特別警報が出されました。奇しくも満月。近くの海が5メートルの高潮を迎える時間と重なっていました。
ヤバいです。ケータイはアラームが鳴り響き、激しい雨音が私の不安を煽ります。ヴァータの私はじっとしていられなくて行ったり来たり。
結局私がしたことは風呂に水をためて、二階に貴重品を運んで、猛スピードでご飯づくりです。そして避難リュックにマスクと消毒液、「癒しの光」「免疫・恒常性」「祝福の光」の写真とサーキュエッセンス和も新しく加えて、やっと一息。
そうそう、友人が「トイレが逆流した」と教えてくれたので、その対策も準備しました。
ただ、今回は避難するつもりはありませんでした。家ごと流される可能性は低いので避難所に行く方が危険だと思いました。避難準備をしただけで気持ちが落ち着きました。備蓄の食料品はあります。
あとは落ち着いて過ごすだけなので「ままぴよ日記53」を書き始めようと思ったのですが、やっぱり私の頭は大雨から離れられません。こりゃムリだと観念して今の自分の気持ちを書くことから始めます。
それにしても毎年毎年、災害で全てが無になる事を覚悟させられます。いったい、いつになったら落ち着くのでしょう。そうでなくても色々な問題が同時進行で発生しているので、最近は祈ることが増えました。
でも、祈ってばかりの自分にも疑問が出てきました。祈ることに疲れたり、あきらめが出てきたりしている自分が見えてきたのです。もしかしたら祈りと期待を混同している?そんな自分を反省しました。
そして、自分が純粋に願っていることがあったら、その意識で生きていけばいいと思いました。叶うかどうかはどうでもいいのです。だってもうそんな生き方をしているのですから。そう思ったら気持ちが楽になりました。
おりしも今日は7月7日。年に一度だけタナバタヒメコタエ様へ願いを託せる日です。今、お願い事を書いた短冊が雨風に踊っています。気持ちを届けただけで安心です。ありがとうございます。
さて、今回のテーマは「小1プロブレム」。でも、子どもの視点で考えたら「学校プロブレム」です。