————————————————————————

日本もドイツも一番がお好き
日本や日本人もよく、なんでも日本が一番!と特にバブル時代は、
『Japan as NO1』などもありましたし、思っている方も多いですが、
ドイツ語の先生によると、ドイツやドイツ人も、ドイツがなんでも
一番と言っていることが多いようです。
グーテンベルクが世界で一番最初に印刷を発明した・・とか、ツェッペリンが
世界で一番最初に飛行船を作ったとよく言われています。
しかしながら、世界で最初に印刷、文字を作成したのは、中国ですし、
世界で初めて飛行船を飛ばしたのは、フランスやハンガリー帝国時代の技術者らしく・・。

Wikimedia_Commons[Public Domain]
世界中でよくある歴史の内容が結構違うこともわかりますし、
なんでも一番になりたいと思う心や価値観が問題ですね。
野心をもってはいけない・・
竹下先生がいろいろなところで言われています。
『なぜ人間が注意深くないのかと言えば、自分の世界に埋没してしまって、ずっと考え事をしているからです。
なぜいつも考え事をしているかというと、欲があるからです。男性ならば、経営や営業のことばかり考えています。風呂に入っても仕事のことを考えています。四六時中、さまざまなことを考え、ずっと白昼夢を描いている状態で、周りのものに注意深くあれ、というのは無理なのです。』ぴ・よ・こ・と3 132ページより
上記の内容を普通の日本人の男性に説明しても
理解してもらえないような気がしています。
我が家の主人に言っても、たぶん意味がわからない・・
仕事のことを四六時中考えることが良いことであると
その価値観から外れることができない・・
その後に続く、ぴ・よ・こ・と3の猫のことを
言ったとしても、忙しい仕事生活の人に言っても
理解してもらえない内容のような気がしています。
『猫を見ていてごらんなさい。彼らは考え事をしていません。それが注意深いということなのです。
なぜ考え事をしていないのか。なぜ世界に正しく向きあえるのか。それは、欲望がないからなのです。』ぴ・よ・こ・と3 132ページより
» 続きはこちらから


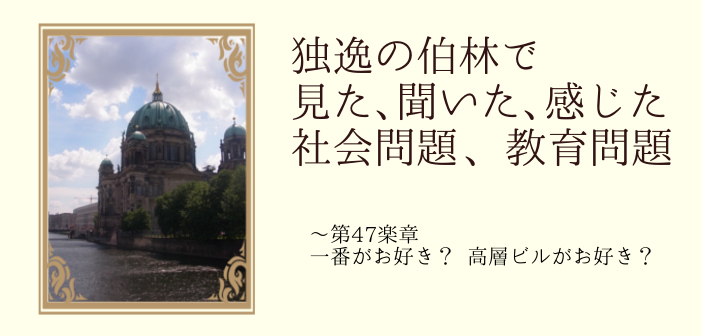



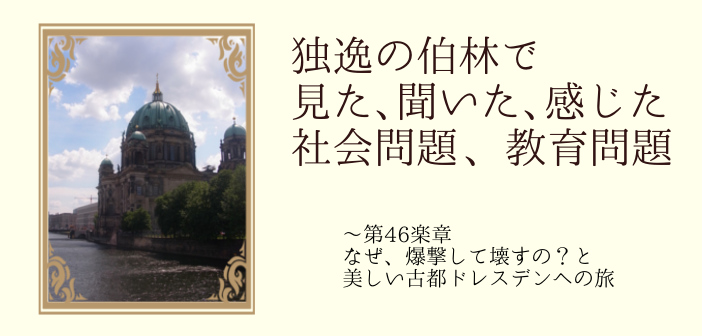

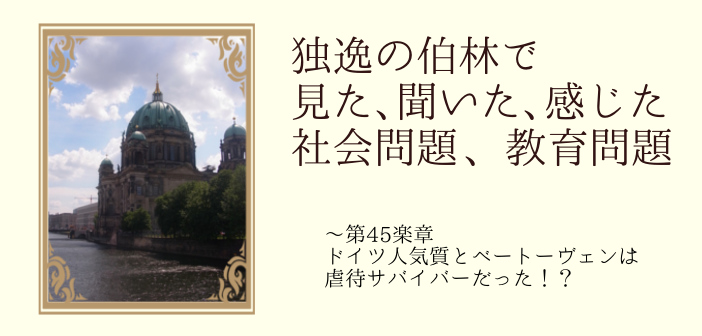


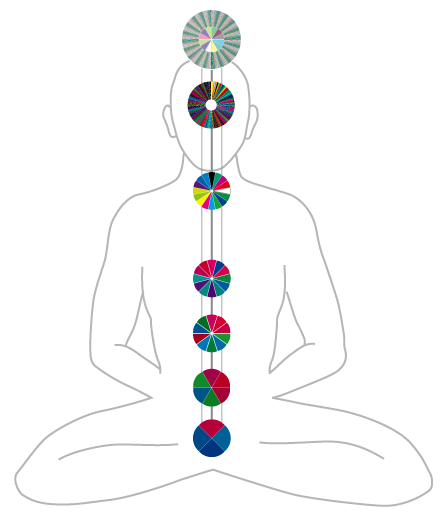
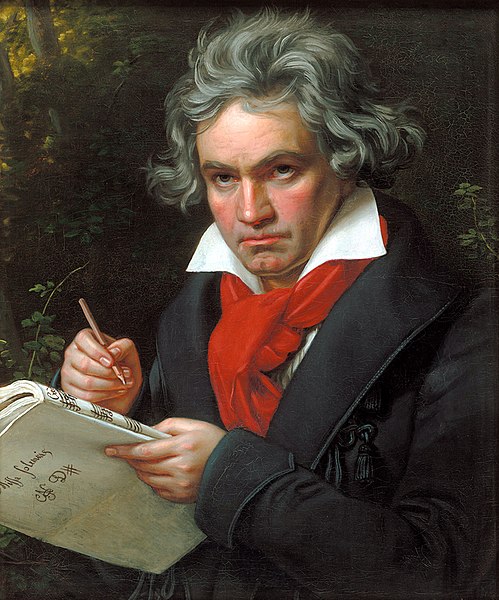

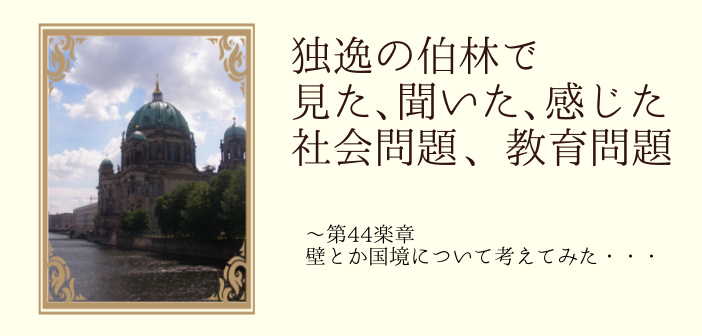



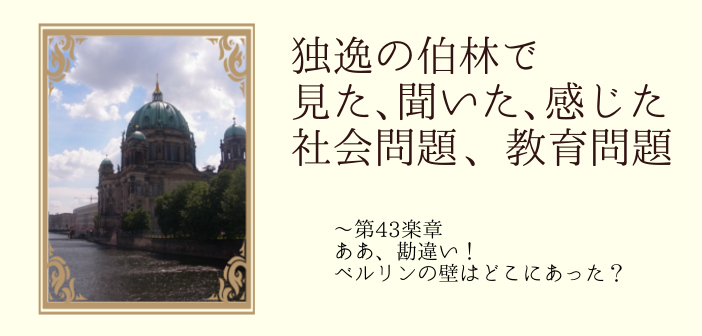


前年度の1989年11月9日にベルリンの壁が崩壊して、
1990年10月3日に東西ドイツが統一したのです。
しかし、ドイツ人にとっては、実際にベルリンの壁が崩壊した
1989年の11月9日こそが、ドイツ統一の記念日だとしたいようですが、
11月9日といえば、歴史を振り返っても多くの事件がありますので、
無難な10月3日にしたようなのです。
11月9日についてはこちらに以前書きました。
11月9日か・・9月11日にも似てるしね・・
あれ、3月11日にも関係がありそう・・
数字へのこだわりがお好きなようで・・。
9月11日は航空券も安いとか???
(アイ、ヤイ、ヤイ、ヤイ・・ドイツ人風に・・こちらの言葉は、日本語でいうと、あらま・・、あら大変!のニュアンスで使われます)
第47楽章は、一番がお好き? 高層ビルがお好き? です。