フルベッキは代々改宗ユダヤ人 〜グラバー、マセソン社との連動

ウィキペディア記事「
グイド・フルベッキ」では、ユダヤ人との表記はないですが、「
日本のユダヤ人」記事ではフルベッキの名前が出ています。他の情報と併せて見ても、フルベッキは“いわゆる”ユダヤ人だったのです。
そして「
グイド・フルベッキ」記事によると、
フルベッキの家系は代々改革派キリスト教徒だったとのこと。ようは
改宗ユダヤ、クリプト・ユダヤ人の家系です。
キリスト教に偽装改宗したサタニストメシアのヤコブ・フランクの一派、つまり、本人を含めフルベッキの家系は代々フランキストだったろうと見受けられます。
外伝31などで見解を示したように、
ヤコブ・フランクはサバタイ派7代目首長であったモーゼス・メンデルスゾーン、そしてロスチャイルド初代のマイヤー・アムシェルと同盟を組み、このシリーズでは
ヴァイシャ革命とよぶ世界革命を裏から推進していました。

ヴァイシャ革命:ヴァイシャ(商人)による「王政(クシャトリア)」と、主に「カソリック教会(ヴィプラ)」への破壊攻撃
フルベッキはイエズス会の別働隊のカルヴァン派であり、
同時にロスチャイルドを頭とするサバタイ-フランキストの一員と見て取れます。
1858年にイギリス東インド会社は解散し、その所有者たちは300人委員会へと移行するのですが、
300人委員会へ移行する東インド会社の支配的地位にあったのがロスチャイルド家でもありました。既に見たように、坂本龍馬や長州ファイブなど
維新の英傑たちのバックにはグラバーとマセソン社の存在があり、彼らの支配者がロスチャイルドであったのです。
フルベッキとグラバーやマセソンなどは皆が仲間だったと見るのが当然で、フルベッキとグラバーは連動して動いていたようにも思えます。フルベッキとグラバーは、共にそれぞれが1859年に上海を経由して日本の長崎に来て居住しているのです。
フルベッキに関しては「れんだいこ」さんの「
フルベッキ考」が参考になるのです。そこでは、フルベッキは非常に頭脳優秀な人物で、来日後に彼は長崎そして佐賀で教師を勤め、「語学(英、仏、蘭、独)のほか政治、天文、科学、築城、兵事の諸学を講じている」とあります。
この多方面に通じていた
フルベッキには多くの門下生と呼ぶべき人物群が集まっていたのです。
薩長土肥の後の明治新政府での高官となる人物たちです。(この中で
特にその高弟と言えそうなのが大隈重信と副島種臣です)。
フルベッキのこれら門下生と加えて、
公家側の重要人物岩倉具視もフルベッキの弟子的な立ち位置にあったのです。ウィキペディアの
フルベッキ記事では次のようあります。
「1868年6月にフルベッキは大隈重信に、日本の近代化についての進言(ブリーフ・スケッチ)を行った。それを大隈が翻訳し、岩倉具視に見せたところ、1871年11月に欧米視察のために使節団を派遣することになった(
岩倉使節団)。直前までフルベッキが岩倉に助言を与えていた。」
だと言うことです。ここから見えるのは、明治新政府の高官ほぼ全てがフルベッキはの弟子的な形で関連があったことです。
» 続きはこちらから

















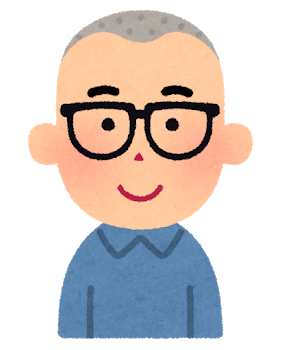











わたし自身、京アニの作品にどれだけ背中を押され、励まされたかわかりません。
そんな傑作を、世に出してきた人たちが大勢、犠牲になりました。
京アニのアニメを楽しみに待つ世界中のファンも、どん底に突き落とされました。
でも今、世界に散らばる私たちファンが、京アニを支える番だと思います。