注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

【悲報】日本の相対的貧困率、米韓にも抜かれ先進国最悪に(OECD38ヶ国で最下位)#自民党公明党に投票するからこうなる #選挙に行かないからこうなる #政治は生活https://t.co/QqSQdtIZIH
— 桃太郎+ (@momotro018) July 13, 2023
貧困化政策を進めてきたのだから当然の結果。更に増税しようというもはや虐待国家。
— 舞小海@後退国へまっしぐら (@kufuidamema) July 13, 2023
>日本よりも貧困率が高いのは、メキシコ、ルーマニア、コスタリカなどを残すのみとなった
少なくとも現時点の最新値において、日本の貧困率が先進国で最悪であることが確定したのである https://t.co/MS3soBY7Su
【悲報】日本の相対的貧困率、米韓にも抜かれ先進国最悪に(OECD38ヶ国で最下位)#自民党公明党に投票するからこうなる #選挙に行かないからこうなる #政治は生活https://t.co/QqSQdtIZIH
— 桃太郎+ (@momotro018) July 13, 2023貧困化政策を進めてきたのだから当然の結果。更に増税しようというもはや虐待国家。
— 舞小海@後退国へまっしぐら (@kufuidamema) July 13, 2023
>日本よりも貧困率が高いのは、メキシコ、ルーマニア、コスタリカなどを残すのみとなった
少なくとも現時点の最新値において、日本の貧困率が先進国で最悪であることが確定したのである https://t.co/MS3soBY7Su【リツイート拡散希望】
— ニシさん【日本を愛する仲間たち】 (@nishisan359668) July 12, 2023
政治に無関心の国民が、このような事態を招きました。一億総貧困化です。家族や知人、友人に下記画像を送りつけましょう😊 pic.twitter.com/ImiyckCwSb
日本は、国連の最貧国に認定されました。 pic.twitter.com/Gx67AUwhBP
— (れいわ支持)政権交代を目指す、自公維は嫌いです (@yW7z8f1qjLrmqBl) May 2, 2023
そう言えば先日スーパーで、半額弁当を妻と自分の分で2つカゴに入れてたら、自分のカゴに手を入れてくるお爺さんがいてギョッとしたのだけれど、「どちらか譲ってくれよ!」と真剣な顔で言うので、どうぞ、と一つ渡したのだけれど、いよいよ日本もこんな感じなのだな。
— KAI (@KAIcycloid) July 12, 2023
(中略)
なお、先の木下論文では、米国では月次で貧困率の推移を追っていることが紹介されている(p.57)。韓国も、毎年、貧困率を公表している。
これに対して、日本の貧困率が更新されるのは、現状のままでは3年後になる。数字の根拠となる国民生活基礎調査が、3年に1度しか実施されないからである。
(中略)
国際比較をするための基礎データを算出することもなく、月次どころか経年でのデータ収集さえ行わない。企業経営や税制の議論をする際に同様の対応をしたら関係者はそっぽを向くだろう。
国民生活基礎調査の過年度データに遡ってOECDの基準で貧困率を算定し直すことは、今すぐにもできるだろう。毎年度のデータを出すことも、他の国ができて日本ができない理由はない。
(中略)
骨太の方針で触れられているのは、「こどもの」という形容詞のついた貧困解消の取組でしかない。そこでは、「大人の」貧困はないものとされている。
(以下略)


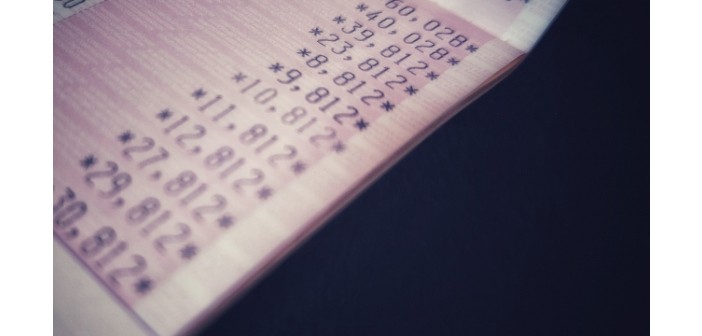




![子ども関連予算を来年に先送りの岸田政権は、物価高騰で困窮する子育て世帯を救わない / [ゆるねとにゅーす] 今の日本政府やマスコミは意図的に国民を”間引き”](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2022/12/m1229.jpg)


 どんなにゅーす?
どんなにゅーす? 






恐ろしいのは、日本が貧困率の把握に熱心ではないことです。アメリカは毎月、韓国は毎年、データを算出し貧困率を追っているそうです。ところが日本は3年に1度しか調査をしないので、次回の3年後まで貧困状態の推移がつかめないというのです。各国が当然のように算出してることを日本ができない理由はないと言います。だとすると、日本はあえて数字を出さないのでしょうか。
政府の骨太の方針で「貧困」のワードが出てくるのは、「こども」の貧困解消への取り組みだけで、それも「自助」「共助」の方針ばかり。「大人の貧困」についてはまともに取り上げていないばかりか、"政府の責任を示す「公助」の言葉はどこにもない"とありました。岸田政権は日本の貧困の現実を知らせず、貧困解消への努力もしないばかりか、増税に次ぐ増税で国民の貧困をさらに生み出そうとしています。
日本の貧困は、政府・自民党政権が生み出していることは確かです。