————————————————————————

垣根を越えた現場での支援者のネットワーク作り
ちょうど一年前、私達子育て支援者と現役ママ達が一緒になって老朽化した子育て広場の存続(もしくは建て替え)と、お産直後からの子育て支援の必要性を市長に話に行きました。そのことはままぴよ日記の20と21に詳しく書きましたが、今回はその続編になります。
その結果は「これからも協議していきましょう」という事でした。でもこれは積極的に動かないという意味だと受け取りました。市は財政難で、既存の事業も見直されている状態です。これでは「子どもは宝、子育て支援は市の柱!」と言いながら何の支援策も取られないまま時が過ぎていきます。
思い返せば13年前、現場の支援者のネットワークを作って試行錯誤しながら子育て広場を作りました。その後ママのための親育ちセミナー、中学生とのふれあい広場、多胎児を持つママが集う日、助産師や小児科医の相談日、外遊びのプレーパーク等も全て、自分たちで学び、企画してきました。もちろんそのたびに効果を報告して市の予算を取り付けてきました。目的はこれらの支援を市の事業にして、全ての親子に無料で届けたかったからです。

Author:倉田哲郎[CC BY]
これは書いてしまえば5行くらいの話ですが、それに至るまでは何度も壁にぶつかり、無力感に襲われました。でも、目の前に必死で子育てをしているママ達が居たからやめられませんでした。そして一緒に支え合う仲間がいたからやってこられました。
困った親子に寄り添う支援
ところが、親子の置かれた環境は深刻さを増すばかり。親はますます孤立無援化していき、「国のために働きに行きましょう。保育園を増設します」という子離れ支援が行われています。
2016年のデータですが、産後鬱もしくは産後鬱の一歩手前だったという母親が80%を超えている事や、周産期死亡より母親の自殺が大きく上回ったことが衝撃でした。自殺のピークは産後4か月。これは産院を退院してから4か月健診まで何も支援がないことからもうかがえます。
赤ちゃんが生まれて幸せなはずなのに「涙が止まらない」「眠れない」「何もしたくない」「こんな私が育てるより専門家に育ててほしい」というママを何人も見てきました。そこまで酷くなったら「相談窓口があるよ」「私達の広場においでよ」と誘っても来てくれません。
» 続きはこちらから






![[YouTube]育休を取った小泉進次郎に一言](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2020/01/m127.jpg)




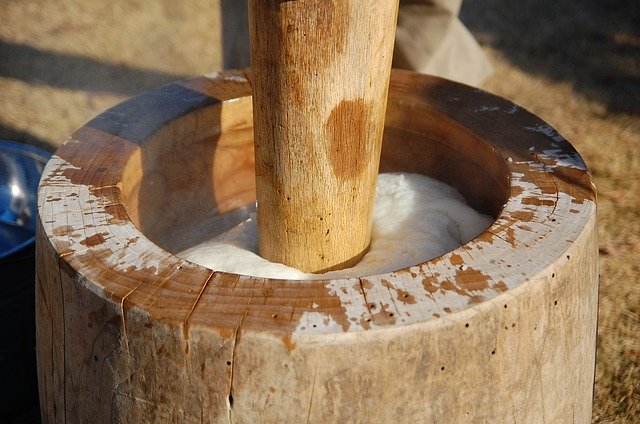

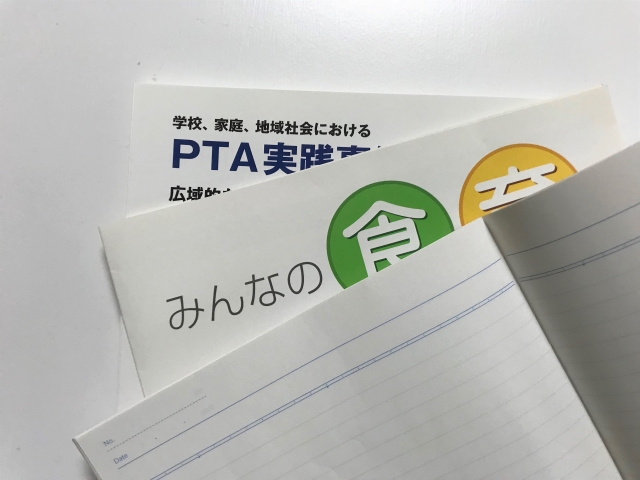








私は人口6万くらいの市に住んでいますが、その町で子育て支援の大きなうねりが来ています。もう私達の手を離れて神様が働いてくださっているのではないかと感じるほどです。
でも、実際に動くのは私達。どんな時もめげずに良心と共に働いていたら・・・このうねりが突然やって来たのです。
もう一方で、コロナウイルス、娘が直面しているオーストラリアの火災、経済崩壊、地震の気配…世界中を巻き込む負のうねりが来ています。
状況は悪化するばかりで私達個人では成すすべもないように見えますが、こんな時こそできる事に集中するしかありません。
そうです。こんなことが起ころうが起こるまいが・・・できる事は1つ。自分の良心に従って目の前の事に愛を体現して生きて行く事。2月のカレンダーの言葉の通り、どんな時も自分が幸せでいる事だと思いました。それが出来ていなかったら今こそが生き方を変えるチャンスです。
子ども達、孫達、すべての子ども達の顔が浮かんで不安になる時はガヤトリー・マントラと「愛しています。愛しています・・・」と唱えて冷静になります。そして私の手の届かないことは神様に祈ろうと思います。生活の中で真剣に祈る時間が増えました。
さあ!今回からは、我が町の子育て支援が私達の提案によってどう変わっていくのか?そのうねりと共に実況中継をしていきたいと思います。