正しい食品表示を求める裁判https://t.co/i9M8QmU2dH
— Ishigaki (@kazu1234510) September 17, 2025
食品表示問題の裁判の
— 1de9 (@1de91941) October 11, 2025
準備をしています!
裁判にご賛同いただける方は是非ご登録ください。
9 pic.twitter.com/THoDk25WPt
![[山田正彦氏] いよいよ「正しい食品表示」を求める裁判を起こすことに 〜 残留農薬の不安のない国産小麦や国産菜種の表示を求めるため「一人でも多くの人に委任状を送ってほしい」](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2025/10/m1017.jpg)
正しい食品表示を求める裁判https://t.co/i9M8QmU2dH
— Ishigaki (@kazu1234510) September 17, 2025
食品表示問題の裁判の
— 1de9 (@1de91941) October 11, 2025
準備をしています!
裁判にご賛同いただける方は是非ご登録ください。
9 pic.twitter.com/THoDk25WPt
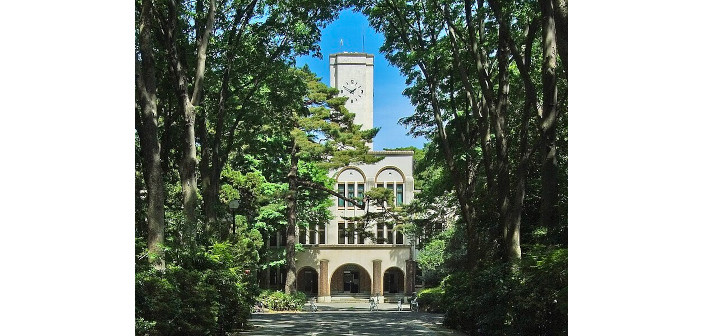
狙った害虫だけ退治「RNA農薬」https://t.co/A8owLVaE3L
— 日本経済新聞 電子版(日経電子版) (@nikkei) April 4, 2025
東京農工大学は野菜や果樹の害虫を食べてくれる、益虫ダニの食欲を増す技術を開発。益虫のエサとしての実用化をめざします。 pic.twitter.com/b8vdsmnqr8
味の素、RNA農薬の量産系を確立、事業化へ農薬企業との連携を模索 https://t.co/GpfhBIJ4vb
— 有機農業ニュースクリップ (@OrganicNewsClip) April 5, 2023
2021年5月21日に農林水産省が作成した「みどりの食料システム戦略」がヤバい…
— 食の未来を本気で考える一般人 (@Syoku_no_mirai) January 13, 2024
この政策により有機・オーガニック農業、化学農薬・化学肥料の削減などが推進されているが、その裏で “RNA農薬” の開発が進んでいるのは怖すぎる。
オーガニックの食品は増えるかもしれないが、その代償は高くつくだろう。 pic.twitter.com/LFX79eBZTr
RNA農薬とは農薬に仕込まれたRNA遺伝子が害虫のRNA遺伝子に干渉し、その働きを停止させることで細胞死を誘発し、害虫を駆除するというものです。
— 食の未来を本気で考える一般人 (@Syoku_no_mirai) January 13, 2024
従来の農薬とは違い特定の害虫のみを駆除することが可能となります。
![[ナカムラクリニック] 製粉会社に勤める男性「小麦が体にいいはずありませんよ」「これだけの毒物をしみこませた小麦を食べて、病気にならないとしたら不思議です」](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2025/02/m213.jpg)
注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

農薬も危険だけど、穀物を収穫した後、殺虫剤(臭化メチル、リン化アルミなど)で燻蒸する。あれは相当危険。
— ナカムラクリニック (@nakamuraclinic8) February 11, 2025
現役の製粉所社員が「これだけの毒物をしみこませた小麦を食べて、病気にならないほうが不思議です」と。https://t.co/j9JpB4mp3n pic.twitter.com/e0HuxddsC6
✿製粉所職員「小麦は食べません」2025/02/12https://t.co/R4c49NZpPV
— MountainLake (@Mt_Lake2020) February 12, 2025
>必須燻蒸過程:充満臭化メチルで小麦に付いた虫をкороす
>仕入れ小麦:不純物(殺虫剤+除草剤+殺虫剤+虫+妙な異物)大量含有
→袋に虫を入れるとсиぬ
→人間が発病しないのは不思議
→全粒粉/胚芽入り絶対食べては駄目
😡 pic.twitter.com/SQbPMlngdv
![[山田正彦氏]日本での発達障害児急増は「危険な農薬残留が原因だった」 ~オーガニックのものだけを4週間食べさせると、自閉症の子供の症状が劇的に改善 / ロバート・F・ケネディ・ジュニア「5Gに関して私が懸念しているのは、5GのRF放射線が危険だということです。血液脳関門を透過し、破壊します」](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2024/11/1118.jpg)

【農林水産省がガン無視する日本人科学者達】
— うた桜子🌸流山市議会議員 (@rocio0825) November 7, 2024
皮肉にもヨーロッパでは日本人の論文が考慮されネオニコ規制をしている。
農林水産省や消費者庁に問い合わせても、のらりくらりの回答しかない。そこまで農薬を売るグローバル大手企業に忖度しないといけないならば、、、… pic.twitter.com/wfpcJpNpMa
まずは需要がないという状況を作らないと規制しようと動かなないかも知れません。農林水産省も消費者庁も今気付いている人の数では、まだ甘く見られていて意見書出しても声を上げても全く対応しようとしていないので💦。周りに知恵をつけて高くても国産無農薬ばかり売れる状況にしていく必要がありそう…
— うた桜子🌸流山市議会議員 (@rocio0825) November 8, 2024
「食品表示法」では全ての食品に原料原産地の表示が義務付けられていますが、その法律の下にある施行規則では国会の審議も通さずに"マイナーチェンジ"して「国産」の表示ができないようにされました。消費者庁は「"非遺伝子組み換え大豆"と表示された商品に、一粒でも遺伝子組み換え大豆が混入していたら厳罰に処します。」という姿勢で、明らかな国産品でも「国内製造」とするよう企業に指導、というか強迫しているそうです。「消費者庁は、消費者のためではなく、大企業のために産地を不明にする、食品の内容を分からなくすることに加担している。」深田萌絵氏は「大企業と中小企業の違いというのは、大企業は大量生産して、コストを下げて、添加物を入れても安く均質なものを作れるというスケールメリットを取りに行く。でも中小企業は、お客様それぞれの嗜好に合ったものを細やかに作るビジネスをしている。その中小企業を潰そうとしている。」と指摘しています。
求める食品が輸入した原料で国内製造したものであった場合、残留農薬が不安です。今の残留農薬は「浸透性農薬」と言って「水に漬けて洗っても煮ても焼いても消えない」「全部体に入ってくる」そうです。
農薬の散布量の増加と発達障害児の増加が相関している実態があり、20年前は4000人しかいなかった発達障害児が今は20万人もいて、支援学級が不足する事態になっている現実から、国民は安全な国産の食品を強く求めています。
「食品表示問題をどうやって解決していきましょうか?」との問いに、山田正彦先生は、いよいよ「正しい食品表示を求める裁判」を起こそうと話されました。国民の知る権利を侵害し、小さな企業の営業の自由を不当に侵害し、生存権すら脅かしている今の行政に対して、「表示が適正でないため一般消費者の利益が害されているとして適正な措置を求める『申出』の手続きをとることになりました。現在申出人になっていただける方を募集しています。」とのことです。8名の弁護士団で、パンや食用菜種油の表示に小麦や菜種の原産地を表示することを求めています。動画最後のQRコードから、あるいはこちらのサイトのダウンロードボタンで、お願い文書や委任状をプリントアウトすることもできます。「一人でも多い方がいい」そうです。「自分の名前と認印、そして捨印を押して送付」して応援しよう。