※全文はツイッターをクリックしてご覧ください富の移転が起こされる。寡頭政治家をボイコットし、地域で経済的レジリエンスを育め。
— ShortShort News (@ShortShort_News) August 7, 2025
─陰謀事実ジャーナリスト ホイットニー・ウェッブ
"赤チームか青チームに投票することにばかり時間を使っていたら、彼らの支配から抜け出すようなことは何もできません。… https://t.co/QsEUEAMa1b pic.twitter.com/IEFAyBGM7A
※全文はツイッターをクリックしてご覧ください書籍『地域通貨、地域感覚:ウォール街からメインストリートへお金をシフトし、真の繁栄を実現する方法』
— Alzhacker (@Alzhacker) August 7, 2025
~98%の人が知らない地域投資という新常識
退職金の運用で「株式なら年8-12%は稼げる」と言われてきたが、これは完全なウソだった。実際のS&P500の140年間の平均リターンは… pic.twitter.com/v5HYcHRZoa
» 続きはこちらから


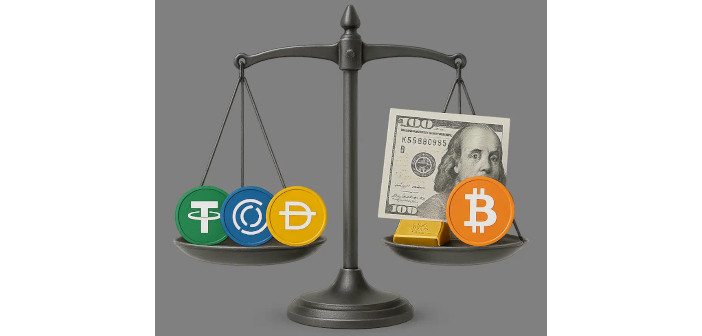





![[被曝80年 広島の平和記念式典] 石破茂首相と湯崎英彦知事のあいさつが話題に 〜 核抑止は有効か?「自信過剰な指導者の出現、突出したエゴ、高揚した民衆の圧力。あるいは誤解や錯誤により抑止は破られてきました」](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2025/08/m807.jpg)


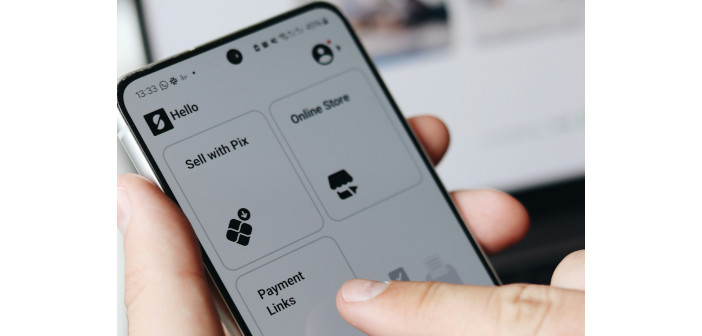





それはともかくホワイティー、いや、ホイットニー・ウェッブ氏は富の移転が繰り返し起こっており、“彼らが仕組んで作り出す危機があって、そして、政府の対応は一般市民のお金を取ることです。そして、それはまた起こる可能性が高い。(30秒)”と話し、ステーブルコイン法が議会を通過したことを指摘しています。
“デジタル・ドルになるでしょう。ステーブルコインはCBDC(中央銀行デジタル通貨)よりマシだと思うかもしれませんが、同じぐらい悪いです。特にCBDCで心配なのは、プログラマビリティ、監視性、差し押さえの可能性です。(46秒)”と言っています。
ホイットニー・ウェッブ氏は、銀行王朝が創設した連邦準備制度は、彼らと政府の間の仲介役だった(1分50秒)ことを指摘し、“今、行われていることは、その仲介役を取り除くことです。だから、富の移転の動きに備えてください。トランプが銀行家の計画を促進しないと思うなら、トランプの歴史、あるいは彼の政権がコロナ中にやった金融政策、「Going Direct Reset」について調べてみることをお勧めします。(2分)”と言っています。
一般市民はこれらの人々に力を与えるのをやめるべきであり、同時に、“経済的な回復力を築くことはとても重要で、それは地方レベルで実現できる(3分15秒)”と言っています。
具体的には、Alzhacker氏のツイート『地域通貨、地域感覚:ウォール街からメインストリートへお金をシフトし、真の繁栄を実現する方法』をご覧ください。
“投資の専門家は「株式市場に長期投資すれば年8-12%のリターンが期待できる」と説明するが、実際には、1871年から2010年までのS&P500の年平均リターンは、配当込み・インフレ調整済みで2.6%に過ぎない。一方、あなたの近所にある地元企業への投資なら年5-8%のリターンが現実的だ。しかも地域経済も活性化する。”と言うのです。
“成功の秘訣は「地産地消」であり、日本でも同様の動きが始まっている。各地の信用金庫や農協は地域密着型の融資を続けている。大型店舗チェーンでの買い物を控え、地元商店街を利用する。メガバンクから地域金融機関に預金を移す。全国チェーンのコーヒー店ではなく、個人経営の喫茶店を選ぶ。こうした小さな選択の積み重ねが、地域経済を活性化し、最終的に自分たちの暮らしを豊かにする。”とあります。私たちが目指す道は、こちらの方向です。
蛇足ですが、“続きはこちらから”の動画でキンバリー・ゴーグエンさんは、CBDCの実現の可能性がないことをあらためて説明しています。11分15秒から12分のところをご覧ください。