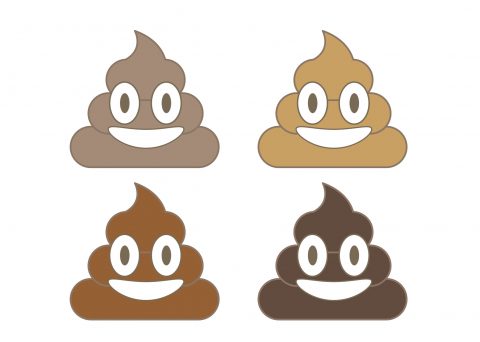かんなままさんの執筆記事第11弾です。
————————————————————————

独立要求
独立の要求を満たすためにも、子どもを好きなように遊ばせてください。遊ぶことは子どものエネルギーを発散させるために非常に重要です。
これを押さえつけると、子どもが余計に騒ぐようになります。
遊びたいエネルギーが鬱滞すると内向状態になります。弱い子をいじめる、虫を殺す、というように陰鬱になります。また、親に対してすぐに反抗する子どもになっていきます。
これを押さえつけると、子どもが余計に騒ぐようになります。
遊びたいエネルギーが鬱滞すると内向状態になります。弱い子をいじめる、虫を殺す、というように陰鬱になります。また、親に対してすぐに反抗する子どもになっていきます。
出典:「ぴ・よ・こ・と」竹下雅敏(著)
子どもは好奇心の塊です。衝動にも似た、湧き出るエネルギーのままチャレンジして、失敗して、又チャレンジして、達成感を味わい、独立要求を満たしていくのです。かつては子どもの生活空間に自由に遊べる場があり、時間も、仲間も、見守る地域の目もあったので、子ども達は生活の全てを遊びとして、エネルギーを発散させ、自立、成長していけたのです。
でも、こんな遊びは、当たり前すぎて、その重要性が認識されていませんでした。そして、経済成長とともに、子どもの生育環境が変わってしまいました。自然の中で自由に遊ぶ場所が激減して、公園も、学校の校庭でさえ自由に遊べなくなりました。住環境もしかり。子どもの声、足音が迷惑とされ、親は子ども達が家で騒がないように気を使います。
さらに、メディアが子どもの生活に入ってきてからは遊びの質も変わりました。身・心・気をフルに連動させてまるごと体験して遊んでいたものがプログラムされた表面的な刺激、反応だけの遊びに取り込まれてしまったのです。これでは生理的に湧き上がるエネルギーも、自発のやる気も鬱滞して、独立要求も満たされません。逆に、満たされないエネルギーが陰欝、反抗、キレる原因になってしまいます。
満たされない子供達の愛情要求と独立要求
追い打ちをかけるように、子どもの教育費を稼ぐためにママ達は早くから仕事に復帰して忙しく、子どもの愛情要求を満たすことができません。子ども達は1歳未満からの集団生活で相当我慢しています。言葉にならないストレスがママの顔を見たら噴出して来ます。無理難題な事を言って、暴れて、忙しいママを困らせます。又、怒られます。・・・子どもの叫びが聞こえてきそうです。
その上、幼稚園、放課後に英会話、お絵かき、水泳、バレエ、スポーツ教室、ピアノと、おけいこ事が人気です。
親は子どもの才能を伸ばすことがいいことだと勘違いをしています。「子どもがピアノを習いたい」と言うのはご用心。自由に弾きたいだけです。習い始めたら一番満たしたかった自由な表現が奪われます。やめると言うと、努力が足りないと叱られます。本来は自分がしたいから頑張れるものなのに、させられてもっと嫌いになります。でも、ママから嫌われたくないから頑張ります。これも相当ストレスが溜まります。
これらの問題は深刻で、親の責任というより、子育てのまなざしを忘れた社会の責任です。
ある意味、親は子どもの幸せのために、孤立しながらも一生懸命頑張っています。でも、子どもの成長に欠かせない「自分が主役、自発、自由」がすっぽり抜け落ちているのです。
どうぞ、惑わされないでください!目の前の子どもの姿に気づいてください。元気ですか?波動は高いですか?満ちてますか?それがいちばん重要な事です。
前回、孫がイライラすることを書きました。独立要求で、自分との葛藤でもあると書きましたが、今の子ども達のエネルギーの鬱滞はそれだけでは解決できないくらい深刻です。自分を発揮できずにキレる子があまりにも多すぎます。(孫達にはゲーム機もスマホもさせていません)
子どもの姿をよく見て、気づいてください。
異常な甘えや怒りの状態が続いていたらSOSです。問題を持ち越せば年齢が上がるほど、もっと深刻になるのを見てきました。何を大事に子育てするのか、どうぞ夫婦で話し合ってください。
そして、子どもの遊びをもっと見直す必要があります。
» 続きはこちらから