![[キシキンTV] 過去の江藤大臣の発言から見える食糧の売国政策「日本人が一生懸命作った食糧は海外の富裕層向け、海外産の農薬まみれの食糧は多くの日本人向け」自・公・維新の既定路線](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2025/05/m523-0.jpg)
アーカイブ: 食
![[キシキンTV] 過去の江藤大臣の発言から見える食糧の売国政策「日本人が一生懸命作った食糧は海外の富裕層向け、海外産の農薬まみれの食糧は多くの日本人向け」自・公・維新の既定路線](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2025/05/m523-0.jpg)

米不足だけではない、日本の食を支えてきた「出汁文化が静かに確実に追い詰められている」〜 主食の米を守り、和食材の担い手を守る政策を早急に
そんな時に、この動画を観ました。「品薄・高騰確実!日本で買えなくなる!? 消える食品7選」というショッキングなタイトルです。
最初が「バターと牛乳」でした。これは日本の酪農家さんの苦境を考えると当然の予測と言えます。この10年で酪農家の数は半分以下に減り、その多くの方が高齢で後継がいない状況です。続いて出たのが「昆布、煮干し、鰹節」でした。原因は海の環境悪化のようです。漁獲が減っている上に技術を持った加工業者の方が高齢化して廃業するケースが増えているそうです。「日本の出汁文化が静かに確実に追い詰められている状況」との解説には愕然としました。
「はちみつ」も危機的で、粗悪な輸入品が増えることが予想されていました。シャンティ・フーラのハチミツは大丈夫。
まさかと思ったのは「緑茶、抹茶」で、ここでも茶畑の減少と生産者の高齢化、後継者不足が原因でした。海外の需要の高まりで「良いものは海外へ、日本には残り物みたいな状況」になる可能性も指摘されていました。
当面の備蓄は各家庭のニーズに合わせて検討するとしても、根本的な解決に必要なのは日本政府の政策だと思いました。
「令和の百姓一揆」では、早急に農家の所得保障をして、米農家さんを守る必要があることが示されました。まずは日本のお米をしっかり守り、さらに日本の食卓を脇で支えてきた食材の担い手も守る政治に変えて、みんなで美味しい和食を囲みたいものです。
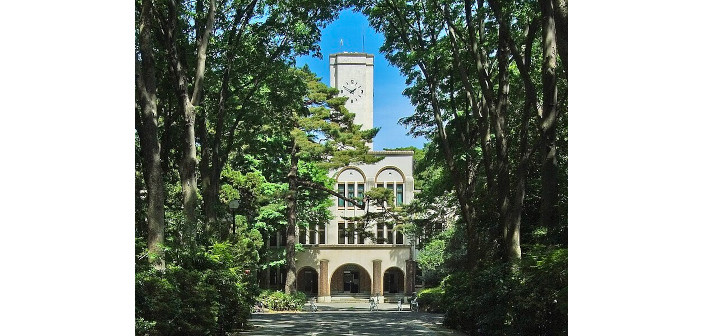
農工大が「狙った害虫だけを退治する」RNA農薬を開発 / 生態系への危険を訴える高橋ひであき氏は政治団体「無所属連合」から立候補を表明
2021年に農水省の「みどりの食料システム戦略」が発表され、中に「RNA農薬」の開発を進めるとありました。「RNA農薬とは農薬に仕込まれたRNA遺伝子が害虫のRNA遺伝子に干渉し、その働きを停止させることで細胞死を誘発し、害虫を駆除するというものです。 従来の農薬とは違い特定の害虫のみを駆除することが可能となります。」農工大のRNA農薬は「農地にまいた後に分解されやすい」とありますが本当でしょうか。新型コロナワクチンのmRNAは分解されるはずでしたが接種後半年経ってもスパイクタンパクの検出が報告されています。
この情報を検索していると、うむ農園のお兄さんが動画で解説されているのを見つけました。うつみさとる氏と大西つねき氏が立ち上げた政治団体「無所属連合」の新たな候補者・高橋ひであき氏として語っておられました。
7:19からは、農家として「平野部の集約された大規模農業ではなく、日本の多くを占める中山間地の農業が日本にとって大事だと考えている。」「土着的な日本の気候風土から自然発生していく人間関係は合議体でもあり、日本の精神性に良いものを残す。その村のあり方と無所属連合のあり方が重なって可能性を感じた」そうです。
17:53からは、日経で報じられたRNA農薬について語っています。味の素がRNA農薬に参入してきたことにも触れています。「これを自然界に解き放ってしまうと何が起きるかわからないことが問題」「微生物に仕込むのでいつまでも自然界に残ってしまいかねない。」「生態系をものすごく壊すだろうなと。」他に稲の改良については「ゲノム編集には規制がないので、交配させた交配種としてゲノム編集の稲を売るということが起こっている。」「自然種とゲノム編集の交配は絶対見抜けない。」「僕ら農家が品種を選ぶときに、交配種の元を辿るとゲノム編集があったとしても開示されていないと分からない。」「農家が消費者に悪いものを出したくないと思っても、その意思決定を飛び越えて、悪いことに加担させられてしまうことが今後起きてくるかもしれない。農家には止められないところまで来てしまった。」と警戒されています。
24:54からは、大西つねき氏がこの問題には「人間の命、人間の経済のためだったら何をしてもいい」という思想があると語っています。「自分たちのエゴを振り回して浅知恵を使って、人間だけが生き延びようとか長生きしようとか」「食の安全とか安心とかを考える以前に、エゴイスティックすぎる」「自然に生きて自然に死ぬということを普通のことにしておきたい」と述べています。
狙った害虫だけ退治「RNA農薬」https://t.co/A8owLVaE3L
— 日本経済新聞 電子版(日経電子版) (@nikkei) April 4, 2025
東京農工大学は野菜や果樹の害虫を食べてくれる、益虫ダニの食欲を増す技術を開発。益虫のエサとしての実用化をめざします。 pic.twitter.com/b8vdsmnqr8
味の素、RNA農薬の量産系を確立、事業化へ農薬企業との連携を模索 https://t.co/GpfhBIJ4vb
— 有機農業ニュースクリップ (@OrganicNewsClip) April 5, 2023
2021年5月21日に農林水産省が作成した「みどりの食料システム戦略」がヤバい…
— 食の未来を本気で考える一般人 (@Syoku_no_mirai) January 13, 2024
この政策により有機・オーガニック農業、化学農薬・化学肥料の削減などが推進されているが、その裏で “RNA農薬” の開発が進んでいるのは怖すぎる。
オーガニックの食品は増えるかもしれないが、その代償は高くつくだろう。 pic.twitter.com/LFX79eBZTr
RNA農薬とは農薬に仕込まれたRNA遺伝子が害虫のRNA遺伝子に干渉し、その働きを停止させることで細胞死を誘発し、害虫を駆除するというものです。
— 食の未来を本気で考える一般人 (@Syoku_no_mirai) January 13, 2024
従来の農薬とは違い特定の害虫のみを駆除することが可能となります。
» 続きはこちらから
「令和の百姓一揆」予想を超える参加者と沿道の熱い声援 / 食と農の危機を打開するのは「怒り」ではなく「希望」への共感、各地の農を守る共感の輪を広げよう
報道ではニューヨークタイムズが大きく報道し、日本は朝日、産経、日経、東京、共同通信が報じたそうです。国民から受信料を取るNHKはスルーだったらしい。
東京以外にも、大分、福岡、熊本、静岡、滋賀、岐阜、奈良、大牟田、山口、富山、沖縄からの熱い報告が届いています。
我那覇真子氏がスタートからずっとライブ配信をされていましたが、デモの後に行われた「次に向けた寄り合い」も伝えて下さいました。その中で「令和の百姓一揆」実行委員会の菅野芳秀代表の言葉が印象的でした。
『対決軸では物事は解決しない、人々の共感を得られず敵を強くするだけだ。共感力が人々の輪を広げる。その共感力は「希望」だ。
食と農という命の危機は未来の危機に繋がっている。それを打開する道は怒りではない、怒りは長く続かない。私たちは何年もかけて食と農の関係を根付かせながら大きくしていかなければならない。食と農の関係から社会を変える、人間関係を変える、農のあり方を変える、その共感を生むのは希望だ。希望を運動の柱にしていく、政策にしていく。喜びこそ共感を広げていく。これからその共感を地域に中で生かしていくことが大事だ。(最後のX投稿 23:00〜)』
また、一揆に駆けつけておられた鈴木宣弘先生は「日本の農業はあと5年が正念場、今止めなければ日本の農と食と命の危機は一気に加速しかねない」「世界で最も競争にさらされながらも、ここまで踏ん張ってきた日本の農家のみなさん、凄いですよ。本当に精鋭です。この踏ん張りこそが子供達の未来を守る希望の光です。(中略)令和の百姓一揆に参加しまして、大きな希望が見えてきました。子供達に明るい未来を残せるように一緒にがんばりましょう。」と激励されました。
【御礼】ご参加いただいた皆さま、本当にありがとうございました!お疲れさまでした!⁰東京では多くの方がお集まりくださり沿道からも想像以上のあたたかい声援をいただきました。その数、4500名!!🚜🚜🚜🚶♀️🚶♀️🚶♂️🚶
— 令和の百姓一揆実行委員会 (@hyakushoikki08) March 30, 2025
ただいま #令和の百姓一揆 が10万ポストでトレンド入り🎉 pic.twitter.com/KgrLQIewKo
人の行進も始まりました!
— トム⭐︎かりん (@JUNJI_Tom_Karin) March 30, 2025
すげーパワーだ!#令和の百姓一揆 #日本消滅を止めろ #今こそ日本人団結の時 pic.twitter.com/gzDpoDe8rz
» 続きはこちらから

「種子法廃止違憲訴訟」東京高裁は「棄却」の判決 〜 “グローバリゼーションの破壊の壁は極めて厚いが、食を守る個々の権利を主張する歩みは止められない”、上告へ
田井勝弁護士から(10:53)「いかに不当判決だったか」の説明がありました。ミツヒカリ不正問題、昨年来の米の供給不足問題は、政府の言う「日本には優れた民間品種がある+コメの供給不足はない」という種子法廃止の根拠を覆す事態であるにも関わらず、高裁は判断することを逃げています。
岩月浩二弁護士からは(30:15)「予想はされたがここまで酷い判決とは思わなかった。訴えを退けるためにできるだけ最短距離で書いた本当に不出来な判決。なぜそうするのか、裁判官の出世の問題とか司法官僚制の問題とかあるが、あえて言えば、"少しでも踏み込むと、この種子法廃止の筋が通らなくなる。少しでも原告の主張に反論しようとすると具体的には何も言えない。そもそも種子法廃止を強行した理由がどこにも見出せない"ということではないか。」「改めて(2015年の)TPP交渉差止訴訟から来て感じるのは、グローバリゼーションにともなって国民の行政を破壊していく一連の流れに抵抗していくのは"極めて、壁、厚いな"。ただ世界の情勢は変わってきて"国民のことも大事にしろよ"と必然的になるので、私たちはこの歩みを止めてはいけない。グローバリゼーションに対して個々の権利を主張し、国のあり方を変えていこう。」と前向きに語られました。
「種子法廃止違憲訴訟」は、2015年の「TPP交渉差止・違憲訴訟」の第3次訴訟として起こされました。山田正彦先生は(45:25)「今日が一番くやしい思いをしました。」と述べ、しかし種子条例という形で実は種子法を守って来た、これまでの10年を思われたのか涙ぐみながら「10年以上無報酬で戦ってこられた弁護団に拍手していただけませんか。」と求めておられました。
国民の声に向き合わない判決を前に、弁護団はすでに上告の意志を固めておられるようです。最高裁では、国民の食を守る種子法を廃止したことへの憲法判断となります。
今まさに「令和の百姓一揆」も始まり、正念場となりました。私たちは、これまで専門家に任せてきたこの訴訟をガッツリ支えて、種子法を取り戻しましょう。
山田 正彦さんからのお願いです。
— Max (@universalsoftw2) February 17, 2025
皆さんに毎回お願いですが、参加して頂けると大変嬉しいです。
いよいよ種子法廃止違憲訴訟の東京高裁での判決言い渡しが2月20日(木)午後3時に行われます。当日午後2時から東京地裁正門前で門前集会 それから弁護団と皆さんとの意見交換会が参議院議員会館の109 pic.twitter.com/MgEdOa4weF
会議室で4時30分から行われます。
— Max (@universalsoftw2) February 17, 2025
早いものでTPP交渉差止・違憲訴訟からすれば10年になろうとしていますが生きていくために私達国民は安全な食べ物を持続して国から供給を受ける権利がある大事な裁判です。
お待ちしています。
種子法廃止違憲確認訴訟は残念ながら控訴棄却。廃止の立法事実(日本には優れた民間品種がある+コメの供給不足はない)はどちらも破綻しているだけに不当判決。
— 日本の種子(たね)を守る会 (@SaveSeedsJapan) February 20, 2025
私たちの食料主権についても理由も付さず憲法判断を回避したことは司法の役割を放棄したものと感じる。
狭き門だがぜひ最高裁で判断を! pic.twitter.com/bEUBFYTdSM












江藤大臣は元々爆弾発言を連発していたそうです。2024年12月18日衆議院農林水産委員会では「国民の皆さま方は輸入した物が食べたいんですよ。」「今の食料自給率38%を考えると、ヘタをすると生産過剰になる可能性がある。」と言っています。
「マジで何言ってんだコイツ、と思った方は正常な頭脳の持ち主です。」と、キシキン氏。「彼の理論だと現在の日本人は、国産よりも輸入食品、しかも危険な農薬まみれの食品を食べたいという人が大多数を占めているようで、しかも現在の食料自給率カロリーベースで38%しかないのに、それすらも過剰とか意味わからんことをほざいています。」と解説されました。
この江藤大臣の「意味わからん」発言には理由がありました。この後の答弁で江藤大臣は「14億人の人口を抱える中国の、さらに超富裕層は日本の食材に極めて高い関心を持っている」「中国人の旅行者の方々は日本に来て、価格が安いとニセモノだと思うらしい。高くないと信じない。なんで一流の和牛が3万円なのか、10万円しないと信じない。そういう方々がおられるマーケットになんとしてもアクセスしたいと思って頑張っている。」とギョッとするようなことを述べていました。
キシキン氏によると「今後は日本人が一生懸命作った食べ物は中国人に全力で売っていくようです。日本人が作った国産食品は海外の富裕層向け、逆に外国産の意味わからん農薬まみれの食品は多くの日本人向けにする的な感じのことを堂々と発言しています。」となります。
さらに関連で「米の輸出還付金で儲けている企業はどこでしょうか?」という質問に答えて、農水省がすでにこの売国政策をかなりの規模で進めている実態を伝えておられました。農林水産省の出している資料にはJA全農を初め輸出上位企業がありました。キシキン氏は「各企業のHPを見にいくと、米の輸出にかなり力を入れているのが分かります。米の輸出に関しては『モデル輸出産地』というものがあり、輸出のためだけに年間約17万トン以上を目標にコメを作っています。これらの米が国内に回ることはまずないので、相当な量を輸出していくつもりかと思います。ちなみに中国特化の輸出企業もここに載っています。最近はやりのパールライスもバッチリ記載されています。」と解説されていました。
そして「皆様も気づいていると思いますが、自民、公明、維新はこれらのことを既定路線化していますので、外国産の意味わからん食品を主食にしたくない人は絶対に自民、公明、維新に投票してはいけません。」と警告されていました。