注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

新型ウイルス クルーズ船 乗客の下船始まる 約500人が下船へhttps://t.co/Q3N0u3sb3E
— 藤原直哉 (@naoyafujiwara) February 19, 2020
武漢から家に戻って42日後に新型肺炎と診断された人がいたhttps://t.co/nJQauOak6m
— 藤原直哉 (@naoyafujiwara) February 18, 2020
岩田教授はBBCとの2つ目の動画で今日のダイアモンド・プリンセスの乗客下船について「非常に懸念している」「昨日感染した人がいるかもしれないのに」「(陰性という)検査結果のミスリーディングだ」「無症状だから大丈夫というのは科学的にも論理的にも間違い」https://t.co/qezS8xpN17
— ゆーすけ (@yoox5135) February 19, 2020
え、下船の前日に感染したかもしれないじゃん。それが十分に考えられる状況じゃん。https://t.co/pJMzQIOUMp
— kentarotakahashi (@kentarotakahash) February 19, 2020
検査しても偽陰性が多いことが報告されている。感染したばかりで、検査では陽性にならないのかもしれない。それを下船したら、そのまま帰宅って、ありえない。
— kentarotakahashi (@kentarotakahash) February 19, 2020
» 続きはこちらから










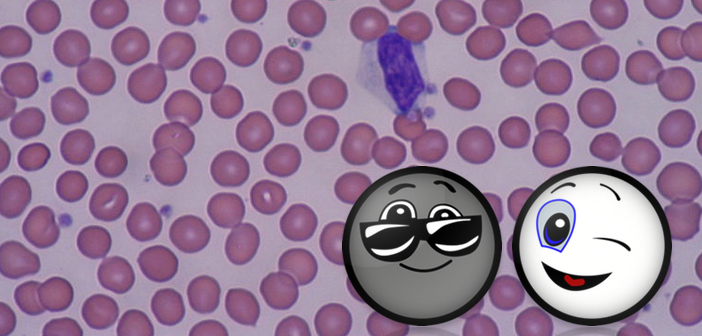








潜伏期間が2週間よりも長い例が報告されています。また、検体を取った時には感染していなくても、「下船の前日に感染したかもしれない」のです。検査で陰性だったとしても偽陰性(感染しているのに陰性になること)の可能性もあります。
“続きはこちらから”の記事によると、感度95%、特異度99.9%、有病率を30%と仮定して、3272人全員にPCR検査を実施すれば偽陰性が49人。引用元では、“有病率が50%であれば偽陰性は82人、つまり、全員検査を行えば49人から82人ほどの感染者を見落とすことになる”と言っています。現状のダイヤモンド・プリンセス号の有病率から、少なく見積もっても約50人の感染者を下船させることになるのです。
箱コネマンさんのツイートによると、CDC(アメリカ疾病予防管理センター)は「クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号の乗客乗員への検疫は無効であり、継続した感染のリスクを抱えたまま下船させる事になる」と日本政府に警告したとのことです。
“バカなのか?”という問いは、すでに過去のものです。新型コロナウイルスよりも遥かにタチが悪く、本来ならそこに居てはいけない連中が権力を握っているということ。
仏教には八大地獄があり、地獄の最下層に位置するのは阿鼻地獄(あびじごく)です。無間地獄(むけんじごく)ともいいます。トランプ大統領が安倍首相を呼ぶときに使う「アビー」を用いて、これからは「アビー地獄」と呼んだ方が良いのではないでしょうか。近いうちに日本のあちこちに現れると予想されます。