注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
————————————————————————
————————————————————————
日本が最低輸入量枠内でコメ輸入75%増
【ワシントン共同】トランプ大統領が4日署名した大統領令は、日本が高関税を課す代わりに無関税で輸入する仕組みのミニマムアクセス(最低輸入量)の枠内で、米国からのコメ輸入を75%増やすと明記した。
————————————————————————
【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】コメ騒動と米国との関係~根底にある「胃袋からの属国化」
令和のコメ騒動が収まらない。辿っていくと、日本の食と農を苦しめて、ここまで追い込んだ根本原因は米国との関係に行きつく。私達は、米国による「胃袋からの属国化」から脱却し、独立国として米国と対等な関係を築かなくては、日本の食と農と日本社会が守れないということに気づく必要がある。(中略)
(中略)
この一連の騒動には、米国との関係が大きく影響していることを押さえる必要がある。今回のコメ騒動の根底には減反政策があるが、それは、米国の日本占領政策の一環としてコメ消費を減らして日本人が米国の農産物に依存しないと生きていけないようにする「胃袋からの属国化」の結果だ。
(中略)
さらに、米価下落に対処するセーフティネット政策が打ち出せないのも、米国との関係なのだ。米国からの要請に応えて武器などの購入に莫大な予算が必要になる。それは拒否できないので、その分、どこからか予算を削減しなくてはならない。その一番の標的に農業予算が位置付けられている。そのため、稲作農家の所得補填政策が打ち出せない。田んぼを潰せば「手切れ金」だけ出すという水田の畑地化政策も予算削減に資するものとして行われた。
私達は、米国による「胃袋からの属国化」から脱却し、独立国として米国と対等な関係を築かなくてはならない。今こそ、「胃袋からの独立」を実現しなくてはならない。


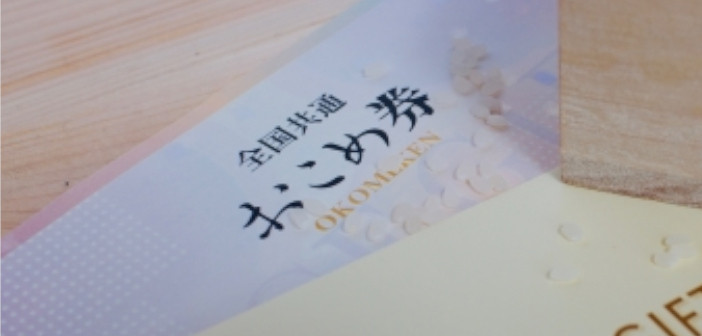


![[鈴木宣弘先生×深田萌絵氏] 石破政権の増産政策から一転、高市政権の減反政策は「お金が出ない」その代わりに「おこめ券」/ 「自給率100%」「財政の壁をぶち破る」は本当か?](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2025/11/m1116.jpg)


![[鈴木宣弘先生] 米国の農産物に依存しないと生きていけない日本にする「胃袋からの属国化」〜 トランプ関税でも自動車の生贄にされたコメ、売国政府を追い出し胃袋の独立を](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2025/09/m906.jpg)






![[鈴木宣弘先生] 令和の米騒動の根源には、日本の貧困化がある / 超党派の議員立法で適正な生産者米価と消費者の価格のギャップを埋める交付金を早急に](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2025/07/m725.jpg)


この鈴木農水大臣が発表した「お米券」について、高橋ひであき氏がまとまった解説をされていました。
鈴木大臣は、物価高支援として新たに地方交付税を配布すると発表しました。「お米券」を使うか、その他の手段を使うかは自治体の任意です。「お米券」を使う場合は、すでにある「JA発行のお米券」と「全米販(全国米穀販売事業共済協同組合)発行のお米券」の2種類を使う方法と、各自治体が独自に「お米券」を発行する方法を挙げています。
JAや全米販の「お米券」であれば、すでにあるので鈴木大臣は「自治体に手間を取らせません」と言っています。しかし高橋氏は、JAや全米販への利益誘導になる可能性や、現在「お米券」は転売・換金ができるという問題点があると指摘しています。
各自治体が独自に「お米券」を発行する場合は、印刷や郵送など発行の費用が20%以上かかるそうです。すると、JA・全米販の「お米券」よりも安い券になるという不公平が生じます。
また、お米券を発行するときに、電子チケットを使う方法があります。経費は抑えられますが電子チケットに馴染みのない人には使いづらく、またスマホやPCでアクセスできない人はどうするのかという問題があります。
さらに自治体の判断で、野菜など他の食品にも使えるプレミアム商品券も可能になるそうです。お米の価格が高くて困っている人のために始まった「お米券」が、お米以外にも使えるのでは元々の主旨から外れ、「お米は面倒見ません」という話になると高橋氏は指摘しています。
このように「お米券」は制度がしっかり設計されていないことがわかります。
交野市の山本市長は、市民のために交付される5億円は「お米券」ではなく、小学校の3学期給食無償化、上水道基本料金と下水道基本料金の8ヶ月免除などの施策を予定しているそうです。