読者の方からの情報です。
注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
————————————————————————

配信元)
セイタカアワダチソウの抽出物で、鳥インフルH5N1を予防・治療する。
— リチャード・コシミズ/richard koshimizu (@ric_koshimizu) March 29, 2025
セイタカアワダチソウは、「背が高くて、泡が立つ」雑草。外来植物。繁茂力が強く、他の植物の成長の邪魔をするため、一気に増える。通常は、邪魔者扱いで、刈り取られるだけ。
だが、多様な… pic.twitter.com/H28dTDF7q2
————————————————————————
抗ウィルス治療・予防用薬物調製におけるセイタカアワダチソウの応用
引用元)
Abstract
【課題】エイズ(AIDS)ウィルスを効果的に治療・予防できる薬物を研究開発する
【解決手段】 抗ウィルス治療・予防用薬物調製におけるセイタカアワダチソウの応用において、薬物は次の重量パーセンテージの原料によって作られ、セイタカアワダチソウの含有量50〜100%であり、セイタカアワダチソウはH5N1鳥インフルエンザ又はインフルエンザウィルス治療・予防用薬物の調製中に応用され、セイタカアワダチソウはエイズ(AIDS)ウィルスの治療・予防用薬物の調製に応用されている。
(以下略)
【課題】エイズ(AIDS)ウィルスを効果的に治療・予防できる薬物を研究開発する
【解決手段】 抗ウィルス治療・予防用薬物調製におけるセイタカアワダチソウの応用において、薬物は次の重量パーセンテージの原料によって作られ、セイタカアワダチソウの含有量50〜100%であり、セイタカアワダチソウはH5N1鳥インフルエンザ又はインフルエンザウィルス治療・予防用薬物の調製中に応用され、セイタカアワダチソウはエイズ(AIDS)ウィルスの治療・予防用薬物の調製に応用されている。
(以下略)
————————————————————————
イタドリの効用
引用元)
note 中村 篤史/ナカムラクリニック 25/10/5
(前略)
イタドリは、英語でJapanese knotweedと言われているぐらいですから、日本のあちこちに自生していて、多分みなさん見かけたことがあるはずです。雑草として厄介者扱いされていますが、「知は力なり」で、知識のある人にとっては薬草です。
ポリフェノール(レスベラトロール)を高濃度に含み、ある研究によると、抗癌作用、抗炎症作用、心臓保護作用が認められています。
両植物の抽出物は、ごく微量(0.03~0.5%)でも細菌のコロニーを死滅させ、微生物の分裂を阻害しました。
1%のキニーネを7日間単回投与するだけで、細菌は完全に根絶されました。薬剤不在下でも、一度根絶されれば、最適な条件下に戻しても細菌は再増殖しなかった。
これは何を意味するか?
研究者「たとえばライム病は体内で休眠型になり、こうなると抗生剤はまったくの無効になりますが、今回の研究で検証したハーブは、休眠型の細菌に対しても強力な活性を持ちました。これを証明したエビデンスは初めてのことです」
(中略)
なぜイタドリが効くのか。
核心はポリフェノールにある。イタドリには、レスベラトロール、ケルセチン、カテキン、エモジン、ポリジンなど、様々な抗炎症物質が含まれている。レスベラトロールといえば、ブドウの皮が有名だけど、イタドリのほうが遥かに含有量が多い。抗炎症作用、抗酸化作用のみならず、抗老化作用、抗癌作用まであるというのだから、毎日イタドリ茶を飲めば、日々病気知らずで過ごせるだろう。
(以下略)
イタドリは、英語でJapanese knotweedと言われているぐらいですから、日本のあちこちに自生していて、多分みなさん見かけたことがあるはずです。雑草として厄介者扱いされていますが、「知は力なり」で、知識のある人にとっては薬草です。
ポリフェノール(レスベラトロール)を高濃度に含み、ある研究によると、抗癌作用、抗炎症作用、心臓保護作用が認められています。
両植物の抽出物は、ごく微量(0.03~0.5%)でも細菌のコロニーを死滅させ、微生物の分裂を阻害しました。
1%のキニーネを7日間単回投与するだけで、細菌は完全に根絶されました。薬剤不在下でも、一度根絶されれば、最適な条件下に戻しても細菌は再増殖しなかった。
これは何を意味するか?
研究者「たとえばライム病は体内で休眠型になり、こうなると抗生剤はまったくの無効になりますが、今回の研究で検証したハーブは、休眠型の細菌に対しても強力な活性を持ちました。これを証明したエビデンスは初めてのことです」
(中略)
なぜイタドリが効くのか。
核心はポリフェノールにある。イタドリには、レスベラトロール、ケルセチン、カテキン、エモジン、ポリジンなど、様々な抗炎症物質が含まれている。レスベラトロールといえば、ブドウの皮が有名だけど、イタドリのほうが遥かに含有量が多い。抗炎症作用、抗酸化作用のみならず、抗老化作用、抗癌作用まであるというのだから、毎日イタドリ茶を飲めば、日々病気知らずで過ごせるだろう。
(以下略)


























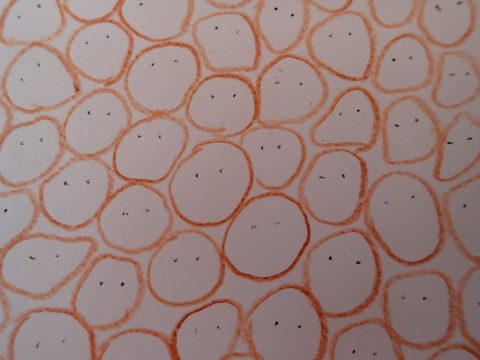

今回届いた情報は、リチャード・コシミズ氏による「セイタカアワダチソウで鳥インフルH5N1を予防・治療する」というものです。中国の研究者の論文に「鳥インフルH5N1に感染した鶏、584羽を本剤で治癒したところ、95%が回復した。同じく予防投与した242羽の健康な鶏の感染予防率は100%だった」とあり、A型インフルエンザの治療や予防に有効なだけでなく、鳥インフルへの治療、予防が期待できるそうです。セイタカアワダチソウがよく効くのであれば、養鶏場での鶏の大量虐殺も防ぐことができます。
ぴょんぴょん先生の記事にもありましたが、セイタカアワダチソウの効果が高いのは、花が咲く前の蕾の状態です。つまり今、今が採取のベストシーズンだそうです。
もう一つの「イタドリ」は、ナカムラクリニックの中村篤史医師の情報です。抗生剤以上の抗菌性を示すと評価されているハーブの中で「圧倒的に優れた効果を示したのは、キニーネとイタドリ」だったそうです。キニーネは、西アフリカ原産の低木ですが、イタドリの方は日本のあちこちに自生するタデ科の"雑草"です。イタドリは「レスベラトロール、ケルセチン、カテキン、エモジン、ポリジンなど、様々な抗炎症物質」が豊富に含まれているそうです。「抗炎症作用、抗酸化作用のみならず、抗老化作用、抗癌作用まである」らしく、中村医師ご自身の不調にも「イタドリの各種成分が、僕の体内の細菌類をしっかり駆逐してくれたということだろう。」と著効を示したそうです。元記事では「50年間全身性のリウマチで、骨の変形と腫れのため、激痛に苦しむ女性」がイタドリに救われたケースも紹介されていました。
この2つの野草の効果について、竹下雅敏氏から「どちらも優れた情報です。」とのコメントが届きました。