注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

クリントンに相対する証人になると自宅が謎の大爆発
本日クレムリンで出回っている【ロシア】対外情報庁(SVR)の大変気掛かりな新報告書によると、ヒラリー・クリントンおよびクリントン財団に対するFBIの捜査拡大の一環として来たる週に大陪審の前で証言する筈だったアメリカ連邦政府側の証人が、ニュージャージー州の自宅をすっかり跡形もなく【破壊】した大爆発で夫と共に無残にも殺されました。
――そして彼女が証言する予定だったのは医薬品の価格吊り上げによる暴利行為を隠蔽するためにクリントン財団に資金を提供したアメリカを拠点とする悪名高き製薬会社を巡るものでした。
@NJSSNA1 @schoolnurses Tragic event took the life of a
— Robin Cogan (@RobinCogan) 9 July 2018
NJ Retired school nurse, husband killed in earth-shaking house explosion https://t.co/ZJdXYCg6nA
» 続きはこちらから




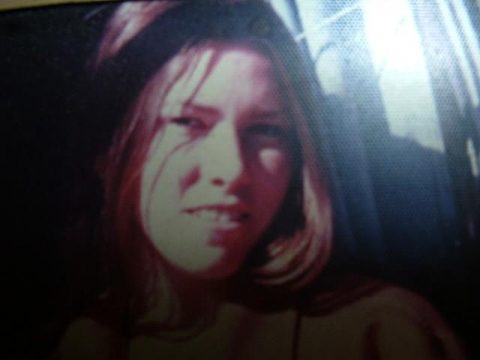








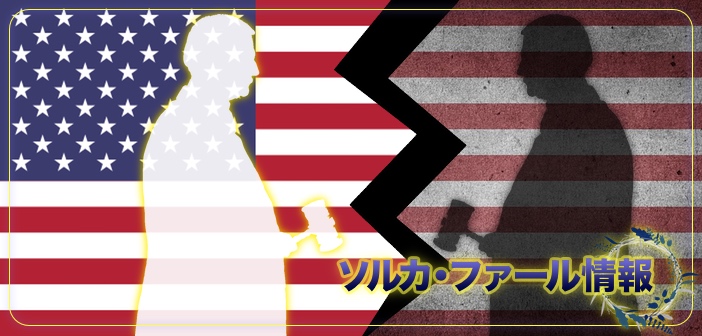






エピペンとはアナフィラキシーショックを起こした緊急時に使用される注射です。これを学校で常備するよう全米教育委員会評議会が推進し、あちこちの州が法律で義務付けると、市場の9割以上を独占する製薬会社が価格を米国の下院で公聴会が開かれるレベルにまで急騰させたのです(2009年には2本入り一箱100ドルだったのが、問題になった2016年には600ドルに)。そいで風当たりが強いので(当たり前や!)、ジェネリック版を“慈悲深く”も300ドルで売り出すことにしてくださいました。
この会社ってば開発研究費なんて払っちゃいませんよ! 2007年になってから別会社から権利を買い取ったんですもん。いやだからこその“ジェネリック”なんですけど……だから普通は安いんです、よ、ね? え、何コレ、意味分かんない。
しかも記事本文に登場するCEOによると、価格600ドルとはいえ会社としての儲けは実質50ドルほどだそうです。ふーん、じゃあ主力商品のエピペンとは別のところで超多額のCEOとしての報酬もらって個人資産を急増させるカラクリが更にあるんですかい。ちなみにエピペン一本の材料費は1ドルだそうです。
そして法案推進役、全米教育委員会評議会のトップだった彼女の母親は、夫がウェストバージニア州知事だった時代に州教育委員会のナンバー2にしてもらってます(※後にはナンバー1になりました)。誰にって夫に指名されて委員会に入れてもらったんですよ。その夫は娘がCEOを勤める製薬会社から多額の選挙資金をもらっています。なんでしょう……モリカケ蕎麦な匂いがプンプンします。
これだけでも顰蹙ものなのに、後半ではこんなあくどい金儲けすら霞んでしまうという別の製薬大手によるオピオイド虚偽情報操作事件が出て来ます。オピオイドは麻薬性鎮痛薬などの総称で、薬物依存による死者続出で深刻な社会問題化しています。そこでもやっぱりクリントンが絡んでいました。流石のコンプリートです。
ただ見方を変えれば、訴訟が次々に起こされて追い詰められているということにもなります。何せクリントン夫婦が警護なし&一般人ひしめく民間機で移動し始めましたから。資産が差し押さえられたのでは、と専らの噂です。それでも殺しは止められないってヤツですかね、病気です。