竹下雅敏氏からの情報です。
————————————————————————
美味しい食べ物は、ぜ〜んぶ食品添加物でつくれますよぉ〜
配信元)
————————————————————————
配信元)
岸田政権の看板政策⁉︎
「バイオものづくり」ってのがあったとは…
気色悪っ(;"°'ω°'):https://t.co/FXPxzmy8la pic.twitter.com/wc7cl8aTX6— ルパン小僧🍑💍kuu331108 (@kuu331108) October 6, 2022
https://t.co/TuPez4o4kk pic.twitter.com/ThtYb989gL— ルパン小僧🍑💍kuu331108 (@kuu331108) October 6, 2022
» 続きはこちらから














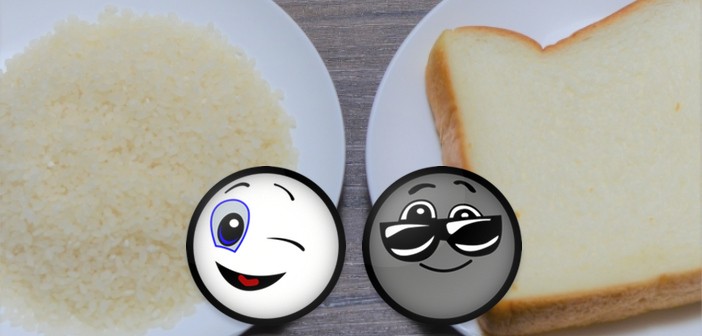



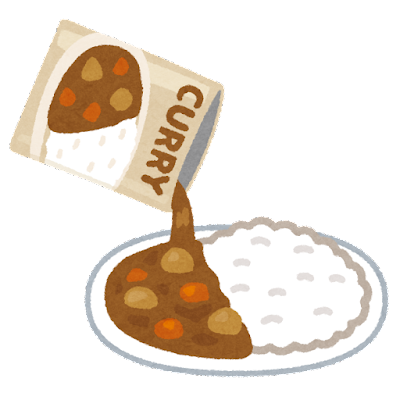

冒頭の動画では、“「辛吉飛」というブロガーが…しゃぶしゃぶ用ラム肉は鴨肉で作ることができると紹介していました。その他、合成ステーキ、リンパ肉小籠包、長期冷凍肉で作った塩フライドチキンなど、何でも揃っています。…この一連の動画が投稿された後、大きな波紋を起こしました。…TikTokはすぐに「辛吉飛」に電話で圧力をかけ、動画の用語や内容を変更するよう要求しました。これに対し辛吉飛は、「私の作品が違法したのか? それともモラルに反しているのか? それとも、これらの添加物が違法なのか?」と疑問を呈し、「私が言ったことは全部事実だ。業界全体がやっていることであり、私は食品工場で働いている」と述べました。”と言っています。
辛吉飛は9月下旬に、「(圧力がかけられた)背後の勢力が大きすぎて、最終的には仕方なく、アカウントを取り消した」という最後のコメントをTikTokに残した、ということです。
動画の1分の所では、ミルクとお茶を使わないミルクティー、鶏肉と大豆たんぱく質を使った牛肉、デンプンソーセージの作り方のレシピが出てきます。
岸田政権の看板政策となる「新しい資本主義」の実行計画の中に、「バイオものづくり」が重点事項の1つとして盛り込まれているということで、「日本ハムが独自に研究開発している培養肉」は量産化を目指しているとのことです。その日本ハムは、「たんぱく質を、もっと自由に」というCMで、“すべての人に愛されるたんぱく質を自由な発想で考える”と言っています。
自由な発想から生まれた究極の食品は既に存在しており、マクドナルドの〇肉ハンバーガーでしょうね。時々「歯」が混入してます。
大豆やトウモロコシの遺伝子組み換え食品から「培養肉」もつくられるのでしょうね。
そして、国連がみんなに食べさせたい「昆虫食」です。昆虫食には発癌性のリスクがあるようですが、ワクチンのリスクを隠蔽できるのなら、こんなものは何でもないですね。病気が増えて病院、製薬会社は儲かりますね。
外食が平気で出来る人々なら、「培養肉」も「昆虫食」も知らない間に口にしているという未来になりそうですね。私は嫌なので、違う未来を望みます。