注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
————————————————————————
OKシードマーク
(前略)
 (以下略)
(以下略)
————————————————————————
————————————————————————
緊急署名、そしてOKシードマークの使用拡散のお願い!
————————————————————————
小学校にゲノム編集トマトの苗を配る!?
(前略)
筑波大学で国の助成を受けて開発されたゲノム編集トマトがサナテックシード株式会社により販売が9月から始まっています。しかし、販売はオンライン販売の微々たるもの、と思っていたら、そんなことではないようなのです。
サナテックシード株式会社は昨年12月から市民のモニターを募集し、4000人の市民ボランティアに苗が配られました。そのことを通じて、同社はゲノム編集食品を支持するコミュニティができたとして、それをさらに広げて、来年から障がい児介護福祉施設に苗を無償配布、さらには2023年には小学校に苗を無償提供して、子どもたちがこのトマトを育てるようにしていきたい、と言っているのです(竹下 達夫パイオニアエコサイエンス株式会社/サナテックシード株式会社 代表取締役会長の『サイバーフィジカルシステムを利用した作物強靭化による食料リスクゼロの実現』シンポジウム10月22日での発言)。
今、ほとんどゲノム編集食品の危険に関する報道は行われていないため、介護施設や小学校側も危険性を考えずに、無償提供されるのなら、ということでゲノム編集トマトの苗の提供を受け入れる可能性もあるでしょう。子どもたちはトマトを育てることに夢中になるでしょうし、収穫したトマトを食べることになるでしょう。その子どもの経験でその家庭をゲノム編集トマトを受け入れる方向に変え、市場も受け入れる方向に変えていくことがこの無償配布の目的であるのかもしれません。世界ではゲノム編集食品は市場の拒否にあって増えていないのが現状であり、その市場の「抵抗感」を取るのが最大の目標であると考えられます。
ゲノム編集トマトを食べたから直ちに健康障害などが起きるということはないかもしれません。しかし、従来の遺伝子組み換え食品が始まる時も、遺伝子組み換え企業が「遺伝子組み換え食品は従来の食品と実質的に同等だ」という安全神話を振りまきましたが、世界で最も遺伝子組み換え食品の消費量が多いと思われる米国では、遺伝子組み換え食品普及後、アレルギー、糖尿病、さらに深刻な慢性疾患で苦しむ人が遺伝子組み換え食品が拡大すると共に、大きく増加し、人びとは遺伝子組み換えでないというラベルのついた食品を買うように市場が大きく変わってきています。
体に影響が出るのには時間がかかりますし、出てから治すのはとても大変であり、その意味で安全性の確証されないものを予防原則で避けることが重要になってきます。
今回のゲノム編集トマトはそのような長期的な影響についてまったく調べられておりません。その影響が不明なものをこれからの体を作る途上で無防備の子どもに食べさせることにつながるプランに対しては、強い違和感と不安を感じざるをえません。
今回の小学校へのゲノム編集トマトの苗の配布は学校給食で使うというものではありませんが、収穫されたトマトは子どもたちの口に入ることはほぼ確実でしょう。将来的に学校給食への採用も道を開いてしまうかもしれません。
今、全国各地でより安全な食にするために学校給食を有機にしようという運動が急速に拡がっています。台湾では遺伝子組み換え食品を学校給食に使うことは禁止されていますし、日本でも愛媛県今治市では禁止する条例を作っています(3)。ゲノム編集食品も同様に規制・禁止すべきという声は今、世界でも広がりつつあります。この動きはそれに逆行するものです。
予防原則の見地から、この無償配布をやめるようサナテックシード株式会社に声を届け、また全国の小学校、教育委員会がそのような危険が予想される苗の無償配布を受け入れないように早急に取り組む必要があるとわたしたちは考えます。
(以下略)
» 続きはこちらから





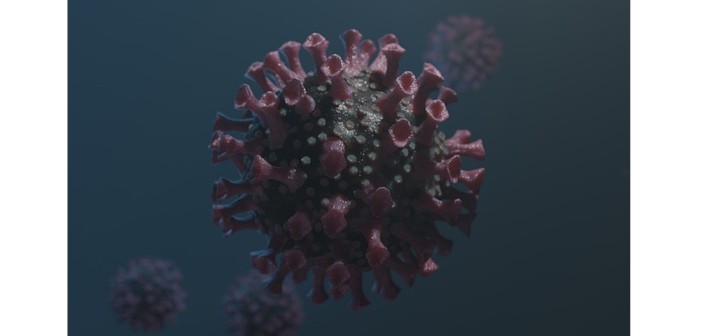








 どんなにゅーす?
どんなにゅーす? 
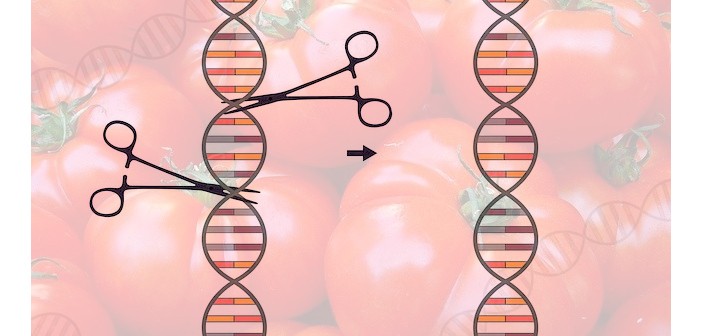

 (以下略)
(以下略)

そもそも検察は公文書改ざんの関係者を全員不起訴にしたために、やむなく赤木雅子さんは損害賠償請求を求める民事訴訟を起こしました。やすやすと認諾できないように、赤木さん側の負担する印紙代が高額になることを覚悟の上で、法外とも言える1億円の請求額にしました。その訴訟の目的は賠償金ではなく「なぜ赤木俊夫さんは自殺に追い込まれなければならなかったのか、その原因と経緯を明らかにする」「誰の指示に基づいてどのような改ざんが行われ、どのような嘘の答弁が行われたかを公的な場所で説明する」ことと訴状に明記されています。
しかし国側は、それまで争っていた姿勢を一変して「認諾」した。川村晃司氏によると認諾を公表した前日の14日、財務省の官房長が官邸に出向き、認諾を岸田首相に提案したようです。岸田首相は国民の公金を使って1億円を支払ってでも不都合な真実を隠蔽することに決め、17日の国会ではまるで他人事のような答弁しました。
国が被告となる裁判で「認諾」するのは異例中の異例と言われ、国会でも過去4例しか確認できません。国に賠償を求める裁判は、訴訟によって違法や不法のプロセスを明らかにすることに意味があると情報公開に携わる三木由希子氏は述べています。何が問題だったのかを国に立証させ、裁判でそれを認定するという国民の利益を国が回避するという犯罪にも等しい行為です。
しかも財務大臣は「情報公開請求が多く出ていてその処理に追われていたことが赤木さんを追い詰めた」と情報公開請求の業務が原因であるかのような言いぶりでしたが、三木氏によると、財務省が改ざん隠蔽を散々行った結果、情報開示の通常処理できなかったのであり、普通に開示していれば赤木さんが忙殺されることもなかったのです。財務省は二重三重に悪質です。
地方自治体では、損害賠償の額など地方議会の議決が必要となりますが、神保哲夫氏によると国の場合、国家予算の中に各省庁の和解や賠償金の「賠償償還金払戻金」がすでに盛り込まれていて、実は認諾の権限も行政に与えられているそうです。けれども、その認諾で1億円の支出をすることが予算の使い方として妥当であったか、目的外の支出ではないかと決算委員会で追求することはできると提案されています。また官僚であった福島伸享議員のブログでは、野党が真剣に追求する気があるのであれば「予算の採決を人質にとって予算審議時から強硬な交渉をすべきだ。」と別件ですが追求の要諦を示されていました。国は争っていたのに証人尋問を前に急きょ認諾し、この認諾で一番安心したのは安倍晋三です。
神保氏は、この認諾が赤木雅子さんだけの問題ではない、日本人がこれをどう受け止めるか、国会と市民社会、そしてメディアに投げられた重大問題で「絶対に許せない」と思えるかどうかが問われると指摘されていました。一人の無能な政治家を守るために国家が人を殺してまで嘘を押し通すことを許すのか。許せるはずがない。参院選という機会もあります。赤木雅子さんは新たな署名を求めておられます。