————————————————————————

地球ニュース:ロシア&イタリア
ロシア:ロスチャの牙城、銀行システム切り崩し作戦
24日付けのRTの記事によりますと、ロシアはアメリカからの更なる制裁の可能性に備えて、悪名高き“SWIFT”から切り離されても銀行間の送金が可能になる代替システムを完成させちゃいました。
ロシア連邦中央銀行エリヴィラ・ナビウリナ総裁がサンクトペテルブルク国際経済フォーラム(※略称SPIEF、1997年からサンクトペテルブルクで毎年開かれているロシアの経済フォーラムです。これまた悪名高き“世界経済フォーラム”とは別物。)にてコメントしています:
「グローバルな金融システム……を使うことにはリスクが伴います。……そこで2014年以来、私たちは支払システムを含めて独自のシステムを開発してきたのです。ロシア国内で金融データを転送するSWIFT同様のシステムを創造しました。……このシステムは既に稼働しております」
一昔前なら、こんなこと口走っただけでもロスチャイルドが戦争仕掛けて抹殺していましたよね、なんだか時代が変わったなと思えた良いニュースでした。最近は原油先物取引や二国間の交易での人民元採用が脚光を浴びていましたが、オイルダラーからの脱退を図っているのは、中国だけではないのです。
そうそう。Mirカードってご存知ですか? ミール(Мир)はロシア語で「世界」あるいは「平和」という意味です。2014年のウクライナ問題による経済制裁で複数のロシアの銀行の顧客がアメリカ式のVISAとMasterCardを使えなくなり、その代替サービスとして導入されました(※VISAカードなど同様、普段のお買い物の支払い時やロシア全土のATMでの引出しに使えます)。
政府が積極的に普及を後押ししており、連邦法を修正して今年の7月1日からは、官僚だけでなく公共部門の全職員、そして国から何らかの福祉給付を受ける人はこのカードが必須になるそうです。年金生活者は2020年7月を目指しています。
Обслуживание карты «Мир» за рубежом: объединение платежных систем России и Армении https://t.co/UxzpLGyHLa pic.twitter.com/6stLOVhfDx
— Сделано у нас (@sdelanounas_ru) 2017年8月20日
モデルは中国の銀聯(UnionPay)カード。こちらの記事によると、银联の方は昨年一年だけで新たに67億枚発行され、14.7兆ドルのやりとりがありました。
そして昨年末には両者の決済システムを連繋させようという構想まで生まれています。
(※単に银联卡の画像をお見せしたかっただけなので、この記事と上のツイート引用記事とは関連していません。)加拿大银行联手银联 跨境汇款到中国一日到账: 据上海金融报:近日,银联国际与加拿大五大银行之一——加拿大帝国商业银行(以下简称“CIBC银行”)共同宣布 … https://t.co/n606okWWyu pic.twitter.com/YXTdgxddTW
— 加国地产资讯 estateinfo.ca (@estateinfoca) 26 January 2017
日本の国民が“アベノミクス”なぞという虚構に翻弄されている横で、ロシアや中国は現実的に対策を講じています。金融崩壊が起こっても持ち堪えそう……移住したいなー。
そしておまけです。冒頭のRTの記事で貼ってあったロシア連邦中央銀行総裁の笑顔が大変印象的でしたので、ツイートで同じものを御紹介。昨年ロシアが新たな200ルーブル紙幣と2000ルーブル紙幣を発表した際のものです。実は54歳のタタール人女性なのです。
В России представили новые купюры с аннексированным Крымом https://t.co/MV1PyV1ZgL pic.twitter.com/O4LLXMpGIl
— Радио Свобода (@SvobodaRadio) 2017年10月12日
» 続きはこちらから




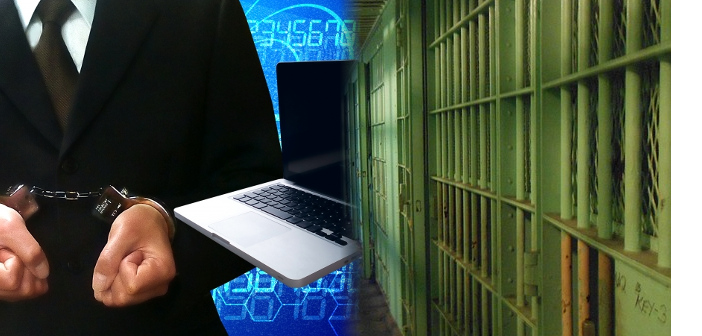


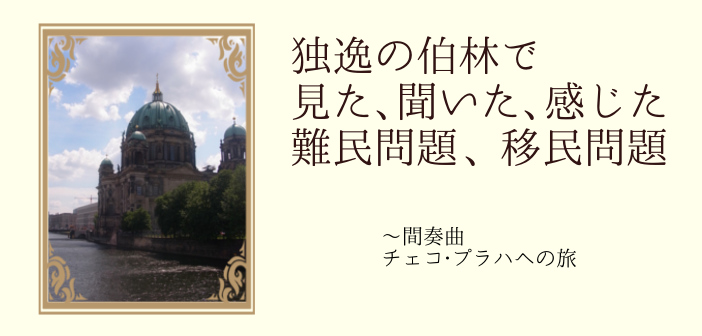








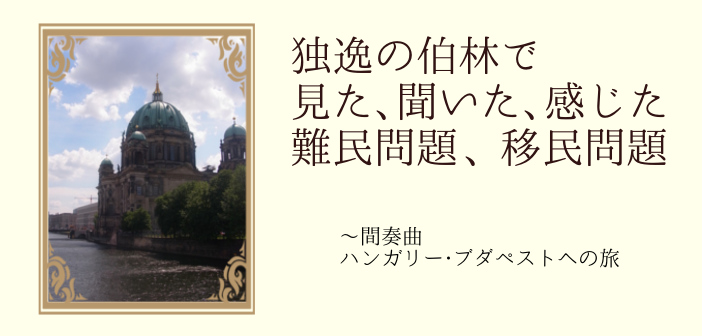





ロシアがSWIFT(※国際銀行間通信協会、世界中の金融機関の間で送金や決済を行うネットワークで、基本ここに入っていないと国際送金が出来ません)の代替版を稼働させました。ここ何年かの欧米からの制裁を口実に、迫る金融崩壊への対策を進めまくっています。さらにダーチャで食糧もそこそこ確保済。おそロシアですっ、羨ましいですっ。
イタリアでは連立政権の二つの党、五つ星運動と同盟が面白い入閣の条件を出してきました。この勢いでP2ロッジの大掃除も是非、支援して頂きたいもの。
ただ私なら「イスラエル反対、パレスチナ容認」も踏み絵にするでしょうか。これを条件にすると、以前ご紹介したシンシア・アン・マキニー博士が証言しているように、アメリカの議員なんて殆ど残らなくなるんですけれどね。
ロシアとイタリア、どちらも最後におまけ画像を入れております。