————————————————————————

ぴょんぴょんの「たかが虫垂、されど虫垂」 ~腸内細菌の貯蔵庫として重要な役割をもつ虫垂
腸内細菌に密接に関係している虫垂
今日まさにこの話出たんよね
— 美容師☆一輝 (@kobesur) October 24, 2025
若い頃に盲腸を取ったから
慢性疲労が何しても抜けないのかな?
という話になった
かなりの健康マニアで
色んなことを取り入れて
相当先行投資もされている
盲腸を取ってしまうと
体の回復スイッチを外された
状態で生きている
虫垂はいらない臓器と
教えられてきたけど… https://t.co/rhYSKVJsOE
※全文はツイッターをクリックしてご覧ください
・何をしても慢性疲労が抜けないのは、若い頃に虫垂を取ったから?
・だから、それを切除したら、体は再起動できない。
・虫垂を取ってしまうと、体の回復スイッチを外された状態で生きている。
・虫垂は、腸内フローラのバックアップ基地として働いている。・だから、それを切除したら、体は再起動できない。
(X)
*虫垂を失うと、腸で感じる力が弱くなる。(X)
*腸は身体のデトックスセンター。虫垂はその初期化スイッチ。(X)
*虫垂を取った人ほど慢性疲労・便秘・肌荒れが多い。腸が毒素を処理できず、常にバッテリー切れ。(X)
» 続きはこちらから


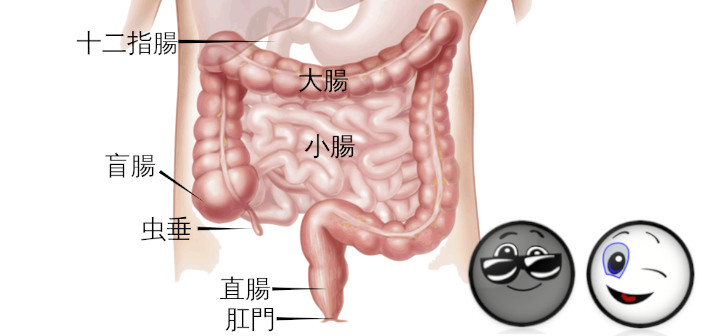














![[ナカムラクリニック] 今後日本で感染症騒動が起きたとしても、あらゆるRNAウイルスの感染予防法、治療法はすでに確立されている / 有効性を証明したゼレンコ博士](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2025/10/m1030.jpg)



昔は、「盲腸(虫垂炎)・即・手術」でしたが、虫垂の免疫的な働きが明らかにされてから、手術をためらう人が増えてきました。
虫垂はどこに、なんのためにあるのか?盲腸とどう違うのか?切るとどうなるのか?切ったらアウトなのか?そこら辺を、掘り下げてみました。