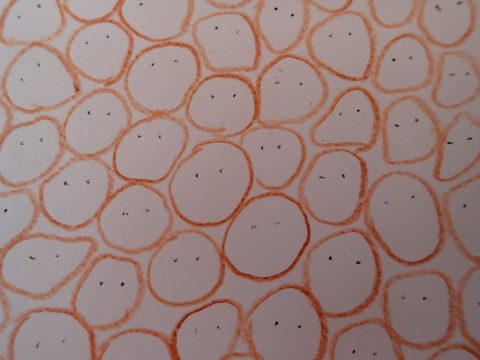たまたま虫を見つめることで、図らずもヴィクトル・シャウベルガー氏の解き明かす「自然の精妙なエネルギーシステム」が地球の未来に繋がる重要な鍵であることに結びつく。それとは真逆の方向性である、現代科学の根本的な間違いが、当然の結果として地球の生態系や生物多様性を損ねてきたのが理解できます。小さい虫の大きな存在を感じます。
————————————————————————

太古から変わらぬ営みを続けている虫たち
先月あたりの話なのですが、花壇に虫が1匹飛んでいました。よく覚えていないのですが、ミツバチかな?と思います。その虫の周りだけが太古の自然を感じさせるのです。虫を中心に半径50㎝位?の空間が異次元なのです。そして思ったのは、その虫は頑なに太古の自然を記憶していて、植物に影響を与えている。記憶は遺伝子に残されていて、虫の存在が植物たちを元気付けている。ということは地球の自然回復に虫が重要な存在なのでは?ここでも私たちは虫に対しての認識が欠けている。もしくは間違っている?太古から変わらぬ営みを続けている虫には、太古の記憶がある。
地球と共に生きている自然界の生物たちと、人間の違いが浮き彫りになります。殺虫剤、農薬、除草剤、空気汚染、土壌汚染、川や海の汚染、海の埋め立て、樹木や山が姿を消す団地開発、高速道路、地面が呼吸できないアスファルト、コンクリート、戦争、ミサイル、爆撃、原子爆弾、原水爆実験、原発事故を起こしてもやめない原子力発電所・・・間違っているのはどっち?本来の人間の営みも、ここまで間違ったものではなかったはずですが。
人が暮らすのにどこまで必要なのでしょうか?物や家が自然界に還りやすい状態で、子孫に迷惑をかけない暮らしができないものかと思うようになりました。その方が健康的で自然に近く幸せな暮らしができるのではないかとも思います。あるいは、ヴィクトル・シャウベルガー氏の示す自然の精妙な求心的エネルギー生成へと、現在の遠心的、分解的な技術や生活方法が180度転換できればと思います。
» 続きはこちらから