注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

藤原直哉氏(経済アナリスト)よりZoomヒアリング]
(3:30)
ブロックチェーンは、2018年頃から猛烈な勢いで実用化が進んだ。政府機関でも応用するところが増えている。
ブロックチェーンとは「分散型台帳技術」「分散型ネットワーク」、データをブロックに分けて、チェーンでつなぐ。
これまでは大きな箱の中にデータベースを順番に詰めていき、箱の中で追加したり変更していた。
しかしブロックチェーンは小さな箱にデータベースを詰めていき、次のデータは次の箱に詰め、箱(ブロック)と箱(ブロック)を暗号の鎖(チェーン)で繋ぐ技術。
先に詰めたデータを修正したり消したりできない性質を持っている。訂正が必要な時は、後から訂正のデータを追加する。そのためこのブロックチェーンは「改ざんに強い」と言われる(5:25)。
» 続きはこちらから










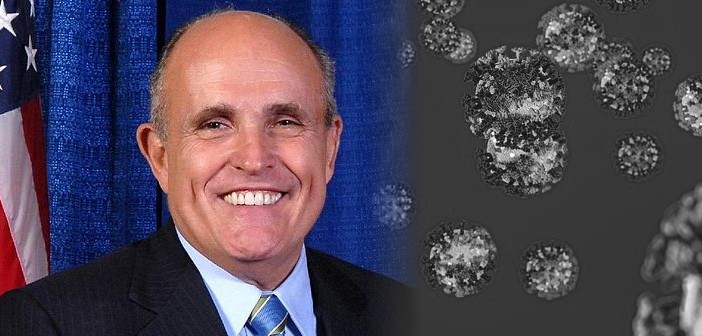


![[Twitter]食事中ですが。。。](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2020/12/u1217.jpg)

講義部分は3:25から42:00までの約40分です。とても面白く拝聴しました。興味深い部分を要約して書き起こしました。
ブロックチェーンは改ざんが不可能という特徴があります。不正がやりにくいシステムで公文書の管理や選挙にも応用できることに期待してしまいます。