「市民皆農」の必然
「みの虫革命ー独立農民の書」の著者である中島正さん(1920~2017)は自然循環型自給自足農業を実践し、平飼いによる自然卵養鶏の先駆者です。
「みの虫革命」とは
大自然に依存する以外は、農政にも農協にも商社にも金融にも、その他あらゆるものに依存せず、自給自足、自立独歩、(中略)かくして農業は大自然と共に在り、大自然の循環と共に行われる。大自然に順応し、大自然に育まれ、大自然の恵みに生きる。大自然の与うるものを、大自然の掟に従い、大自然の命ずるままに食う(中略)これを称して自然流のくらしという。そして自然流のくらしに転回を図ることを『みの虫革命』というまた、中島正さんは、非生産的、非自給的な都市化が人々を滅ぼすという都市の実態を明らかにして、「市民皆農」を訴えておられます。
引用:みの虫革命ー独立農民の書 中島正/著(十月社出版局・1986年)
都市が収奪・破壊・浪費するもの・・・①森林 ②農地 ③大地 ④農業人口 ⑤農産物 ⑥自然海岸と水産資源 ⑦エネルギーと金属資源 ⑧酸素と水 ⑨電源と水源 都市が排出するもの・・・①二酸化炭素放出 ②排気ガスによる大気汚染 ③高空オゾン層の破壊 ④汚染水垂れ流し ⑤ゴミと汚泥の埋め立て ⑥商品の洪水 ⑦強制過剰サービス ⑧戦争の仕掛け人
引用:murmur magazine for men 3号13p
この都市に生きるとは、田舎にいても非自給的な暮らしをしていれば、都市生活と同じで、逆に都会でも自給を目指す生き方があります。
「都会からはじまる新しい生き方のデザインURBAN PERMACULTURE GUIDE」ソーヤー海/監修(エムエム・ブックス)
「東京アーバンパーマカルチャー」のように・・・東京に種を植えよう・・・という人たちです。

ビワの木の下にニラ
以前、私は「循環式エコロジー住宅」の発想とともに、昔の田舎で家を建てる時に、地域の全戸から萱を持ち寄り、家の建築に協力し合う仕組みがあったように、お互いの家を一緒に建てながら、技術の習得や知恵を得る機会と伝承と、お金のかからない自立した生活基盤を、社会が保証する仕組みができたらいいなぁと思いました。
今、日本の山は戦後植林した杉檜が育ち、建築資材として活用されれば、山が自然林としての再生(木を伐った後植林をしなければ、埋土種子や鳥や動物が種を運び、その山に一番適した木が芽生え)するのを促し、動物たちの食べ物が育ち、土石流災害防止にもつながります。

杉の人工林と銀杏と竹林
放置人工林の杉檜を上手に活かして、自給自足生活基盤の家と、森林農法をする土地を供給する仕組みができないものでしょうか?山の再生と共に、地域活性にもつながると思うのです。
中島正さんと山下惣一さん、二人のジサマ百姓の書簡集「市民皆農」(倉森社・2012年)で、グローバル世界による二極化、貧富の格差社会は行きづまり、農業回帰、皆農の時代になる、と予測されていますが、今そのとおりになってきているのではないかと思います。
イギリスの環境NPOが掲げたグローバリゼーションの定義に「資本対民衆の世界同時戦争」というのがあるそうですが、民衆の側は敗退を重ね貧困化し、日本では、ここ10年間で30万人以上の自殺者に、最近では餓死、孤立死、貧困死もめだち、かたや、日本でも9億円以上の報酬を筆頭に3億円以上の役員報酬の20社など大企業が名を連ねています。
この市民の苦境を乗り越えるには他者に頼っていられず、自力で立ち上がるしかなくなります。すなわち自給自足です。
以下は中島正さんの言。
『究極は万人小農です。縄文が1万年も平穏を持続し得たのは「自分の食い扶持は自分で賄う、自分の生存は自分で守る」という「天与の大道、宇宙の法則、大自然の摂理」に順応した生き方を、すべての人が平等に実践したからであります。慎ましくても平穏無事、幸せな生活を少しずつ実践していきたいものです。
野生の動物は悉くこの天命方式に従っているので、狸も雀も蜻蛉も自殺するような憂き目に遭うことはあり得ません。』
『野生の動物はみな貧乏であります。富める狸やトンボなど一匹もいるわけがありません。これが正真正銘自然の生態であり、人間だって自然の動物なので、自然に即した暮らしをするのがあたりまえでなくてはなりません。しかるに驕慢にして強欲怠惰なる人間は、これをはみ出して贅沢と便利と快適と豊富と娯楽とに耽溺し、そのために生物生存の必須条件である空気や水や大地や食料を汚染、破壊して止まないのであります。
この横暴にして不遜な「富める生活生態」を全面的に支え、推進しているものがすなわち都市社会、都市産業なのであります。生存の必須条件である「食料」を作る「農」、これぞ自然の動物としての当然の生態であり、そして(ここが肝心)そのあたりまえの生態は、必ず「貧」であるということを肝に銘ずべきです。』
引用:「市民皆農」山下惣一 中島正(創森社)

さて、柚子をはじめ柑橘類の美味しい季節ですね。

柚子
また、柚子の中身をくり抜き、味噌を詰めてユベシを作ります。
ミリンや蜂蜜などで甘くしても良いのですが、私は味噌のままです。甘味を足す方が綺麗にできるようです。ゴマや刻んだピーナッツなどを混ぜますが、今年はドングリやスパイス(ディルシード)、キクイモ、唐辛子、黒砂糖、ヨモギの種、スギナなど色々なバージョンを作ってみました。

ユベシ
また、甘味に干し柿や黒にんにくを混ぜても良さそうです。乾燥した野草、フキの佃煮などを入れてもいいかも。
冷蔵庫の野菜室に竹の皮やお弁当箱に入れて寝かして、半年~1年くらいまでで、皮ごとスライスして食べています。
くり抜いた中身は絞って醤油と混ぜて柚子ポン酢に、種は焼酎漬けにして、飲んだり化粧水兼汚れ落としに使います。搾りかすはお湯を入れてホット柚子や、入浴剤にと、捨てるところなくいただけますね。
ちなみに柚子の薬効は発汗、解熱で、浴湯料として血行促進の効果があり、しもやけ、ひび、あかぎれ、肌荒れなどにも有効だそうです。



![[第38回] 地球の鼓動・野草便り 「市民皆農」の必然](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2017/12/38.jpg)











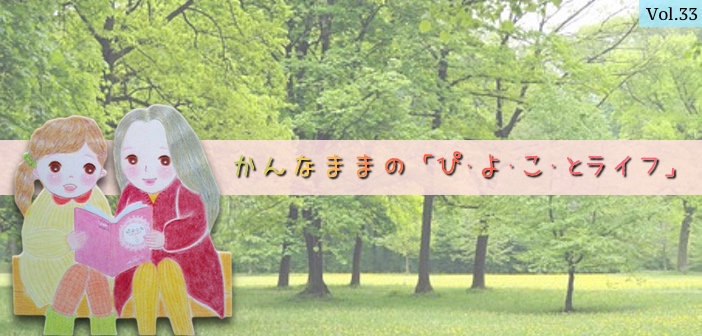







![[temita] シルバーたちの川柳大会のブラックジョークのキレが凄すぎると話題に](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2017/11/1123pepperoni-2936528_1280.jpg)
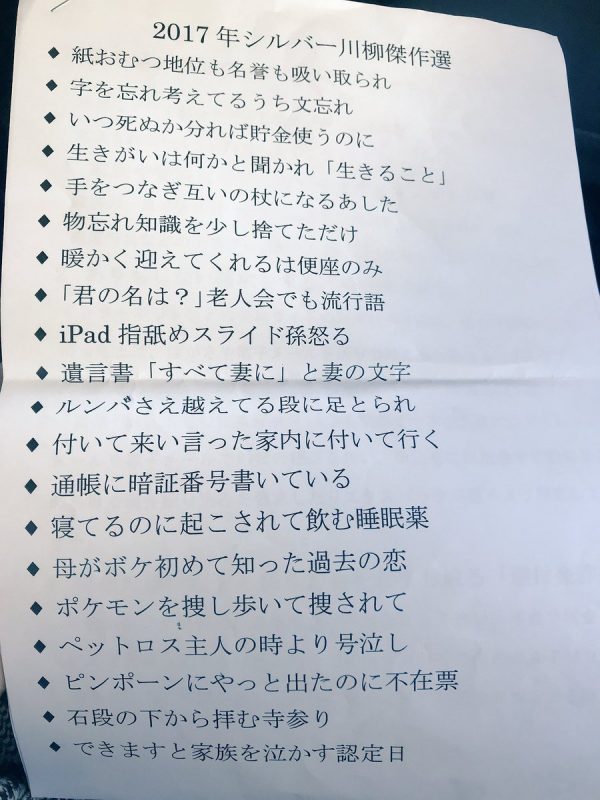

![[第37回] 地球の鼓動・野草便り 草で紙作り・ぞうのウンチの紙](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2017/11/37.jpg)

















その方は、つねに真剣に患者さんと向き合っている方です。
けんめいに治療して、あそこまで良くなっていたのにと無念がっておられました。
医者が放った呪いのことばを、家族はいつまでも忘れることはないでしょう。