注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

故・細田前衆院議長に桐花大綬章を授与 政府が閣議決定
— 島津 未来 🌻86.ZN6 ⋆⸜🐬⸝⋆ (@swg2p) November 14, 2023
セクハラ統一教会議長に勲章。
日本の勲章は貰うと恥のような気がします。https://t.co/Ty8D0T0MeM
逆に考えるんだ。
— 猫のリュックくん (@nasitaro) November 15, 2023
日本政府が統一教会に支配されてるなら勲章をもらうのは当然なのだ。 https://t.co/EiTSG1xCRJ
やっぱりね。そう来ると思ったわ。所詮、自民党は統一教会ってことよ。
— きみ (@kimixasleep) November 14, 2023
旧統一教会の財産保全、自公が法案提出を見送り(毎日新聞)#Yahooニュースhttps://t.co/2VJvcpNAX4
旧統一教会の田中会長「今国会で議論される財産保全措置法の必要性は全くないと考える」“被害補償の資金” 国に最大100億円を供託https://t.co/wjK6t3jzWF
— ニコニコニュース (@nico_nico_news) November 7, 2023
田中富広会長は会見で、全国統一教会被害対策弁護団が試算した「潜在的な被害額1200億円の根拠はない」と主張した。#家庭連合 #旧統一教会 pic.twitter.com/CsxBHDbVr6
(以下略)
» 続きはこちらから

















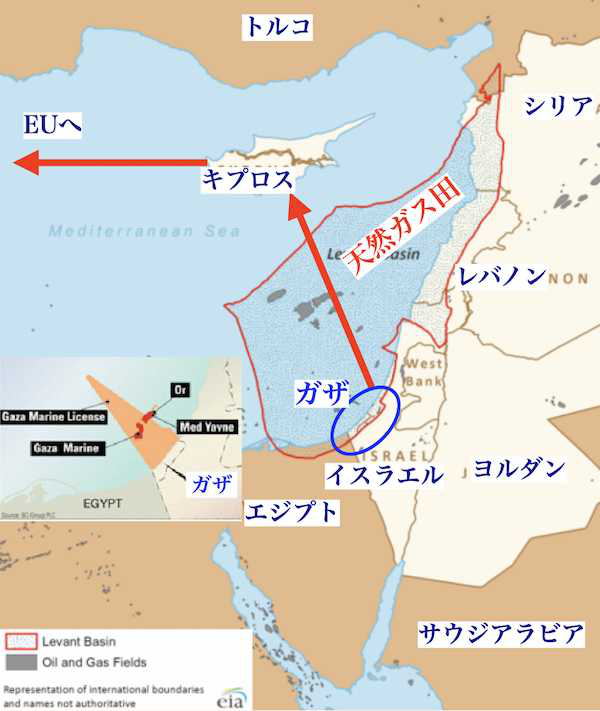




さて自民・公明の与党からなる旧統一教会の被害者救済策の検討チームは、「教団財産の保全を包括的に可能とする新法制定に向けた法案提出」を見送りました。旧統一教会側は「今国会で議論される財産保全措置法の必要性は全くないと考える」その代わり「“被害補償の資金” 国に最大100億円を供託する」とドヤ顔です。潜在的な被害総額の1割にも満たない額で逃げ切りたいらしい。
15日に発表された与党の財産保全スキームは民事保全法を利用するもので、これは「財産保全は被害者任せになってしまっている」「これでは財産保全を放棄したも同然」と指摘されています。
15日の衆院・内閣委員会で、くしぶち万里議員は旧統一教会の「解散命令逃れ」「財産保全逃れ」を取り上げ、教団の財産を保全する法整備が必要だと強調しました。これまで教団の不法行為や目的逸脱行為によって財産を獲得し、巨額の不動産を得てきただけでなく、さらに今また新しい不動産を手に入れ、巨大施設を建設しようとしている問題を知らせました。東京都多摩市の学校が多くある地域に6000㎡以上の土地を取得し、巨大な研修施設を新たに建てる予定になっています。くしぶち議員は、被害者救済を優先させるためにも、土地を保全して利用を制限する、被害者の損害賠償や不当利得返還に充てるのが本来の筋ではないかと指摘しました。
統一教会と一体化した自民党に、本気で被害者救済をする気があるのか。これは投票の大事な判断材料です。