注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

第25回参院選が4日公示され、21日の投開票に向け17日間の選挙戦が始まった。2012年末から6年半余りにわたる安倍政権の“独裁・隠蔽政治”に終止符を打てるかどうかが問われる。
「政治の安定」を掲げ、改選議席の過半数確保を目指す自民・公明の与党に対し、野党は消費増税や年金制度、憲法改正などが争点に、全国で32ある「1人区」で統一候補を擁立するなどして対抗する。
(以下略)
祝500万回再生㊗️🎉
— 小池晃 (@koike_akira) July 3, 2019
pic.twitter.com/qeoS8VLAc7
政界地殻変動の予兆 山本太郎の金集め、小池晃の動画再生|日刊ゲンダイDIGITAL https://t.co/YGqj9DnCiH
— 小池晃 (@koike_akira) July 3, 2019





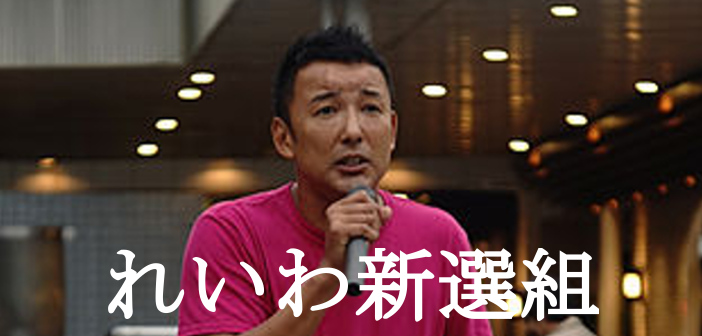






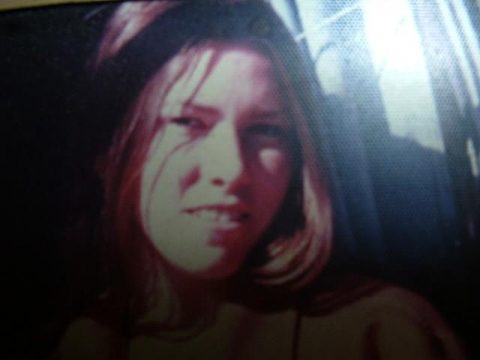




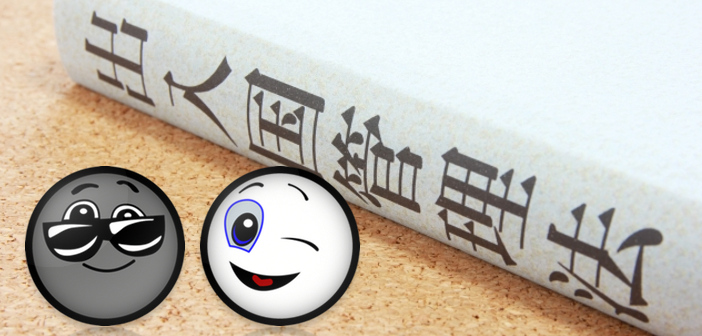



また、年金に関しては、別班マンさんの動画が500万回再生を達成したとのこと。日刊ゲンダイでは、れいわ新選組の話題と合わせ、“政界地殻変動の予兆”と言っています。
れいわ新選組の候補者を見ると、山本太郎氏の本気がビシバシと伝わってきます。本来なら、れいわ新選組を核として野党が集結しなければならないはず。この辺のことは、小沢一郎氏の中で、どんな風になっているんでしょう。