注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
————————————————————————

フルフォード情報英語版:今終わりつつある秘密の戦争に、私がどのようにして関わることになったか
転載元)
投稿者:フルフォード

» 続きはこちらから
はじめに
Notice to readers. So that I may take my annual sabbatical in the Canadian wilderness, the next several reports will be pre-written. They will focus on the history of how I got involved in fighting the Khazarian Mafia. Hopefully, this will help readers get a better understanding of what is happening now. Of course, if something really big happens, we will issue an emergency report.読者の皆様にお知らせがある。私がカナダの荒野で年に一度の休暇を取ることができるように、今回からいくつかのレポートはあらかじめ書いたものである。このレポートでは、私がハザール・マフィアとの戦いに関わるようになった経緯を中心にお伝えする。読者の皆さんには、今起きていることをよりよく理解していただけることと思う。もちろん、何か大きな出来事があったときには、緊急レポートを発行する。
80年代後半、世界を牛耳るチンピラに遭遇
If you are really doing your job as a front-line reporter, it will not take too long before you run into a dark underside of the powers that run the world. In my case, I first ran into the hoodlums who run the world while reporting on the Japanese financial bubble of the late 1980s. Japan was very important at the time because the bubble made the real estate in Japan worth 20 times more than all the real estate in the United States. The stock market too was worth by far more than that of the U.S. With so much money involved, the foreign financial companies and their controlled press wanted in on the action.もし、あなたが第一線の記者として実際に仕事をしていれば、世界を牛耳る権力者の邪悪な面に遭遇するのにそう時間はかからないだろう。私の場合は、1980年代後半の日本の金融バブルを取材しているときに、初めて世界を牛耳るチンピラたちに遭遇した。当時、日本は非常に重要な国だった、というのもバブルによって日本の不動産はアメリカの不動産の20倍の価値があったからだ。株式市場もアメリカよりはるかに価値があった。これだけの大金が動くと、外国の金融機関やその支配下にあるマスコミも、この動きに入りたがっていてた。

1989年に、三菱地所が8億4600万ドル(当時の日本円で約1200億円)
で買収したニューヨークのロックフェラー・センター。
当時の日本企業による国外不動産買い漁りの象徴となった。
で買収したニューヨークのロックフェラー・センター。
当時の日本企業による国外不動産買い漁りの象徴となった。
Wikimedia_Commons[Public Domain]
画像はシャンティ・フーラが挿入
フルフォード氏、レポーターの道を選ぶ
At the time, I was a rare native English speaker who could read a Japanese newspaper and as a result, was offered many lucrative jobs in the financial industry. I chose to become a reporter instead. My first reporting job (with Knight Ridder Financial News) involved going every week to the Finance Minister’s (Kiichi Miyazawa at the time) weekly press conferences so I had a front-row seat at the center of Japanese power.当時、私は日本の新聞を読むことができる珍しい英語のネイティブスピーカーで、その結果、金融業界で多くの儲かる仕事のオファーを頂いた。しかし、私はレポーターになることにした。最初の報道の仕事(ナイト・リッダー・ファイナンシャル・ニュース)では、毎週、大蔵大臣(当時は宮澤喜一氏)の記者会見に出向き、日本の権力の中心を最前列で見ることができた。
» 続きはこちらから









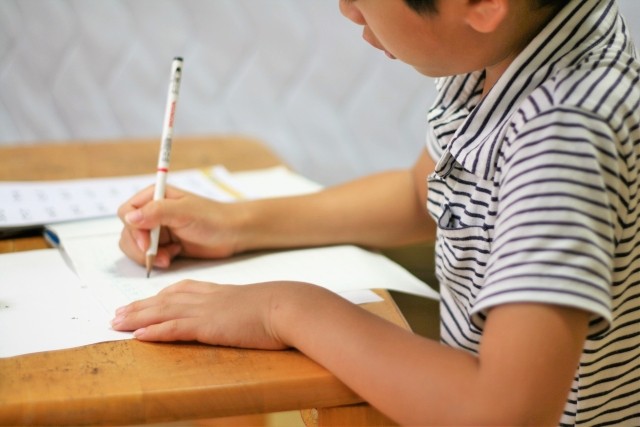


















バブル崩壊後、日本政府が救済したのは、ヤクザにお金を貸していた元官僚らの不動産ローン会社。この時フルフォード氏は自ら「ヤクザに話を聞いてみよう」と思い立ち、ヤクザを紹介してもらい政府とヤクザの関係を知る。その関係はまるで前政権までのメキシコ政府とカルテルの関係と同じ。フルフォード氏は「自殺」とされた日本債券信用銀行の本間忠世社長が殺害されたことを「フォーブス」に掲載したことで、ハザール・マフィアに狙われることに。ちなみに殺害の理由は、本間社長が銀行の全財産が北朝鮮に流れるのを阻止しようとしたから。ハザール・マフィアのブラックリストに載ってしまったフルフォード氏を狙った東京とロシアでの殺人未遂のお話もあり。
毎度のこと命よりもお金が大切なマフィアです。いつもの記事とはガラリと変わり、まるでノンフィクションの小説を読んでいるような感じで最後まで興味深く読めました。こうしてフルフォード氏が生きているのが奇跡なんだと思いました。ピンチの時のフルフォード氏の機転の良さ、勇敢さは、ちょっと男前でした。😁