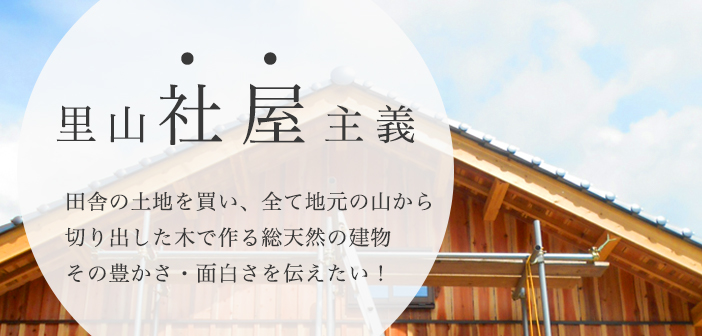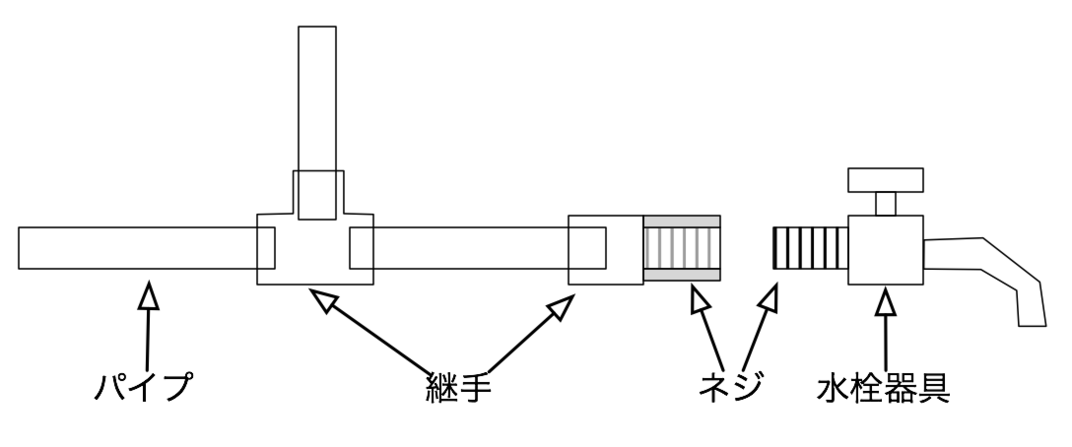ちなみに日本で最も有名な重言というのは、長嶋茂雄氏が現役引退時のスピーチで述べた「我が巨人軍は永久に不滅です」♪

pixabay[CC0]
こちら山口では湿度がグッと下がったせいか、気温がそれほど変わらないのにも関わらず、あまり暑さを感じずに過ごさせていただいておりますが、夏本番真っ只中ですので油断はできません。しかしながら、こんな夏の季節だからこそできることがあります。その一つが今回ご紹介する究極の毒出し法です。
人は日々の暮らしの中で、実にさまざまなものを溜め込んでしまっております。農薬、添加物、放射性物質、電磁波、ケムトレイル、ワクチン、遺伝子組み換え食品、フッ素などなど…しかも目に見えない、ストレスや生霊といったものまであります。もう普通に生き切るのが本当に大変な世の中ですね。
ですので、体からそういったものをときどき強制的に排出した方がいいと思われます。その方法はいろいろありますが、その中でも極めて効果的に毒出ししてしまう方法。。。
それは、砂浴です。
海水浴に行きますと体を砂に埋めるイベントが自然発生すると思いますが、あれは体内の毒素などを強力に排出するとても優れた方法なのです。しかも今の暑い時期にはピッタリですので、もし海水浴に行かれる機会などありましたら、ぜひぜひ試してみてください。(放射能などの問題もあるので、時事ブログ読者はあまり行かないかもしれませんが…) 健康マニアのこのぺりどっとが、もしガンなどの大病にかかったとしたら、真っ先に試す効果絶大な方法でもあります。

pxhere[CC0]
» 続きはこちらから