————————————————————————

メキシコ便り(17):市長選略奪!AMLO氏の厳しいお言葉!マフィア・メディア!
1)ゴリ押し、ファレス市長の不正選挙!
メキシコでは7月1日に史上最大の総選挙がありました。メキシコ便り(15)でもお伝えしたように、popoちゃん在住のファレス市長選挙の結果がのびのびで(候補者第2位、現在の市長カバダ氏が2回ほど数え直すことを要求したため)、最終的に結果が出たのは7月13日。次期大統領ロペス・オブラドール氏と同じMorena党のモッケン氏が勝利!
7月13日に選挙に勝利したモッケン氏が、当日、結果報告の後に紙に著名しているところRecibiendo el acta de mayoría Javier Gonzalez Mocken es alcalde de Cd Juárez. pic.twitter.com/vg170ofSqk
— Héctor F. Ochoa M. (@hector_ochoa_m) 2018年7月14日
そしてたしか任務は9月頃からのスタートのはずだった。。。。のに。。。8月11日(土)朝のテレビニュースでいきなり次期市長はカバダ氏になったと報道!!!え?え?え?どういうこと?!?!😳 popoちゃんもpopoちゃんの旦那さまも、ちょうど朝ごはんの最中で、お箸。。。じゃなくてフォークとナイフを持つ手は止まり、お互い顔を見合わせ「どういうこと?!」。。。一瞬、頭が真っ白に💭!popoちゃんの旦那さまはすぐさまテーブルから立ち上がり、部屋の中をくるくる歩き回り、青ざめた顔😨で「お腹の中の蝶々がバタバタしてきたぁ〜」と。。。気分を害した旦那さまはすっかり食欲を失い、残りのごはん食べれず、呆然としたままくるくる歩き回るばかり。。。(旦那さまが青ざめる理由は、カバダ氏がまた市長になるとpopoちゃん家のお家を手放す可能性が高いため。。。詳細はメキシコ便り(15)をどうぞ!そんな旦那さまをpopoちゃんは横目で見守りながらも、モグモグ。。。しっかり最後まで朝ごはん食べちゃいました。。。😆だって週に一度の大好きなパンケーキだったんだもん!
» 続きはこちらから










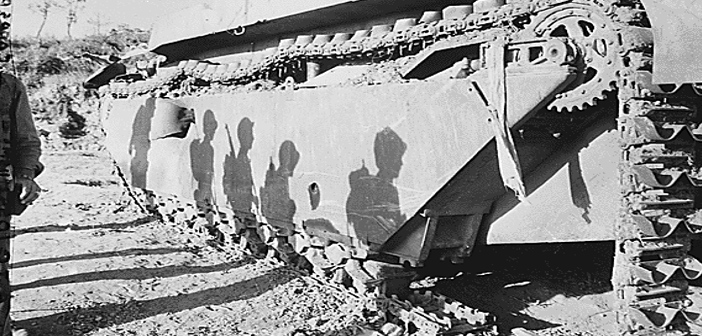







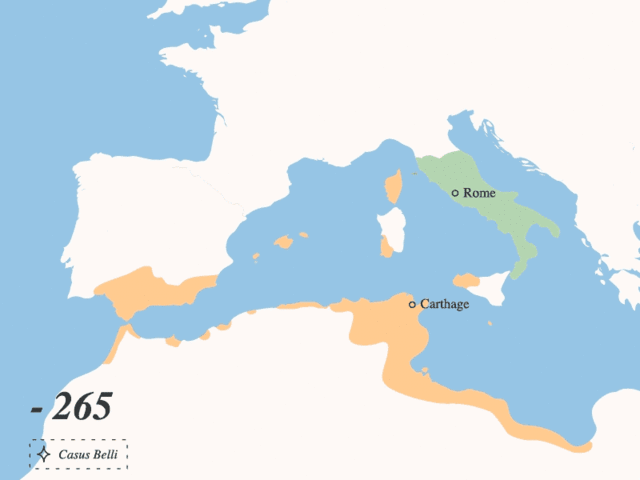









今回は1)2)とローカルな話題です。popoちゃん家の朝食の様子も混ざってますのでお楽しみください♪そしてあのいつも眠気を誘う話し方をするロペス・オブラドール氏が、なんと一変!大変、熱がこもっています。こんなに熱くなるお方だとは。。。知らなかった。。。最後にQへのメディア一斉攻撃!について。。。そしてQのキャッチフレーズに秘密?!発見!!!
2)次期大統領オブラドール氏がファレスにやってきた!
3)マフィア・メディア