注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

スプートニク日本
「この問題は両国間でかなり昔から話し合われており、秘密チャンネルを通じて話し合われている。首脳会談の実施についての合意、実施場所と時間についての合意にさえ達したと言うことができる。このことは明日、米国側と共に発表する。」
ウシャコフ氏は、会談が第3国で行われると付け加えた。
スプートニク日本
中国は「米国の兵器プロジェクトや他の戦略的技術を盗んだ」うえ「世界でも重要な海洋航路の1つを軍事化した。」さらに、米国に約「4万人のスパイ」を送ったとウッド氏は指摘する。さらに、中国防衛産業の急速な成長は米国の存続を脅かす支配的な軍事力へと中国を変える。こうして、中国は世界の大国という米国の地位にダメージを与える。
ウッズ氏はまた、主流メディアが「あらゆるコストを払っても生かし続けている」「ロシアの捜査」という話題のため、米国の人びとはこのことについて知ることがないだろうと指摘する。
「これらの人びとはモスクワの悪魔化につとめている。トランプ米大統領を潰すためだ」との見方をウッズ氏は示す。
トランプ米大統領は、中国が米国を脅かす可能性があることを理解しているとウッズ氏は見ている。そのため、トランプ氏はロシア政府に接近し、プーチン大統領との首脳会談を開こうと試みているという。
(以下略)
米露首脳会談7月16日、フィンランドのヘルシンキでhttps://t.co/gxfHx5TTDo
— 藤原直哉 (@naoyafujiwara) June 28, 2018
ロシアは敵だと浮足立っている米民主党やNATO同盟国は、プーチン・トランプ会談開催が決まって震え上がっている。https://t.co/S6qKe7p5ig
— 藤原直哉 (@naoyafujiwara) June 28, 2018
米露首脳会議開催決定で旧体制は錯乱状態。
— 藤原直哉 (@naoyafujiwara) June 28, 2018
ネオコンの応援団長のボルトンってロシアの二重スパイじゃないの?
そのとおりよ。https://t.co/aRBAVQ3hzu









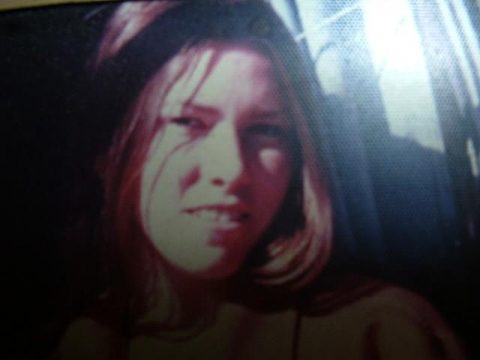
![[Twitter]初めて人間(ダイバー)と出会ったコシオレガニ](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2018/06/u629.jpg)










藤原直哉氏のツイートによると、プーチン・トランプ会談開催が決まったことで、“旧体制は錯乱状態”とあります。これは確かに、こう考えてよいのではないでしょうか。
ジョン・ボルトン氏について多くの人は、ネオコンのタカ派であり、北朝鮮の和平会談を潰し、第三次大戦を引き起こすためにディープ・ステートから送り込まれた人物だとの評価でした。
時事ブログはそうではなく、ボルトン氏はキッシンジャー博士の部下で、現在は世界の平和のために働いており、ボルトン氏の起用は適任であるというコメントをしました。
過去の経歴だけを見ていて現在を見ないと、世界情勢における判断を誤ります。判断する上で、人物の波動を読むことは重要です。ボルトン氏が、例えばアナーハタ・チャクラ以上の高い波動を保っているならば、氏が地球の破壊のために活動しているのではないということがわかります。