注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

山田 正彦さんからの情報です。
— Max (@universalsoftw2) September 27, 2023
高知県馬路村が素晴らしい取り組みを。(日農新聞) 農水省が市町村別に耕地面積に占める有機農業の面積が高いランキングを発表。トップは高知県の馬路村でなんと耕地面積の81%は有機栽培です。JAは他の地域との差別化を狙って化学肥料、農薬、除草剤は使用しない、 pic.twitter.com/36uVfrFj5w
さらに有機栽培に準じた栽培暦を作り。 村も、病害虫防除に役立つ微生物資材や草刈り機の導入など、独自に有機栽培農家を支援して地域一帯で有機栽培を実現したのです。 pic.twitter.com/nUB7IJK75g
— Max (@universalsoftw2) September 27, 2023
高知県馬路村はなんと有機栽培耕地面積が80%。売り上げも上がっていると。すごい。 https://t.co/uRHNOCBrfJ
— 黒い猫やん🐾れいわの自治体選挙はまだ継続中ですよ (@NoirGattonero) September 27, 2023
農政に物申すオーナーが草取りをしながら色々教えてくれます。うむ農園自然栽培チャンネルで聞きました↓https://t.co/2l2EkVo90S
21年は、耕地面積に占める有機農業の割合を50年に25%(100万ヘクタール)に増やす目標を掲げる「みどりの食料システム戦略」の策定初年に当たる。3位は宮城県柴田町で同13%、4位は秋田県小坂町で同11%。上位10市町村の主な品目は米や野菜、果樹など多岐にわたった。
1位の高知県馬路村は、村内の全てのユズ農家が有機JASの基準に沿って栽培する。ユズ加工品を全国の消費者に販売するなど、産地一体の取り組みが数値に表れた。JA馬路村の担当者は「傾斜地が多く、農業には不向きな地域だが、独自の農業路線を築いてきた。今後も差別化を図り、村の産業や自然を守りたい」(加工販売課)と意気込む。
2位の山形県西川町は高齢化や担い手不足で稲作を断念した農地の荒廃を防ぐため、ソバの有機栽培に乗り出した。ただ、国の水田活用の直接支払交付金の見直しで、5年間水張りしない農地が交付対象から外れ、収量が少なく単価が安いソバ栽培の先行きは見通せないという。
(以下略)





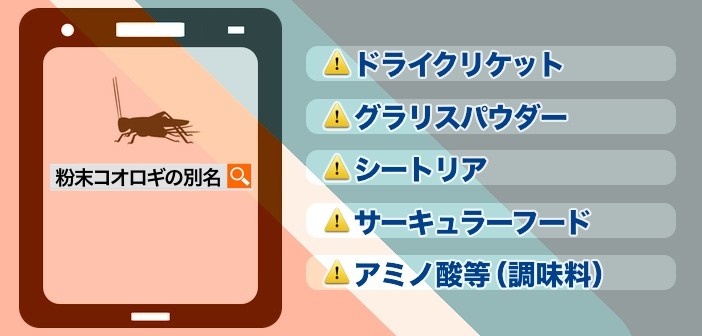




![[鈴木宣弘先生×山田正彦先生] 崩壊寸前の日本の農業、自家採種禁止の取り締まり監視機関が今年中にも設置 〜 対抗策は消費者と生産者の信頼に基づくネットワーク](https://shanti-phula.net/ja/social/blog/wp-content/uploads/2023/09/m916-1.jpg)





さらにJA馬路村は「有機栽培に準じた栽培暦を作り、ユズや木の皮から作った堆肥を無料で配布」したり「担い手のいない畑の管理も請け負う」など地域一体で有機栽培を後押ししたとあります。高価な農機具や農薬を売りつけるJAのイメージとはずいぶん違っていて頼もしいと感じました。
一つだけ気になったのは、今回のランキングが農水省の「耕地面積に占める有機農業の割合を2050年には25%(100万ヘクタール)に増やすことを目標とする『みどりの食料システム戦略』」によるものだという点です。農水省が国民のための農業を進めるとは思えない現状で、素直に有機栽培を増やすとは考えにくい。「これまでの化学農薬に代わってRNA農薬(昆虫の細胞の中でのタンパク質の発現を変える、つまり遺伝子の働きを変える農薬)が開発され、そうした農薬が『安全』」な有機栽培に適うものだとされてしまわないか、有機栽培の定義を勝手な国際ルールに置き換えられないか、私たち国民がしっかり監視をして食を守る情報を拡散するなど主体的に関わっていかなければと思います。