百溪英一(ももたにえいいち) 一般社団法人比較医学研究所所長を務める。また、東都医療大学客員教授、国際ヨーネ病学会理事、順天堂大学医学部協力研究員として研究に携わっている。元動物衛生研究所ヨーネ病研究チーム長、元東京医科歯科大学非常勤講師
一般社団法人比較医学研究所HP
世界で蔓延するヨーネ病と粉ミルク汚染
~唯一清浄化が可能な国の酪農・畜産振興作戦~
国際ヨーネ病学会理事 百溪英一
はじめに
牛など家畜の伝染病であるヨーネ病が世界的に大流行している。ヨーネ病をひき起こすヨーネ菌は直接人間に感染することはないと考えられてきたため、その実態は一般にはあまり知られていない。
しかし、人間の難病であるクローン病や、多発性硬化症など自己免疫疾患の原因になっていることを疑う研究報告は非常に増加してきており、国際的に研究が積み重ねられてきた。
クローン病や多発性硬化症など自己免疫病の患者数は増加の一途をたどっている。クローン病はもともと20歳前後で発症するケースが多かったが、近年、低年齢化し、ゼロ歳児が発症した事例も報告されている。その解明が急がれるなか、
私たちの研究で、ヨーネ菌に汚染された牛の牛乳を通じて排出される菌がこれらの発病に関連していることが明らかになってきた。生きた菌だけでなく、
死んだ菌を体内にとりこむことが、神経難病である多発性硬化症(自己免疫疾患)やクローン病発症の一因となっている可能性が非常に高い。
研究の途上ではあるものの、海外のヨーネ菌汚染状況は深刻であり、撲滅が不可能なほど感染が広がっている。
ヨーネ菌は、ほぼ100%輸入牛乳を使用して製造されている赤ちゃん用の粉ミルクに死菌が含まれていることは疑いない状況であり、それが乳幼児のクローン病を増加させている可能性も否定できない。
一方で日本は長い期間、税金を投じて国家防疫の対策をしてきた結果、撲滅が可能な水準にあり、清浄化農場も多いことから、本気でとりくめばヨーネ菌フリーの原乳を原料にして、ヨーネ菌フリーの粉ミルクを製造することもできる状況にある。そうすれば子どもたちが難病にかかる可能性をより低くすることができるかもしれない。とくに、家族に自己免疫疾患を持つ家庭に生まれた乳幼児にこれを供することができれば発症リスクを低減できる可能性もある。さらに
重要なことは、ヨーネ菌フリー牛乳、チーズそして粉ミルクを製造することのできる国は日本だけといっても良いことから、世界中から日本の安心な牛乳や乳製品を買いに来る状況をつくって酪農業を大きく発展させる道筋も開けることだ。農水省は安心・安全をスローガンに掲げているがあえてヨーネ病を撲滅しない施策をとっている。
今後、TPPや日欧EPA、日米FTAによって、海外から成牛の輸入が増加することが考えられ、国民の税金を投じて撲滅直前まできたヨーネ病を逆に大流行させる危険性がある。さらに、現在日本では国内産の乳製品を購入できるが、
酪農業が衰退・淘汰されてしまうと、ヨーネ菌汚染された海外の乳製品を買うほかなくなることを心配している。またヨーネ菌に汚染された乳製品の輸入量がさらに増えて、食卓に並ぶことが人体に与える影響も無視できない。ヨーネ病について広く知っていただき、考えていただく機会になることを願っている。
» 続きはこちらから






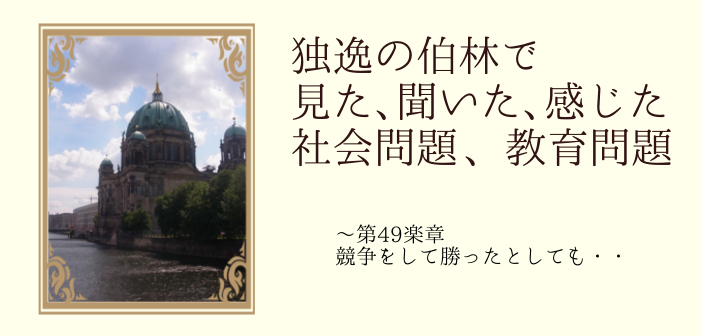









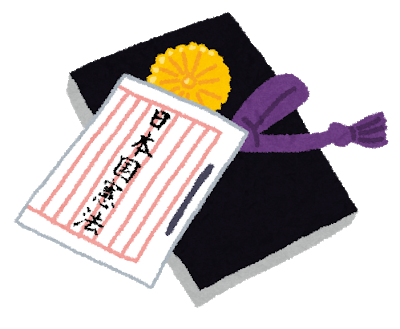







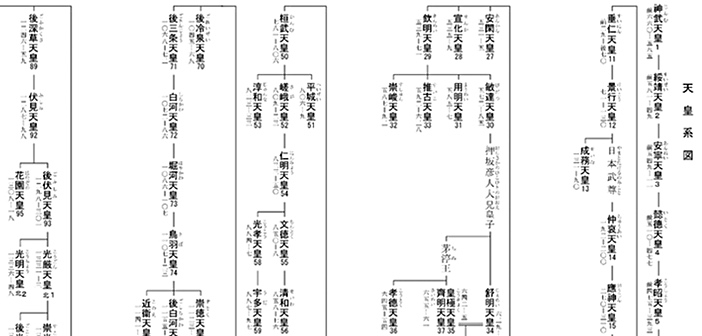


“ベルリンの壁崩壊30周年 平和の革命”(“ 30 Jahre Friedliche Revolution – Mauerfall ”)
ということでベルリンの数カ所にて様々なイベントが開催されました。
現在の語学学校の先生は、他の国で平和の革命ある? ないでしょう?
30周年記念にベルリンにいることはラッキーなことだ・・
と言っていました。
しかし、これは、西ドイツ出身の方の見方かもしれません。
第48楽章で書きました東ベルリン出身の先生は、
ドイツ統一をしたことで、自由になったけれど、
負けたような気がした・・すべての価値観が変わった・・
と言っていましたが・・。
第49楽章は、競争をして勝ったとしても・・です。