孫たちとの渓流遊び
8月1日に孫軍団がやってきました。お父さんの病気もあって、どこにも遊びに行けない孫たちは夏休みにばあばの家に行くのを楽しみにしていました。ところが外は猛暑。室内の遊技場は人だかり。
孫たちの期待に応えるには渓流遊びしかないと、連日川へ遊びに行きました。
もちろん息子の子ども達も、お嫁ちゃんも、夫も
総出で川探検です。食べて、川で遊んで、遊んで、遊んで、寝て、洗濯物をいっぱい出してお盆前に帰っていきました。
帰りの新幹線のホームで、みんなのテンションが下がります。ああ~宿題が、受験が・・・と、現実に戻らなければいけません。
でも、その瞬間だけでも楽しめてよかった!中学3年生から2歳まで、みんな好奇心と冒険心を持ってよかった!誰一人ゲームをすることなく過ごせてよかった!
今の時代、子どもらしく遊ぶには努力が必要なのです。
「又いらっしゃい!」と見送った言葉に嘘はないけど、体力も限界でした。
「えっ!待って。さよならを言ってない」
静かなお盆を過ごしてホッとしたのもつかの間、
義母のグループホームから電話が入りました。朝の6時半です。
電話の声が震えています。
朝、義母を起こしに行ったらお布団の中で亡くなっていたとのこと。
私の最初の思いは「えっ!待って。さよならを言ってない」でした。覚悟はしていましたが、あまりにも突然で夢を見ているようです。
前の日も完食。快便。
いつものように「おやすみ」を言ってベッドに入り、そのままだったようです。まさに95歳の大往生です。
コロナ禍でずっと面会制限があり、直前まで面会謝絶でした。義母の荷物を届ける時に後姿をそおーっと見たのが最後でした。
警察が入り、死亡確認ができて、義母に会えたのはお昼近くでした。家族葬と決めていたので子ども達や身近な親戚にだけ知らせました。
遺体を運ぶため霊柩車とお寺の手配をしました。
すぐに必要になる遺影、最後に着せてあげる母の好きな洋服、死亡手続きに必要な保険証、マイナンバー通知、固定資産税などの書類、通帳、印鑑・・・母が認知症になったおかげですべて私が管理していましたのでスムーズにいきました。それでも、次々にしなければいけない手続きがあって気が上がってしまいます。
離れて暮らしている人、家のどこに何があるのか知らない遺族は大変だと思いました。
葬儀社との話し合いも、こちらがどのような式を挙げたいのか決めていないと迷います。ランクがいろいろあって次々に加算されていきます。
お寺との打ち合わせもあります。先祖代々のお墓があるお寺です。我が家は夫で54代目(らしい)。先祖の碑があり家系図には男の名前がありますが、女性は女としか書いてありません(笑)
先代のご住職が亡くなられて、戒名などにお金をかけなくてもいいというお考えの方に代わられていたので助かりました。こちらの意思を尊重してくださいました。
生前の義母が好きな華やかな花と、お気に入りのプアゾン(毒!)という名の香水をふって、カラオケでよく歌っていた「糸」の曲を流して送ることにしました。


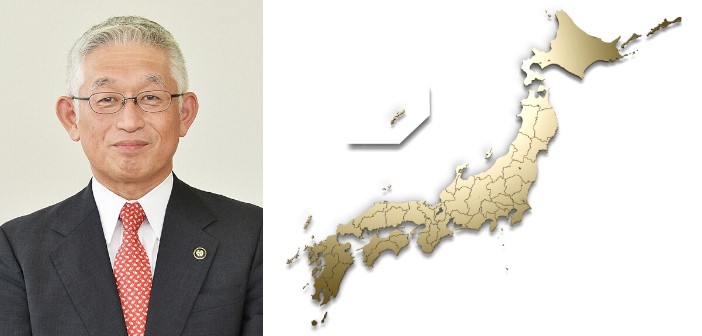

















泉房穂氏が明石市の市長時代に子育て支援策を軸として「人口減少、財政赤字、駅前衰退」の三重苦を見事に逆転させ「人口増加、財政黒字化、駅前活性化」されたことは、今や有名です。
三橋貴明氏が「予算を決めて何かやる場合に、すぐには経済効果が出ない。成果が出るまでの不満に対して"しばらくすればあなたも豊かになるから待ってくれ"と説得するのが政治だが、当面不満を持つ市民にどう説得したのか」と質問しました。
「(市長になった)12年前から、今の時代は子供に投資をしたら、みんなが幸せになるからちょっと順番待って。子供を応援すると子育て世帯はお金を使う、地域経済が回って商店街が豊かになる、人気が出て街が元気になると人口が増えて建設ラッシュが起こるから待っときなさい、と説明したが、なっかなか皆さん納得しなかった。商店街のアーケードを作れ、公共事業を増やせと。アーケードをきれいにしても人は増えない。明石の市民が金を落とせるようにします、私がやっているのは地域経済支援策、つまり商店街対策なのだから、必ず儲かるから、ちょっと待って下さいと説得した。それでも批判が来るが成果が出る自信があった。5、6年経った頃から一気に客が増えて、商店街はウハウハで。空き店舗なんか一件もない。以前はテナントに補助金を出して空き店舗に入れていたがそんなん意味ない。本来の経済対策というのはちゃんと消費ができるようにすること。」と振り返りました。政治家には市民を説得し導く度量が求められ、市民には目先の利益に惑わされない賢明さが求められるのだとわかりました。
今回初めて知った話題で「タコマネーを発行したかった」と、地域通貨の話をされていました(10:16〜)。最初は明石市職員のボーナスを1割増にして、その部分をタコマネーで支給したかったそうです。三橋氏は「イケたと思うんだけどなあ」泉氏も「市長最後の頃だったらイケたかも」とお二人とも残念そうでした。見てみたかった、タコマネー。