ジミー・カーター退場に利用された事件
イラン-イスラム革命に付随して起きたイランアメリカ大使館人質事件、これが引き起こしたドラマは、ジミー・カーターの大統領からの退場でした。
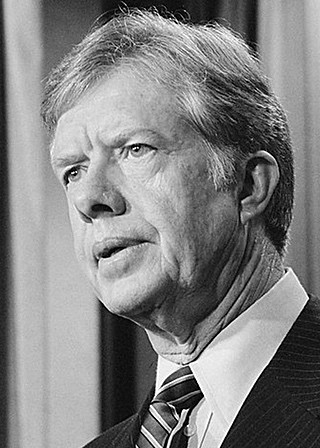
ジミー・カーター大統領
イラン-イスラム革命が成立した1979年、皇帝モハンマド・レザーは1月に国外退去、10月に米国に入国、米国入国に激怒したイラン国民によってイランのアメリカ大使館が11月に占拠され、大使館の人間などがモハンマド・レザーの引き換え要求としての人質に取られました。これがイランアメリカ大使館人質事件です。

テヘランのアメリカ大使館の塀を乗り越えるイスラム法学校の学生たち
この後、
カーター政権は大使館の人質開放のための作戦をことごとく失敗、これでカーター政権は批判の的となり、1980年11月の大統領選挙でジミー・カーターは敗退します。米大使館事件がカーター敗退の最大要因といってもよく、この事件は次のロナルド・レーガン就任と同時に解決しています。
そもそもカーターは、元イラン皇帝の米国入国には反対だった模様です。
しかし、「パフラヴィー元皇帝の友人だったヘンリー・キッシンジャー元国務長官らの働きかけを受け、最終的に『人道的見地』から入国を認め」(ウィキペディア「イランアメリカ大使館人質事件」)、カーター自身の首を絞める事件へと発展していったのです。

ヘンリー・キッシンジャー
ここでもやはりキッシンジャーです。イラン革命に付随する米大使館事件が、カーター大統領退場に利用されたとの見方も成立するでしょう。
ジミー・カーターは1977年に大統領に就任しています。
カーター政権の外交政策は「人権外交」と呼ばれ、1978年には長年対立していたエジプトとイスラエルの間の和平協定「キャンプ・デービッド合意」を締結させています。

編集者註:左からイスラエル首相ベギン、アメリカ大統領カーター、エジプト大統領サーダート。中東和平の枠組みとエジプト・イスラエル平和条約の枠組みからなる和平合意を米国のキャンプ・デービッドで交わした。
ただし問題になるのが、ウィキペディアの「ジミー・カーター」記事の「
外交政策」欄の
次の記述です。
1977年3月16日にマサチューセッツ州クリントンで行われたタウンミーティングにおいて、アメリカ大統領として初めてパレスチナ人国家建設を容認する発言をした(しかしながら、この発言がユダヤ系アメリカ人の反感を買い、先に述べた1980年アメリカ合衆国大統領選挙の敗北の一因となった)。
『櫻井ジャーナル』
2017.05.30記事では、
「1976年の大統領選挙で勝ったジミー・カーターはブレジンスキーとデイビッド・ロックフェラーが後ろ盾になっていた人物。」との指摘があり、同記事にはそのカーター政権の安全保障補佐官となったズビグネフ・ブレジンスキーについて次の記述があります。

ズビグネフ・ブレジンスキー
ハーバード大学で博士号を取得、後にコロンビア大学で教えるようになる。このころかCIAと関係ができたと見られているが、その一方でデイビッド・ロックフェラーと親しくなる。
カーターは、ロックフェラーらの思惑で大統領に就任するも、イスラエルのパレスチナ問題などで彼らの思惑に外れた行為をとっため、イランの米大使館事件を起こされ、更迭されたというの本筋でしょう。
» 続きはこちらから
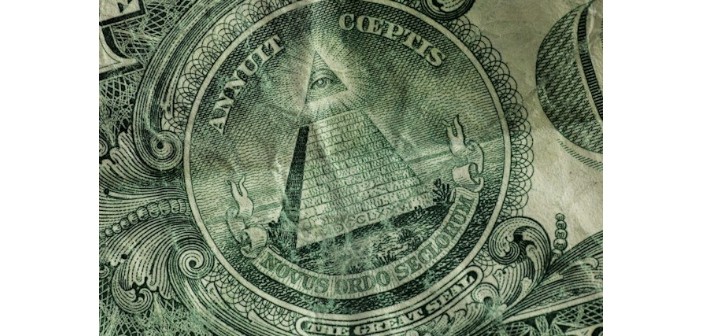





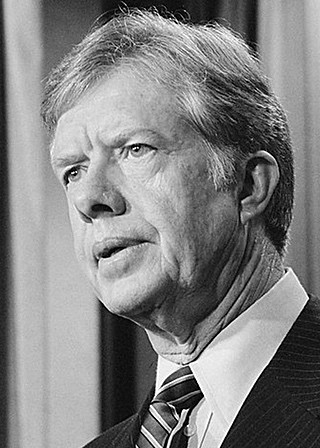





イタコ芸でチャーリー・マンガー氏の霊を呼び寄せて、米軍がベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領を拘束した理由を説明してもらった…ということではないようです。
ですから動画の内容は真剣に受け止めるようなものではないのですが、かなり鋭い。
“ドルという紙切れに価値を持たせ続けるには何が必要か? それは信用ではない。暴力と石油だ。世界中の国々がなぜドルを持つのか? それはドルが好きだからではない。エネルギーを買うためにドルが必要だからだ。石油取引の決済通貨としてドルが使われる限り、世界中の中央銀行はドルの準備高を維持しなければならない。これが過去半世紀にわたってアメリカが享受してきた法外な特権の正体だ(1分53秒)。…ベネズエラで起きたことを麻薬戦争という言葉で片付けるのは思考の放棄に他ならない。あれは地政学的なメッセージだ。もし誰かが石油をドル以外の通貨で売ろうとしたり、自国の資源を完全に国有化してドルの循環システムから離脱しようとすればどうなるか。その答えがあの爆発だ(2分35秒)。…あの国の地下にある黒い液体がドル以外の通貨、例えば人民元やルーブルで取引されることを阻止するための防衛線だ。考えても見て欲しい。もし世界中のエネルギー取引からドルが排除されたらどうなるか。アメリカ国内に戻ってくる大量のドルはハイパーインフレを引き起こすだろう。アメリカの生活水準は劇的に低下する。それを防ぐためなら、どんなことでもするのが国家というものだ(3分44秒)。…作用には必ず反作用がある。圧力をかければかけるほど反発力は増す。世界中で起きている脱ドル化の動きは、この反作用の結果だ。ベネズエラを追い詰めれば追い詰めるほど、彼らは代替的な決済手段や新たな同盟関係を模索する。それは結果としてドルの寿命を縮めることになる。皮肉なことだ(8分9秒)。…一つ確かなことは、どんなに強力な軍事力を持ってしても経済の重力には逆らえないということだ。借金は必ず返さなければならない。形はどうあれ、必ず清算の日が来る。それがデフォルトなのか、ハイパーインフレなのか、あるいは戦争による帳消しなのかは誰にも分からない。だがその日が近づいていることを、カラカスの爆発は告げている。(17分15秒)”と説明しています。
「ベネズエラは始まりに過ぎない。ベネズエラでの米国の動きはマドゥロのことではなく、中国のエネルギー生命線を支配することにある。」という見解もあります。
2025年12月5日にトランプ政権が公表した『国家安全保障戦略』に従って、「南北アメリカ大陸を含む西半球を重視する方針」を実行に移しています。トランプは「グリーンランドは必要だ。今やロシアと中国の船がウジャウジャいる」と発言していますが、スペインの政治家エンリケ・サンティアゴ氏は、“最悪なのは欧州連合の態度です。起きたことに対しての非難に力強さが欠けています。…次の標的がグリーンランドやカナダ、あるいはコロンビアやパナマになることは疑いようがないからです。”と話しています。